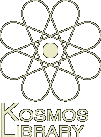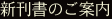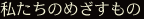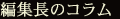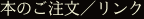そんな中で小社もなんとか下記の新刊を出すことができました。
(1)『心理療法の彼岸 ◎ 加藤清翁卒寿記念論文集』(1月17日)
(2)『五つの約束:自己修養のための実用ガイド』(2月8 日)
(3)『あるパワーの探求(2) 今すぐ駆け出すように旅に出たら〈完結編〉』(4月24日)
(4)『『静かな精神の祝福──クリシュナムルティの連続講話』(5月22日)
(5)『『夜と霧』 ビクトール・フランクルの言葉』(7月8日)
(6)『人間中心の教育──パーソンセンタード・アプローチによる教育の再生をめざして』(7月20日)
(7)『愛とその失望──人生の意味、セラピーと芸術』(9月9日)
(8)『あるパワーの探求(3)「サブリナの法則」──人生はすり鉢の底で月がほほ笑む』(10月25日)
特に(5)の『『夜と霧』ビクトール・フランクルの言葉』は、ちょうど8月にNHK 教育テレビが「100分で名著」で『夜と霧』を取り上げ、著者の諸富祥先生が解説者として登場し、また4回シリーズの最終回には姜尚中さんが加わったこともあり、関連書としてけっこう話題になりました。大変ありがたいことです。
今年もいろいろ工夫して出したいと思っており、第一陣として次のものを月末までに出します。これについては追って新刊案内でご紹介します。
貴船哲治著『抑鬱の文化と文化の抑鬱』 また、クリシュナムルティ著『伝統と革命──J・クリシュナムルティとの対話』(拙訳)を2月に出す予定です。これについては、予告編として「訳者あとがき」をPDF で添付しますので、よかったらご一読ください。
他にもいろいろ計画していますので、よろしくお願いします。
「伝統と革命」訳者あとがき
◎『昭和の動乱』(重光葵)著、中央公論社) 最後に、最近読んだ本をご紹介させていただきます。著者は重光葵(しげみつまもる)さんで、上巻は昭和27(1952)年3月25日に、下巻は同年4月13日に刊行されています。上下とも300頁あまりあり、小さい字でびっしり書かれているので読むのがけっこう大変です。Wikipediaには著者について次のように書かれています。
文官高等試験外交科合格後の1911年(明治44年)年9月、外務省に入省(第20回、芦田均・堀内謙介・桑島主計らと同期)、在ドイツ・在英国各公使館書記官、在シアトル領事を経て、各国において日本国公使として勤務していたが、1930年(昭和5年)には駐華公使となる。1931年(昭和6年)9月、日本陸軍の一部が突如中国東北部を制圧しようと満州事変を引き起こし国際問題となる。これに対し重光は「明治以来積み立てられた日本の国際的地位が一朝にして破壊せられ、我が国際的信用が急速に消耗の一途をたどって行くことは外交の局に当たっている者の耐え難いところである」(重光著『昭和の動乱』より)と怒り、外交による協調路線によって収めようと奔走。1932年(昭和7年)1月、上海事変が起き重光は欧米諸国の協力の元、中国との停戦交渉を行う。何とか停戦協定をまとめ、あとは調印を残すだけとなった同年4月29日、上海虹口公園での天長節祝賀式典において朝鮮独立運動家・尹奉吉の爆弾攻撃に遭い重傷を負う(上海天長節爆弾事件)。重光は激痛の中「停戦を成立させねば国家の前途は取り返しのつかざる羽目に陥るべし」と語り、事件の7日後の5月5日、右脚切断手術の直前に上海停戦協定の署名を果たす。このとき重光の隣でやはり遭難し片目を失った海軍大将の野村吉三郎ものちに外務大臣、そして駐米大使となり、日米交渉の最前線に立っている。なお、弁当箱状の爆弾が投げつけられた時、逃げなかったことについて「国歌斉唱中だったから」と答えている。
重光さんは1887年生まれなので、右脚を失った1932年には45歳です。それから1957年に亡くなるまで25年間義足をつけて外交官としての激務をこなしたのです。Wikipediaにはさらに次のように記されています。
(右脚切断)以降公式の場においては重さ10kgの義足をつけるようになった。義足をつけた状態での歩行は大変な困難を伴うものだったのにもかかわらず、彼自身はその事を気にする素振りはなかった。後年ミズーリ号甲板上に重光を吊り上げるために四苦八苦するアメリカの水兵たちを尻目に、重光はまったく臆することなくただ悠然と構えていたという。
この冷静沈着ぶりは並大抵のものではありませんが、この鋼のような精神が『昭和の動乱』全編を貫いているのです。通読していて、編者はまずこのことに強い感銘を受けました。外交官、そして最後には外務大臣としてみずからが関わった動乱の時代の出来事を、驚くほど客観的に記録しており、自分自身のこともいわば戦乱の巷を舞台とした劇中の登場人物の一人として冷静に記述しています(自分のことを「記者」と呼んでいます)。超越的な視点(今風に言えば「メタ視点」)から大戦の全容を、満州事変から書き始め、1945年9月2日の「降伏文書」調印という、わが国の歴史上でも類例のない出来事への自らの関与と、その直後の状況まで正確に記しているのです。この文書の調印に関する記録は感動的なものなので、そのままご紹介します(一部,当用漢字に改めました)。
戦争が一日にして止んだ當時の、日本指導層の心理状態は特異のものであつた。戦争の終結、降伏の実現について責任を負ふことを極力嫌忌して、その仕事に関係することを避けた。この空気において降伏文書の調印に當ることは、公人としては破滅を意味し、軍人としては自殺を意来する、とさへ考へられた。
記者は自ら久しく待望した終戦が、遂に実現したのみならず、今やその決定的最後手続を処理する地位にあるのであるから、精神をこめて事に當り、専心、重大なる最後の御奉公をする覺悟であった。爆弾に見舞はれるくらゐは豫期したところであったが、それよりも何よりも、降伏が日本の将来を生かす道であることを、心から祈った。
記者は自ら久しく待望した終戦が、遂に実現したのみならず、今やその決定的最後手続を処理する地位にあるのであるから、精神をこめて事に當り、専心、重大なる最後の御奉公をする覺悟であった。爆弾に見舞はれるくらゐは豫期したところであったが、それよりも何よりも、降伏が日本の将来を生かす道であることを、心から祈った。
他の指導者たちのほとんどが嫌がった仕事を、逆に嬉々として引き受けているのです。まさに「メタ視点」なしにはできない偉業です。そして、いよいよ調印当日の記録です。
降伏文書の調印には、陸海軍軍統帥部から各一名を選ぶ必要があると考へられた。従って、天皇及び政府を代表するものもまた、二名を指名することを適當とする案を立てた。記者は、この案によって、外務大臣の外、先づ総理若しくは副総理の奮起を促した。これは天皇を直接代理する意味において適當と認められたのであったが、実現を見なかった。結局、各一名宛の代表を任命することとなって、天皇及び政府を代表するものとして外務大臣、統帥部を代表するものとして参謀総長を任命することとなって、記者は、梅津参謀線長と共に、その任に當ることとなった。天皇陛下は、梅津及び記者を別々に御召しになって、懇々使命の重大なるを託された。
記者は外務大臣として、また天皇及び政府の代表として、我が歴史上未曾有のことでぁる降伏文書調印に當る全権代表として、天皇陛下に拝謁した時に次のやうに内奏した。
「降伏文書に調即するということは、実に我が国有史以来の出来事でありまして、勿論不詳事であり、残念でありますが、これは、日本民族を減亡より救ひ、由緒ある歴史及び文化を続ける唯一の方法でぁりますから、眞に己むを得ないことでぁります。日本は古来一君萬民の国がらであり、陛下は萬民の心をもって心とせられることは、記者等陛下に咫尺(しせき:拝喝)するもののよく拝承するところでぁります。これが、今までややともすれば、権力を有するもののために、曲げられたことがあったので、日本が今日の悲境を見ることとなりました。ポツダム宣言の要求するデモクラシーは、その実、我が国がらと何等矛盾するところはないのみならず、日本本来の姿は、これによって却って顕はれて来ると思はれます。かやうな考へ方で、この文書に調印し、その上で、この文書を誠実に且つ完全に実行することによつてのみ、國運を開拓すべきであり、またそれは出来得ることと思はれます。」
天皇陛下は、この趣旨を深く嘉納せられ、「まことにその通りである」とのたまひ、あくまでその方針で行かうと激励遊ばされた。
九月二日は夜明け後、直ちに総理官邸に集合して、梅津全権及び随員一同とともに官城を拝し、横濱に向った。沿道未だ人影なく、見渡す限りの焼野原で、その間に罹災者の群は黙々として燒跡を漁って居り、戦痕はまざまざと眼前に展開された。
敵軍の占領してゐる横濱埠頭から、米國駆逐艦によって、約一時間、東京灣を埋めてゐる米英の軍艦の中を縫って、ニミッツ提督の旗艦ミズリー號に到着した。二百十日は昨日であるにも拘はらず、海上は平穏で、朝日がさして来た。ミズリー琥の艦橋を攀ぢて、甲板衛兵の敬禮を受けて、更に上甲板の式場に上った時は、すでに十時に近い時であつた。
式場は、すでに敵側の見物人や、新聞記者や、写真班で一杯であった。日本人新聞記者の知り合ひの顔も見えた。シンガポールで降伏したパーシブァル英将軍や、バタン半島で降伏したウェーンライト米将軍等も、参列員の中に特に列んでをった。庭狭きまでに満たされてゐた式場に、各国代表が机を隔てて我々と遠く向ひ合った後に、マッカーサー總司令官が出て来て、直ちに演説を始め、戦ひの終結したことを宣言し、降伏文書に署名を求めた。先づ、記者が署名を終り、次いで梅津大将も同様署名した。マッカーサー總司令官は、日本側の降伏を受け入れる意味で署名し、次いで各国代表が同様署名した。米国の代表者は、海軍のニミッツ提督で、英國代表はフレーザー提督であった。ソ連や支那の代表者も参加した。
珍らしい天氣で、ミズリー號甲板の上に立つとき、夏の名残りの富士山が東京灣上に聳えて見えた。開戦當初、シンガポール近海で撃沈された、プリンス・オブ・ウェールス號の姉妹艦ジョージ五世號も、銀色のスマートな巨体を浮べてゐた。
我々は、もとの経路で横濱埠頭に引き返して、東京に引き上げた上、政府に報告し、更に宮中に参内して、天皇陛下に復命して、重大任務を終了した。数千年の歴史はこれで一應閉ぢて、新日本の歴史がこれから始まることとなった。否、数千年の歴史が、これによって初めて継続して行き得ることとなった。いづれにしても、これから新日本が始まることは確かである。しかし、その新日本の建設は、なほ昭和日本革命でぁるのである。新日本の将来は、全く日本民族の能力と努力の如何に懸つてゐる。
人々は、「敗戦による勝利である」といふ意見を吐いた。日本がこれまでのやうでは、勝っても前途は駄目である。心を入れ換へて萬事新たに出直せば、繁榮もし生き甲斐もある。一旦苦悩の底を経てこそ、初めて立派になり得る、といふ意味である。記者はこれを否定することは出来なかったが、さらに国家の前途を深刻に考へて、悲痛の念を禁ずることが出来なかった。
記者は外務大臣として、また天皇及び政府の代表として、我が歴史上未曾有のことでぁる降伏文書調印に當る全権代表として、天皇陛下に拝謁した時に次のやうに内奏した。
「降伏文書に調即するということは、実に我が国有史以来の出来事でありまして、勿論不詳事であり、残念でありますが、これは、日本民族を減亡より救ひ、由緒ある歴史及び文化を続ける唯一の方法でぁりますから、眞に己むを得ないことでぁります。日本は古来一君萬民の国がらであり、陛下は萬民の心をもって心とせられることは、記者等陛下に咫尺(しせき:拝喝)するもののよく拝承するところでぁります。これが、今までややともすれば、権力を有するもののために、曲げられたことがあったので、日本が今日の悲境を見ることとなりました。ポツダム宣言の要求するデモクラシーは、その実、我が国がらと何等矛盾するところはないのみならず、日本本来の姿は、これによって却って顕はれて来ると思はれます。かやうな考へ方で、この文書に調印し、その上で、この文書を誠実に且つ完全に実行することによつてのみ、國運を開拓すべきであり、またそれは出来得ることと思はれます。」
天皇陛下は、この趣旨を深く嘉納せられ、「まことにその通りである」とのたまひ、あくまでその方針で行かうと激励遊ばされた。
九月二日は夜明け後、直ちに総理官邸に集合して、梅津全権及び随員一同とともに官城を拝し、横濱に向った。沿道未だ人影なく、見渡す限りの焼野原で、その間に罹災者の群は黙々として燒跡を漁って居り、戦痕はまざまざと眼前に展開された。
敵軍の占領してゐる横濱埠頭から、米國駆逐艦によって、約一時間、東京灣を埋めてゐる米英の軍艦の中を縫って、ニミッツ提督の旗艦ミズリー號に到着した。二百十日は昨日であるにも拘はらず、海上は平穏で、朝日がさして来た。ミズリー琥の艦橋を攀ぢて、甲板衛兵の敬禮を受けて、更に上甲板の式場に上った時は、すでに十時に近い時であつた。
式場は、すでに敵側の見物人や、新聞記者や、写真班で一杯であった。日本人新聞記者の知り合ひの顔も見えた。シンガポールで降伏したパーシブァル英将軍や、バタン半島で降伏したウェーンライト米将軍等も、参列員の中に特に列んでをった。庭狭きまでに満たされてゐた式場に、各国代表が机を隔てて我々と遠く向ひ合った後に、マッカーサー總司令官が出て来て、直ちに演説を始め、戦ひの終結したことを宣言し、降伏文書に署名を求めた。先づ、記者が署名を終り、次いで梅津大将も同様署名した。マッカーサー總司令官は、日本側の降伏を受け入れる意味で署名し、次いで各国代表が同様署名した。米国の代表者は、海軍のニミッツ提督で、英國代表はフレーザー提督であった。ソ連や支那の代表者も参加した。
珍らしい天氣で、ミズリー號甲板の上に立つとき、夏の名残りの富士山が東京灣上に聳えて見えた。開戦當初、シンガポール近海で撃沈された、プリンス・オブ・ウェールス號の姉妹艦ジョージ五世號も、銀色のスマートな巨体を浮べてゐた。
我々は、もとの経路で横濱埠頭に引き返して、東京に引き上げた上、政府に報告し、更に宮中に参内して、天皇陛下に復命して、重大任務を終了した。数千年の歴史はこれで一應閉ぢて、新日本の歴史がこれから始まることとなった。否、数千年の歴史が、これによって初めて継続して行き得ることとなった。いづれにしても、これから新日本が始まることは確かである。しかし、その新日本の建設は、なほ昭和日本革命でぁるのである。新日本の将来は、全く日本民族の能力と努力の如何に懸つてゐる。
人々は、「敗戦による勝利である」といふ意見を吐いた。日本がこれまでのやうでは、勝っても前途は駄目である。心を入れ換へて萬事新たに出直せば、繁榮もし生き甲斐もある。一旦苦悩の底を経てこそ、初めて立派になり得る、といふ意味である。記者はこれを否定することは出来なかったが、さらに国家の前途を深刻に考へて、悲痛の念を禁ずることが出来なかった。
このような人を本当の政治家(statesman)というのでしょう。最後の最後まで尻込みせず、与えられた任務をまっとうするというのは私心を超えた人でないかぎりなしえないことだと思います。そしてこのような高い志を持っていればこそ、次のように戦争の遠因を指摘したのです。
日本は第一次世界戦争では、日英同盟の誼によつて参戦し、日本軍はドイツの租借地たる支那山東省における膠州灣を攻略し、欧洲に関しては有力な駆逐艦隊を地中海に送り、印度洋の輸途路を防護したほか、その生産力を拳げて、連合国に対して経済的援助を行った。然し、この経済的援助は、同時に日本商権の海外拡張であり、日本貿易の膨張を意味した。自由貿易あるを知って未だ統制経済の意義を知らなかった日本は、その漸く発達したる軽工業が、世界の市場を荒すのをそのままに放任して、戦後到るところにおいて日本品排斥の種を蒔いたのであるが、とにかく戦争中の繁栄によって富をなしたのは、明治以来の政商として大をなした三井、三菱、住友等の財閥のみでなくして、東京・大阪・名古屋を中心とする大小商人が急に莫大の富を蓄積することが出来た。これがために、戦後においても日本には成金の氾濫時代が現出した。戦時獲得した利得の一半は、その後の世界的経済激変と、京濱地方の震災とによって失はれたが、多くの新奮大小財閥は、残存し且つ繁榮することを得て、新興資本家の傍若無人な横暴振りを発揮した。
かかる成金風潮が、穿きちがへた自由主義思想に便乗した結果、社会に興へた悪影響は、名状し灘きものとなった。国民的道徳は低下し、風俗は紊れ、自己主義は極端に流れ、物質主義は横行した。金権が直ちに政治を左右するやうになるのは當然である。
明治藩閥政治が、やうやくデモクラシーによる大正以後の政党政治に進化して、自由主義思想が顕著となっても、日本の社会機構は多く旧套を脱することが出来なかった。明治維新はあっても、封建制度は貴族の特権制度に温存せられて、政治生活においても日常生活においても、主張に依らず合理的に動かず、むしろ派閥的にまたは感情的に動くといふ風習は抜けなかった。第一次世界戦争は、デモクラシーの勝利に帰したために、世界は挙げてデモクラシーを謳歌し、日本においてはむしろデモクラシーの弊害のみが輸入せられ、時を得た政党政治は、時流を競ふ社会生活とともに無自覺無責任の方向に走った。国民の代表たるべき政党は、党利を計るに汲々として、國家の休戚を第二次的に見ることがしばしばであった。また進んでその政治資金を新旧財閥の間に仰いだのみならず、これをもって政治家の個人的勢力培養に利用した。経済界の繁榮も、順調な資本主義の発達によったものではなく、時の政権と結んだ閥族的成長によったものであった。国家国民の協力によって大をなした大小財閥は、政党と結託し、これを操縦して金催と化し、莫大なる富は、一般公共のために使用せらるること少く、多くはこれを私生活に濫費し、または政治的社会的野望の実現若しくは勢力の伸長のために使用された。國を挙げての拝金風潮は、遂に政治社会の隅々にまで波及し、貧富の差による思想問題は悪化し、農村は極度に疲弊し、富の濫用による弊害は、急テンポをもって頻出するに至った。日本の二大政党と称せられた政友、民政両党は、デモクラシー政治の指導的責任を果し得なかったのみならず、これら政党と金権との関係が、遂に政治頽廃の主たる原因と看倣さるるに至った。
かかる成金風潮が、穿きちがへた自由主義思想に便乗した結果、社会に興へた悪影響は、名状し灘きものとなった。国民的道徳は低下し、風俗は紊れ、自己主義は極端に流れ、物質主義は横行した。金権が直ちに政治を左右するやうになるのは當然である。
明治藩閥政治が、やうやくデモクラシーによる大正以後の政党政治に進化して、自由主義思想が顕著となっても、日本の社会機構は多く旧套を脱することが出来なかった。明治維新はあっても、封建制度は貴族の特権制度に温存せられて、政治生活においても日常生活においても、主張に依らず合理的に動かず、むしろ派閥的にまたは感情的に動くといふ風習は抜けなかった。第一次世界戦争は、デモクラシーの勝利に帰したために、世界は挙げてデモクラシーを謳歌し、日本においてはむしろデモクラシーの弊害のみが輸入せられ、時を得た政党政治は、時流を競ふ社会生活とともに無自覺無責任の方向に走った。国民の代表たるべき政党は、党利を計るに汲々として、國家の休戚を第二次的に見ることがしばしばであった。また進んでその政治資金を新旧財閥の間に仰いだのみならず、これをもって政治家の個人的勢力培養に利用した。経済界の繁榮も、順調な資本主義の発達によったものではなく、時の政権と結んだ閥族的成長によったものであった。国家国民の協力によって大をなした大小財閥は、政党と結託し、これを操縦して金催と化し、莫大なる富は、一般公共のために使用せらるること少く、多くはこれを私生活に濫費し、または政治的社会的野望の実現若しくは勢力の伸長のために使用された。國を挙げての拝金風潮は、遂に政治社会の隅々にまで波及し、貧富の差による思想問題は悪化し、農村は極度に疲弊し、富の濫用による弊害は、急テンポをもって頻出するに至った。日本の二大政党と称せられた政友、民政両党は、デモクラシー政治の指導的責任を果し得なかったのみならず、これら政党と金権との関係が、遂に政治頽廃の主たる原因と看倣さるるに至った。
この解説は少しも古くなく、現在の状況ときわめて多くの共通点を持っていることに驚かされます。結局、大戦前夜の日本は、今もそうであるように「拝金教徒」がはびこる浅ましい場所だったのです。そして重光さんは、日本の敗戦の原因を次のように簡潔に要約しています。
第一次世界大戦によつて、日本はアジアを代表して急に世界の五大国または三大国の一つに列することになり、西大手洋において厳然たる指導的地位につくこととなった。日本の世界平和に封する地位は大であり、人類文化に対する責任は極めて重かった。日本国家の将来の発展も、日本人自身の進歩も、明治以来の粒々辛苦の努力を忘れることなく、ただこの重大なる地位及び責任を充分に自覺し、常に自己反省を怠ることなく、努力を続けることによってのみ、なし遂げ得べきものであったのである。然るに、日本は、国家も国民も成金風の吹くに委せて、氣位のみ高くなって、内容実力はこれに件はなかった。日本の地位は躍進したが、日本は、個人も国家も、謙譲なる態度と努力とによってのみ大成するものである、といふ極めて見易き道理を忘却してしまった。これは、餘りにも、日本的でないのであるが、物質文明の滔々たる濁流に流されて、実際寸前の利益感情に捉はれ、個人及び国家の永遠の安寧や理想を顧みる良識を欠くに至ってゐた。これは昭和の動乱の原因でもあり、また動乱を通して見得る不幸なる現象であった。
重光さんはこの本の元となっている文章を巣鴨プリズンに収容されている間に書いたのですが、そのとき東條大将から次のような話を聞いています。
東條大将は、菓鴨で記者に封して、敗戦の原因を論じたことがあった。彼は、「根本は不統制が原因である。一国の運命を預るべき總理大臣が、軍の統帥に開興する権限のないやうな國柄で、戦争に勝つわけがない。その統帥がまた、陸軍と海軍とに判然と分れて、協力の困難な別々のものとなってゐた。自分がミッドウェーの敗戦を知らされたのは、一ヶ月以上後のことであって、その詳細に至っては遂に知らされなかった。かくの如くして、最後まで作戦上の完全な統一は実現されなかった」と述懐した。沈黙を巌守してゐた彼が、この最後的の述懐をしたのは、餘程のことであったと思はれる。東條大将は、最初に陸軍大臣であり、次いで首相兼陸相として、戦争を指導し、最後には参謀総長をも自ら兼ねて、政治と続帥とを続制せんとして、その権力を一身に集めた人である。死を前にした彼の言論は、少なからず価値のあるものと思はれた。
これではまさに今の官庁の「縦割り行政」と何ら変わりはないでしょう。また、別の箇所で、さらに次のように述べています。
日本の敗戦は、戦争に至る過去十餘年の政治的破碇の集積であることは、今更云ふまでもない。
国家としても、個人としても、獨善にして反省なきものは、自ら眠かくしをして、猛進するやうなものである。今日の国際生存競争場裡において、国家として生存を全うするには、大智なくしては不可能である。世界の形勢について、大局的判断を誤れる国の前途は、始めから定まってゐる。日本は、不幸にして大局上の判断を誤ったのみでなく、日本的焦躁感につきまとはれた。その結果は、始めから総てが玉砕型に陥ってしまった。政策的玉砕型は、作戦においても玉砕型となり、戦時日本人の心理にも、これが多分に作用した。玉砕は、感激を件ふけれども、堅忍と叡智とは、更に貴重である。
欧洲戦争が始まった後に、三國同盟を締結して渦中に入り、獨ソ戦争の結果が危ぶまれる際に、敢へて南進を決行し、欧洲戦争の大勢が定まって来た時に、世界最大の二強国を敵に廻して、世界戦争に突入するといふのは、何としても日本的の玉砕型であった。
その大戦争中にあって、作戦上内外における統帥上の不統一があったことは、物質力の測定を誤ったことと共に、敗戦の根本原因をなした。日本の指導が、政治上、経済上及び心理上、その他萬般のことにおいて、冷静なる科學的の検討に欠如してゐたことが、戦争によって遺憾なく暴露された。
国家としても、個人としても、獨善にして反省なきものは、自ら眠かくしをして、猛進するやうなものである。今日の国際生存競争場裡において、国家として生存を全うするには、大智なくしては不可能である。世界の形勢について、大局的判断を誤れる国の前途は、始めから定まってゐる。日本は、不幸にして大局上の判断を誤ったのみでなく、日本的焦躁感につきまとはれた。その結果は、始めから総てが玉砕型に陥ってしまった。政策的玉砕型は、作戦においても玉砕型となり、戦時日本人の心理にも、これが多分に作用した。玉砕は、感激を件ふけれども、堅忍と叡智とは、更に貴重である。
欧洲戦争が始まった後に、三國同盟を締結して渦中に入り、獨ソ戦争の結果が危ぶまれる際に、敢へて南進を決行し、欧洲戦争の大勢が定まって来た時に、世界最大の二強国を敵に廻して、世界戦争に突入するといふのは、何としても日本的の玉砕型であった。
その大戦争中にあって、作戦上内外における統帥上の不統一があったことは、物質力の測定を誤ったことと共に、敗戦の根本原因をなした。日本の指導が、政治上、経済上及び心理上、その他萬般のことにおいて、冷静なる科學的の検討に欠如してゐたことが、戦争によって遺憾なく暴露された。
物量面で劣勢だっただけでなく、情報戦でもはなはだしく貧弱であり、さらに精神的にも「鬼畜米英」にはなはだしく劣っていたのですから、玉砕することはわかりきっていたということでしょう。重光さんはこの記録を敗戦後に書いたわけですが、しかしその戦争観は戦時中も一貫して不動のものでした。
1941年7月2日に開催された御前会議で「対英米戦争を辞せず」、南仏印に進駐するという決定が下され、これが結局日本を破局へと至るべく運命づけたのです。この決定が永野軍司令總長から7月31日に天皇に伝えられると、「天皇は非常に驚かれて、米国との戦争なぞ考え得るか、と叱責的に反問せられた。永野總長は、対米戦争は1年半以上は不可能で、到底勝利の見込みのないことを申上げた。戦争は、日本上層部の欲したところではなかった。」そう重光さんは述べています。
当時対米交渉に全力をあげていた松岡外相が解任され、病気で臥せっていたときに重光さんが見舞いに行くと、元外相は次のように述べたそうです。「自分は米国と国交を調整することを終局の目的として奮闘したが、それは遂に不可能のことであった。南にも北にも、恐らく火がつくであらう、日本は、かやうにして一旦奈落の底に落ちて、然る後でなければ、国民的自覺の上に浮び上ることは出来ぬ、と思ふ。」蒼白な顔は氣力さへ喪失して見え、帰国したばかりで、この当時の国内の重要な動きをよく知らなかった重光さんは、前外相の「自暴自乗的な言葉は、狂氣の沙汰ではないか、とすら思った」と述べています。「如何なることがあっても、日本が大戦に突入して行くことを避けたばならぬ、と一途に考へた」からです。「しかし、今日よく顧みれば、松岡君の上記の言葉は、明らかに、七月二日の御前會議の決議に現はれた軍の動向を心配したものであったことは疑を容れぬ。手綱を振り切って、群衆の喚聲に驚きながら突進してゐる荒馬」が、当時の日本の姿だったのだと述べています。天皇も上層部も望んでいない方向に猪突猛進しようとしていたのです。
そこで重光さんは、宮中における御前講演や連絡會議の席上において、また近衛首相及び豊田外相に対しても、国際情勢の観察結果を意見とともに述べました。軍部の本拠である参謀本部にも行って、将校全員意向かって講演し、その他の會合でも、また重立った人々に対しても、大同小異の内容をもって所見を披露した。それが自分の義務と強く感じたからです。以下がそのその要旨でした。
1941年7月2日に開催された御前会議で「対英米戦争を辞せず」、南仏印に進駐するという決定が下され、これが結局日本を破局へと至るべく運命づけたのです。この決定が永野軍司令總長から7月31日に天皇に伝えられると、「天皇は非常に驚かれて、米国との戦争なぞ考え得るか、と叱責的に反問せられた。永野總長は、対米戦争は1年半以上は不可能で、到底勝利の見込みのないことを申上げた。戦争は、日本上層部の欲したところではなかった。」そう重光さんは述べています。
当時対米交渉に全力をあげていた松岡外相が解任され、病気で臥せっていたときに重光さんが見舞いに行くと、元外相は次のように述べたそうです。「自分は米国と国交を調整することを終局の目的として奮闘したが、それは遂に不可能のことであった。南にも北にも、恐らく火がつくであらう、日本は、かやうにして一旦奈落の底に落ちて、然る後でなければ、国民的自覺の上に浮び上ることは出来ぬ、と思ふ。」蒼白な顔は氣力さへ喪失して見え、帰国したばかりで、この当時の国内の重要な動きをよく知らなかった重光さんは、前外相の「自暴自乗的な言葉は、狂氣の沙汰ではないか、とすら思った」と述べています。「如何なることがあっても、日本が大戦に突入して行くことを避けたばならぬ、と一途に考へた」からです。「しかし、今日よく顧みれば、松岡君の上記の言葉は、明らかに、七月二日の御前會議の決議に現はれた軍の動向を心配したものであったことは疑を容れぬ。手綱を振り切って、群衆の喚聲に驚きながら突進してゐる荒馬」が、当時の日本の姿だったのだと述べています。天皇も上層部も望んでいない方向に猪突猛進しようとしていたのです。
そこで重光さんは、宮中における御前講演や連絡會議の席上において、また近衛首相及び豊田外相に対しても、国際情勢の観察結果を意見とともに述べました。軍部の本拠である参謀本部にも行って、将校全員意向かって講演し、その他の會合でも、また重立った人々に対しても、大同小異の内容をもって所見を披露した。それが自分の義務と強く感じたからです。以下がそのその要旨でした。
記者の駐屯してゐた英国の國情について、先づ述べた。「英国民の堅忍不抜の精神はすでに伝統的である。困難に遭へば遭ふ程決意は堅くなり、忍耐は強くなるのが英國人である。これを指導するチャーチルは、稀有の闘士であって、鐵血の決意をもって戦時の英国民を卒ゐてゐる。彼は英帝国の總力を動員し、興国と密接に連繋し、また米国を完全に味方に引き入れてゐる。海上における英国の優越は云ふに及ばず、空陸における勢力は、時間とともにドイツに接近しつつある。ドイツの海上封鎖は失敗しつつあるに反して、英国の大陸封鎖は益々効果を拳げつつある。
次いで、欧洲の戦勢に封する判断を述べた。「ドイツは、一九四〇年夏すでに対英上陸作戦を断念せざるを得なかったが、陸上においてはなほ長く優位を維持する。しかし、これは欧大陸に関することであって、植民地においては英国の経験ある軍隊が優ってゐる。英国の海上の優越は動かぬ。当ソ戦は、ドイツ側の云ふが如く数ヶ月で片付けることは不可能であって、恰かも我が支那戦争の如く、ドイッの武力を際限なく消耗する戦争と化することは必至である。戦争は短期に非ずして長期にわたる。英國の準備が完成し、豫見せられる米国の公然たる参戦が實現する時は、前回大職の場合と同じく、ドイツの運命の定まる時である。」
更に、国際関係については、「英國と亡命興國との園結は益々鞏固となり、佛国もド・ゴール中心に集結しつつあり、彼等の終局の勝利に封する信念は動かぬ。米国の動向は戦争に対する決定點であるが、ルーズヴェルトの指導の下に、事實上すでに参戦してゐると同様である。米国は、今日南北米における軍事上の基地を固め、英本國を國防の前哨と称してゐる。英米の国防はすで合體してをり、米国の形式上の参戦は単に時と機會の問題である。英国はすでに植民地戦において自信を示してゐる。加ふるに、ドイツの占領地における困難は、時とともに累加するは必至である。従って、ドイツに対する英、ソ及び米の包圍戦が終局の勝利を得ることは、大勢上動かすべからざるところで、戦争はすでに峠を越えてゐる」との観測を述べた。この戦争に対する一般観察は、駐英陸軍武官辰巳少将も同意見で、彼はその意見書を中央軍當局に記者を通じて提出した。
記者は結論として、「日本は欧洲戦争に介入してはならぬ。日本は絶対に戦争不介入方針を堅持し、現に着手してゐる日米交渉を成功せしめ、且つ進んで、支那問題を解決して、日支関係を清算するやうにせねばならぬ。日本が戦争に介入せず、外交によってその困難を解決する方針に出づれば、日本の地位は欧洲戦後必ずおのづから向上する」と云ふのであった。
長く海外に勤務し、日本政府の方針や国内事情について、何等通報を受けてをらぬ記者は、軍部の方向や御前會議の決定等は、素より知る由もなかったが、みすみす負ける戦争に加入するほど日本人は愚ではない、とひたすら考へた。
宮中の御進講では、ロンドン離任の際のチャーチル首相との會談によって表された英国の決意から、英國皇室の動静、ダンカークの時の英国の有様、空襲下の英国民の沈着なる態度、についても詳述した。
天皇陛下は、後に皇后陛下に対しても同様御進講をなすべきことを記者に命ぜられた。参謀本部における記者の講演は、数百名の将校以上の聴衆に対してなされたもので、戦争の大勢に重きを置き、英国の不敗と長期戦による勝利を解説して、心ある将校には少からず感銘を興へたが、爾来記者は英米派として悪宣伝をされ、憲兵の尾行も付くやうになった。軍には、なほドイツの勝利が常識であったのである。興論は素より狂信的に枢軸謳歌が圧倒的であった。
近衛公も豐田外相も、記者の説明には共鳴したものの如くに感ぜられた。特に日米交渉に対しては熱意を示し、近衛公の如きは、死をもって、これが成立に努力して、陛下の御意思に副ふ、との決意を表明した。記者の當時接触した多数の識者の中には、記者を激働するものも少くはなかった。記者は、近衛公の日米交渉に対しては、自分のなし得る限りの援助を興へた。しかし、国内の事情は既に容易なものではなかった。
次いで、欧洲の戦勢に封する判断を述べた。「ドイツは、一九四〇年夏すでに対英上陸作戦を断念せざるを得なかったが、陸上においてはなほ長く優位を維持する。しかし、これは欧大陸に関することであって、植民地においては英国の経験ある軍隊が優ってゐる。英国の海上の優越は動かぬ。当ソ戦は、ドイツ側の云ふが如く数ヶ月で片付けることは不可能であって、恰かも我が支那戦争の如く、ドイッの武力を際限なく消耗する戦争と化することは必至である。戦争は短期に非ずして長期にわたる。英國の準備が完成し、豫見せられる米国の公然たる参戦が實現する時は、前回大職の場合と同じく、ドイツの運命の定まる時である。」
更に、国際関係については、「英國と亡命興國との園結は益々鞏固となり、佛国もド・ゴール中心に集結しつつあり、彼等の終局の勝利に封する信念は動かぬ。米国の動向は戦争に対する決定點であるが、ルーズヴェルトの指導の下に、事實上すでに参戦してゐると同様である。米国は、今日南北米における軍事上の基地を固め、英本國を國防の前哨と称してゐる。英米の国防はすで合體してをり、米国の形式上の参戦は単に時と機會の問題である。英国はすでに植民地戦において自信を示してゐる。加ふるに、ドイツの占領地における困難は、時とともに累加するは必至である。従って、ドイツに対する英、ソ及び米の包圍戦が終局の勝利を得ることは、大勢上動かすべからざるところで、戦争はすでに峠を越えてゐる」との観測を述べた。この戦争に対する一般観察は、駐英陸軍武官辰巳少将も同意見で、彼はその意見書を中央軍當局に記者を通じて提出した。
記者は結論として、「日本は欧洲戦争に介入してはならぬ。日本は絶対に戦争不介入方針を堅持し、現に着手してゐる日米交渉を成功せしめ、且つ進んで、支那問題を解決して、日支関係を清算するやうにせねばならぬ。日本が戦争に介入せず、外交によってその困難を解決する方針に出づれば、日本の地位は欧洲戦後必ずおのづから向上する」と云ふのであった。
長く海外に勤務し、日本政府の方針や国内事情について、何等通報を受けてをらぬ記者は、軍部の方向や御前會議の決定等は、素より知る由もなかったが、みすみす負ける戦争に加入するほど日本人は愚ではない、とひたすら考へた。
宮中の御進講では、ロンドン離任の際のチャーチル首相との會談によって表された英国の決意から、英國皇室の動静、ダンカークの時の英国の有様、空襲下の英国民の沈着なる態度、についても詳述した。
天皇陛下は、後に皇后陛下に対しても同様御進講をなすべきことを記者に命ぜられた。参謀本部における記者の講演は、数百名の将校以上の聴衆に対してなされたもので、戦争の大勢に重きを置き、英国の不敗と長期戦による勝利を解説して、心ある将校には少からず感銘を興へたが、爾来記者は英米派として悪宣伝をされ、憲兵の尾行も付くやうになった。軍には、なほドイツの勝利が常識であったのである。興論は素より狂信的に枢軸謳歌が圧倒的であった。
近衛公も豐田外相も、記者の説明には共鳴したものの如くに感ぜられた。特に日米交渉に対しては熱意を示し、近衛公の如きは、死をもって、これが成立に努力して、陛下の御意思に副ふ、との決意を表明した。記者の當時接触した多数の識者の中には、記者を激働するものも少くはなかった。記者は、近衛公の日米交渉に対しては、自分のなし得る限りの援助を興へた。しかし、国内の事情は既に容易なものではなかった。
これだけ誠心誠意に国際情勢を正確に伝えたのですから、多くの賛同者が出て当然ですが、しかし情勢は正しい方向に転じませんでした。松岡外相を排斥した第三次近衛内閣によって、「決死の覺悟をもって」成立させるべく日米交渉が続けられることになったにもかかわらず、前内閣時代、7月2日の御前会議で決定された仏印への進駐は、取り消されることなく、第三次近衛内閣によつて、躊躇なく実行に移されたのです。これは「何たる矛盾であらう」と重光さんはあきれています。
日本軍はサイゴンを占拠し、海軍は日露戦争當時、露国、バルチック艦隊の停泊したカムラン灣を占領し、附近に大飛行場を建設するという計画が7月21日から実行に移されたのです。
日本軍はサイゴンを占拠し、海軍は日露戦争當時、露国、バルチック艦隊の停泊したカムラン灣を占領し、附近に大飛行場を建設するという計画が7月21日から実行に移されたのです。
南佛印占領の軍事上の意義は極めて明瞭である。カムラン海は、海を隔ててマニラとシンガポールとに対し、陸はシャムに績いてゐる。英米の東亜における根拠地は、すでに日本軍の一撃の距離の内に収められた。英米蘭は、日本の意図を明瞭に汲み取り、日米交渉は、殆んど中絶の有様となった。米国は、直ちに日本に封して凍結令を實施し、日本商社に対して、米国における資金を凍結し(一九四一年七月二十六日)、日本との通商を全面的に停止し、本格的経済戦争に移行してしまった。米国の対日経済戦争はかくして白熱し、英国もオラングもまた同様な措置に出た。日本が、八千萬の人口を養ふために必要とする海外貿易は、日本軍隊の占領区域以外は、洋の東西を問はず、悉く失ふこととなったわけである。米国は、経済的には,全く日本活殺の権を握ることとなった。これより後の日米交渉の中心點は、本筋を離れ、寧ろ日米経済交通を復活し、日本が米国より油を輸入するためには、日本は如何なる譲歩をしたければならぬか、と云ふことに帰着するにいたった。
日本軍部は何か物に憑かれたやうに、ドイツの全勝を盲信し、なほもドイツ勝利の暁に、日本の戦争参加によって取り得べき莫大なる分け前についてのみ、頭を悩ましてゐた。
日本軍部は何か物に憑かれたやうに、ドイツの全勝を盲信し、なほもドイツ勝利の暁に、日本の戦争参加によって取り得べき莫大なる分け前についてのみ、頭を悩ましてゐた。
自分たちが奈落の底に向かい始めたというのに、戦勝後の分け前について妄想をたくましくしていた──まさに捕らぬ狸の皮算用をしていた──のです。ドイツも日本に対して、自国の軍勢の大きさについてかなりの誇大宣伝をしていたようなので、日本の軍部は欲に駆られてその宣伝を盲信してしまったのです。何という「欲ぼけ」でしょう!
これと対極を成しているのがチャーチル治下の英国です。重光さんは「史上の一偉観」として、チャーチル新総理が1940年6月18日に行なった第1回戦況報告演説の模様を次のように感動をもって記しています。
これと対極を成しているのがチャーチル治下の英国です。重光さんは「史上の一偉観」として、チャーチル新総理が1940年6月18日に行なった第1回戦況報告演説の模様を次のように感動をもって記しています。
チャーチル新總理の第一回の戦況報告演説が始った。議場は緊張と静粛とをもって、一語も聞き洩らすまいとする。
チャーチルは、淡々として、北佛における敗戦を少しの虚飾もなく正當に評債して、その経緯を詳細に叙述し、ドイツ軍の見事な戦術とその大成功とを説き、聯合軍は健闘に拘らず惨敗し、英軍はつひに海岸に退却を餘儀なくせられたことを述べ、ダンカークの悲壮にして勇敢なる軍隊の救出状況を叙し、英雄的に闘った佛國軍も、つひに力尽きたることを明らかにし、言々句々、現實に即した冷静平明にして、男性的なるその叙述は、聴くものの肺腑を抉るが如きものがあった。
彼は続けた。佛國脱落せば、英國は単獨にてこの強敵と死闘せねばならぬ。敵は対岸に立ってゐる。何時侵入して来るかも知れぬ。今日は、英國歴史始って以来の最大危機である。自分は、陸海空三軍の首脳部に専門家の意見を徴した。彼等は未だ勝利可能の見込みを捨てぬ。英国人の戦意が、ドイツの享有してゐる量的及び物的の優越を乗り越え得ることを信ずると云ふのである。英国人は、獨裁専制の敵に屈するよりも、最後の一人まで戦ふ決意を有ってゐる。かやうにして、英国がつひに最終の勝利に到達することを今日なほ確信するものである。
「今や英国の戦ひ(Battle of Britain)が展開せられんとしつつある。人類文明の安危は、この戦に懸ってゐる。四自治領は、我々の戦争継続を全面的に支持してゐる。勝利か、死か、我々はその一つを選ばんとしてゐる。若し、英帝國が千年の久しきに互って続くものならば、これぞ彼等の最も光輝ある時(their finest hour)であったと、後世の人をして讃美せしめようではないか」と述べ終って、熱涙の下るまま頭を抱へて自席に着席したその光景は、これを見たものの忘れることの出来ぬ光景であった。
議會の表示した決意は、英国民一人一人の決意であった。この国家存亡の危機に際して、国民的決意の表示せられた瞬間は、真に光輝ある一と時であった。英国民はまた元の冷静に還って、日々の仕事を急いだ。政府も工場も家庭も日夜働きを績けた。
記者は本国政府に当して、この歴史的議會を参観した後「史上の偉観」であつたと報告した。
チャーチルは、淡々として、北佛における敗戦を少しの虚飾もなく正當に評債して、その経緯を詳細に叙述し、ドイツ軍の見事な戦術とその大成功とを説き、聯合軍は健闘に拘らず惨敗し、英軍はつひに海岸に退却を餘儀なくせられたことを述べ、ダンカークの悲壮にして勇敢なる軍隊の救出状況を叙し、英雄的に闘った佛國軍も、つひに力尽きたることを明らかにし、言々句々、現實に即した冷静平明にして、男性的なるその叙述は、聴くものの肺腑を抉るが如きものがあった。
彼は続けた。佛國脱落せば、英國は単獨にてこの強敵と死闘せねばならぬ。敵は対岸に立ってゐる。何時侵入して来るかも知れぬ。今日は、英國歴史始って以来の最大危機である。自分は、陸海空三軍の首脳部に専門家の意見を徴した。彼等は未だ勝利可能の見込みを捨てぬ。英国人の戦意が、ドイツの享有してゐる量的及び物的の優越を乗り越え得ることを信ずると云ふのである。英国人は、獨裁専制の敵に屈するよりも、最後の一人まで戦ふ決意を有ってゐる。かやうにして、英国がつひに最終の勝利に到達することを今日なほ確信するものである。
「今や英国の戦ひ(Battle of Britain)が展開せられんとしつつある。人類文明の安危は、この戦に懸ってゐる。四自治領は、我々の戦争継続を全面的に支持してゐる。勝利か、死か、我々はその一つを選ばんとしてゐる。若し、英帝國が千年の久しきに互って続くものならば、これぞ彼等の最も光輝ある時(their finest hour)であったと、後世の人をして讃美せしめようではないか」と述べ終って、熱涙の下るまま頭を抱へて自席に着席したその光景は、これを見たものの忘れることの出来ぬ光景であった。
(中略)
議場の中央に立って演説を終えたチャーチルが、一、二歩後方の自席に引き下がった瞬間に、議場は沸き返った。隣の席にゐたチェムバレンは、立ち上って熱烈に拍手しハンケチを振った。議場は總立ちになって、議事日程やハンケチを振り、足摺りをして熱狂した。傍聴席も沸いた。この光景は、宣戦布告をした一年前の議會の冷静にして事務的なりしに比して、何と甚だしく異なったものであることよ。英国人は、時としてかくも血を沸かすことがあるのである。議會の表示した決意は、英国民一人一人の決意であった。この国家存亡の危機に際して、国民的決意の表示せられた瞬間は、真に光輝ある一と時であった。英国民はまた元の冷静に還って、日々の仕事を急いだ。政府も工場も家庭も日夜働きを績けた。
記者は本国政府に当して、この歴史的議會を参観した後「史上の偉観」であつたと報告した。
これこそはまさに未曾有の危機に直面しての「挙国一致」だと言いうるでしょう。これに対して日本軍部は本当のことを国民に伝えず、誇大な報告をし続け、結果的に国民に前例のない犠牲を強いることになったのです。これではとうてい挙国一致とは言えません。
☆
新年早々このような長々とした紹介をさせていただいたのは、重光さんの回想録に書かれていることが今の政治経済状況を見る上できわめて参考になると思ったからです。それを示すため、重光さんが誰も嫌がった降伏文書への署名役を、日本の再生への願いを込めて任じ終わった直後の様子についての、「人心の軽浮」と題された記述を最後にご紹介します。
天皇陛下の終戦に開する御思召は、皇族内閣の威令によって能く行はれ、且つ國民一般は、理解をもってあらゆる協力をなした。議會も新聞記者も皇族内閣には寛大の態度を示した。それがためには、終戦事業には當初支障がなかった。しかし、一旦終戦となると、忽ちにして政治家も實業家も、恰かも日本は戦前平時の状態に復帰したもののやうに考へ、終には、国際関係は舊に復し、通商すら直ちに自由に開けるものと軽信するものが少くなく、戦争は恰かも日清日露の舊時の戦争の如く処理せられることを豫期し、全体的戦争の結果の如何なるものであるかを理解するものが少かったのみならず、ポツダム宣言の實行については、日本国民の食糧問題に理解を有するとか、工業生産の原料供給に同情を有するとかの、耳ざはりの好き部分のみに重きを置き、全体的に日本の運命が敵の手中に陥ったといふ冷厳なる敗戦の事實を認識し、責任を感ずるものが少かった。
それのみではない、戦時中軍部に追随しその希望に先き走りしてゐたものが、掌を翻すが如く軍部の敵となり、占領軍の謳歌者となったりした。従来対外強硬論を唱へて、軟弱外交を悪罵していた人々の多くのものは、いづれも急に穏健派を自称し、平和主義者となり、剰へ自分の立場を擁護するため、他を害することを何とも思はぬやうなあさましい状況であった。この滔々たる事大主義(自分の信念をもたず、支配的な勢力や風潮に迎合して自己保身を図ろうとする態度・考え方──編者註)的傾向は、敗戦の止むを得ざる結果ではあるが、識者をして甚だしく顰蹙せしむる(不快を感じて、眉をひそめさせる──編者註)ものがあった。軍閥に対しても、占領軍に対しても、追随するところなく、一様に公正なる態度をもって臨む中庸を得たる人々は、却って漸次、姿を匿した。
占領軍司令部の態度が、国民生活を主とする事業の経営は、平時と同様続行して差支へなし、といふことが明らかになるや、多くの實業家は、今にも米国その他との取引も戦前の通りに行はれるものの如く感じて、これに関して自ら交渉を申出でたり、敗戦国として、身分不相應にして無自覺な要望を當局になすものが、引きもきらぬ状況となり、これが政府にも反映して、政府部内においてすら、安易な考へ方をなすものが少くなかった。占領軍司令部は、日本側より申出で交渉すれば、何でも受け入れる、とまで誤認するものすらあった。
それのみではない、戦時中軍部に追随しその希望に先き走りしてゐたものが、掌を翻すが如く軍部の敵となり、占領軍の謳歌者となったりした。従来対外強硬論を唱へて、軟弱外交を悪罵していた人々の多くのものは、いづれも急に穏健派を自称し、平和主義者となり、剰へ自分の立場を擁護するため、他を害することを何とも思はぬやうなあさましい状況であった。この滔々たる事大主義(自分の信念をもたず、支配的な勢力や風潮に迎合して自己保身を図ろうとする態度・考え方──編者註)的傾向は、敗戦の止むを得ざる結果ではあるが、識者をして甚だしく顰蹙せしむる(不快を感じて、眉をひそめさせる──編者註)ものがあった。軍閥に対しても、占領軍に対しても、追随するところなく、一様に公正なる態度をもって臨む中庸を得たる人々は、却って漸次、姿を匿した。
占領軍司令部の態度が、国民生活を主とする事業の経営は、平時と同様続行して差支へなし、といふことが明らかになるや、多くの實業家は、今にも米国その他との取引も戦前の通りに行はれるものの如く感じて、これに関して自ら交渉を申出でたり、敗戦国として、身分不相應にして無自覺な要望を當局になすものが、引きもきらぬ状況となり、これが政府にも反映して、政府部内においてすら、安易な考へ方をなすものが少くなかった。占領軍司令部は、日本側より申出で交渉すれば、何でも受け入れる、とまで誤認するものすらあった。
そのため重光さんは、新聞記者會見談において、日本の復興し得る唯一の途は、敗戦を自覺し反省することにある、と繰り返し述べなければなりませんでした。そして、なぜあえて「降伏」という文字を使ったかについて、次のように述べています。
降伏といふ文字を使用することは、日本人の氣持として非常に心苦しかった。軍人出身の閣僚は、譯文だけでも休戦の文字を使用し度いと圭張したが、surrenderといふ原語は何といっても降伏といふことであり、また敗戦の結果、實際降伏することになったのであって、その事實はこれを十分に承認し、徹底的に意識しなければ、日本の再生は出来ない、偽装的一方的の考へ方は、これからは総てよさねばならぬ、といふ外務省の強い考へ方を押し通した。
外務省において、マッカーサー司令部との連絡を司るために、終戦連絡事務局といふ一小部局を新設することの提案に対しては、内閣内において非常に大きな反対に遭遇した。反対意見は、總司令部との連絡は事重大であるから、その機関は内閣内に首相直轄の大組織を要する、といふのである。記者は、終戦事務は敗戦後殆んど國務の全部を支配するもので、内閣全體の仕事であって、内閣各省自體がそのままこれに當るべきものである。これがために新たに大きな組織を造るの要はない、ただ問題は、外務省の任務とする占領軍との連絡のための設備を要する、事務的に外務省を通じてやる、といふことは日本政府が獨立性を持続した立場をとるものであって、この建前だけは、これを維持することが必要である、但し各省が、その任務の範囲内において、直接司令部と接触することは拘束すべきでないが、連絡事務の不統整は必ず重大な不利益をもたらすに至る、といふ趣旨を主張したのであった。
大規模の終戦機関を造って、これに民間大物を割り込ませようと云ふのが、また利害本位實業方面の主張であった。民間の意見を聞く機関は、必要に應じて、外務省にでも内閣にでもこれを設置することに記者は何等の異存はなく、またこれを企図してゐた。しかし、日本の獨立主権は、たとへ制限されても、飽くまでこれを維持してゐる建前をとりたかった。これがためには、やはり一国の玄関である外務省の管轄の下に、連絡事務を取り扱ふことが、軍政に反対したと同趣旨によって、必要であった。當時の空気でこれを諒解してくれる人は殆んどなく、閣内の多くの人々は、これを平時の仕事の奪ひ合ひのやうに考へた。近衛副總理は、これを政界賞業界の有力者を利用する操縦機関のやうに取扱った。
政府内部の空気は、敗戦後の降伏文書の實施といふ冷厳なる現實とは非常に遠きものがあった。折角ポツダム宣言の忠實なる實施を方針として成立した内閣は、降伏の實現とその文書の調印といふ第一段第二段の使命を順當に果して後は、全く普通の時の内閣の仕事をやって行くやうな氣安な空気に自然に還元されて、昨日まで戦ってゐた敵軍の占領下に日本が置かれてゐる現實とは、離れた観を呈して来た。
外務省において、マッカーサー司令部との連絡を司るために、終戦連絡事務局といふ一小部局を新設することの提案に対しては、内閣内において非常に大きな反対に遭遇した。反対意見は、總司令部との連絡は事重大であるから、その機関は内閣内に首相直轄の大組織を要する、といふのである。記者は、終戦事務は敗戦後殆んど國務の全部を支配するもので、内閣全體の仕事であって、内閣各省自體がそのままこれに當るべきものである。これがために新たに大きな組織を造るの要はない、ただ問題は、外務省の任務とする占領軍との連絡のための設備を要する、事務的に外務省を通じてやる、といふことは日本政府が獨立性を持続した立場をとるものであって、この建前だけは、これを維持することが必要である、但し各省が、その任務の範囲内において、直接司令部と接触することは拘束すべきでないが、連絡事務の不統整は必ず重大な不利益をもたらすに至る、といふ趣旨を主張したのであった。
大規模の終戦機関を造って、これに民間大物を割り込ませようと云ふのが、また利害本位實業方面の主張であった。民間の意見を聞く機関は、必要に應じて、外務省にでも内閣にでもこれを設置することに記者は何等の異存はなく、またこれを企図してゐた。しかし、日本の獨立主権は、たとへ制限されても、飽くまでこれを維持してゐる建前をとりたかった。これがためには、やはり一国の玄関である外務省の管轄の下に、連絡事務を取り扱ふことが、軍政に反対したと同趣旨によって、必要であった。當時の空気でこれを諒解してくれる人は殆んどなく、閣内の多くの人々は、これを平時の仕事の奪ひ合ひのやうに考へた。近衛副總理は、これを政界賞業界の有力者を利用する操縦機関のやうに取扱った。
政府内部の空気は、敗戦後の降伏文書の實施といふ冷厳なる現實とは非常に遠きものがあった。折角ポツダム宣言の忠實なる實施を方針として成立した内閣は、降伏の實現とその文書の調印といふ第一段第二段の使命を順當に果して後は、全く普通の時の内閣の仕事をやって行くやうな氣安な空気に自然に還元されて、昨日まで戦ってゐた敵軍の占領下に日本が置かれてゐる現實とは、離れた観を呈して来た。
要するに、軍部やそれを支持した財閥や富農たちは、戦争によって大儲けをたくらんでいただけなのであり、「聖戦」でも何でもなかったことが改めて明らかになったのです。このような支配者たちのために尊い生命を犠牲にした純真な若者たちが多数いたわけですが、これほど気の毒なことはありません。重光さんがこの本を書いたのは日本人に「深い反省」を促すことが主なねらいだったのですが、それはほとんど無視されたのです。この軽薄な精神が、今日までずっと居座り続けているのです。
そして「軍閥に対しても、占領軍に対しても、追随するところなく、一様に公正なる態度をもって臨む中庸を得たる人々は、却って漸次、姿を匿した」のです。
政治が右傾化しつつあると言われ、過去に逆戻りしているのではないかとさえ思われる今、この国の過去を振り返ってみることが大事なのではないかと思い、新年のご挨拶ついでに『昭和の動乱』を紹介させていただきました。この本は「事実尊重」の姿勢に貫かれており、勝手な「思い込み」など微塵もありません。もちろんいろいろな意見があるでしょうが、少なくとも編者にはそう思われました。そしてその意味で、きわめて貴重な資料であり、これを残してくれた重光さんに心から敬意を表したいと思います。
そして「軍閥に対しても、占領軍に対しても、追随するところなく、一様に公正なる態度をもって臨む中庸を得たる人々は、却って漸次、姿を匿した」のです。
政治が右傾化しつつあると言われ、過去に逆戻りしているのではないかとさえ思われる今、この国の過去を振り返ってみることが大事なのではないかと思い、新年のご挨拶ついでに『昭和の動乱』を紹介させていただきました。この本は「事実尊重」の姿勢に貫かれており、勝手な「思い込み」など微塵もありません。もちろんいろいろな意見があるでしょうが、少なくとも編者にはそう思われました。そしてその意味で、きわめて貴重な資料であり、これを残してくれた重光さんに心から敬意を表したいと思います。