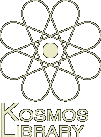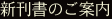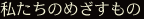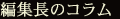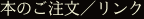[新装・新訳版]『キッチン日記― J・クリシュナムルティとの1001回のランチ ―』
マイケル・クローネン[著]/大野純一[訳]
定価(本体2,500円+税)
ISBN978-4-434-22117-0 C0011
![[新装・新訳版]キッチン日記― J・クリシュナムルティとの1001回のランチ ―](../ic/image/163b.jpg)
キッチンで料理を提供し、D・ボームなどの会食者たちと歓談するかたわらで綴られた、精緻にして長大なクリシュナムルティ随聞記
インドでは、古来食べ物はブラフマン(意識)だと言われてきた。『キッチン日記』は、当代の最も偉大な賢者の一人の意識の中で揺れ動いている気分ならびに精神の微妙な陰影への洞察をあなたに与えてくれる。
一連のランチメニューに順次目を通しながら本文を読み進めていくうちに、あなたは、多くの人々に影響を与えてきたこの偉大な存在のパーソナリティの中にある複雑さ、単純さ、そしてユーモアを体験するであろう。
──ディーパック・チョプラ(『富と成功をもたらす7つの法則』の著者)
マイケル・クローネンの『キッチン日記』は、クリシュナムルティと彼の客たちにシェフとして菜食料理を提供した著者による、一九七五年から一九八六年までの出来事の優れた記録である。この伝記的ポートレートは、クリシュナムルティを聖人扱いしようとする様々な企てへのタイムリーな矯味薬である。ランチ中の打ち解けた会話からの記述と引用は、読んで楽しいだけでなく、真剣に考察するに値する。クリシュナムルティの教えのエッセンスの多くが、本書全体にちりばめられている。
メニューが添えられている菜食料理を想像しながら、会食者たちと共に間接的に味わう人は誰であれ、それに満喫させられるだけでなく、スピリチュアルな滋養も与えられることだろう。
──アラン・W・アンダーソン(サンディエゴ大学宗教学部名誉教授)
クリシュナムルティの最も深い理解者の一人による、手作りの菜食料理と
ジョークによって趣を添えられた、機智に富んだ回顧録。
【本書の内容】
第一章 秘教および本書の概要
秘教とは何か/各章の概略
第1部 道なき土地への導き
第1 章 最初の数歩 ■ 第2 章 友情の始まり ■ 第3 章 充分な味わい
第4 章 縁は二度訪れて
第2部 クリシュナムルティとのランチ
第5 章 月の谷間で ■ 第6 章 クリシュナジとの集会
第7 章 クリシュナジを待ち受ける ■ 第8 章 クリシュナジとのランチ
第9 章 「何かニュースはありますか?」 ■ 第10 章 恵みの水
第11 章 宗教的精神の持ち主 ■ 第12 章 不死の友
第3部 完成の年月
第13 章 様々な精神の出会い ■ 第14 章 思考の糧
第15 章 人生のミステリーへの鍵? ■ 第16 章 空(くう)のエネルギー
第17 章 すべてのエネルギーの結集 ■ 第18 章 対話の極致 ■ 第19 章 創造性
第20 章 鷲の飛翔
第4部 善性の開花
第21 章 地上の平和 ■ 第22 章 内的なものの科学者 ■ 第23 章 長いお別れ
第24 章 最後の日々
以下は、高橋重敏氏の訳で1999年に出版された『キッチン日記』の「訳者あとがき」です。
訳者あとがき
その日、私はオハイ バレーインに宿泊していた。クリシュナムルティ財団のあるオーク グローブのすぐ近くにあり、ゴルフコースも備えたこの著名なホテルではかつてクリシュナムルティもクラブを振ってゴルフを楽しんだことがあると言う。彼は若い頃英国でプロについて正式にゴルフを習っていて、直ぐに上手になり一時はハンデイ2にまでなったという。この事実は彼の伝記作者のメアリー・ルーチェンスから直接聞いた話であり、彼女はクリシュナムルティがオハイ バレーインのコースに立って実際に自球を打ったときも、彼の側で見ていたと言ってくれた。
「それでどんな球を打ったのですか」と私が無遠慮に聞くと、彼女は悪戯っぼく私を見つめて「彼が変な球を打つはずがないでしょ。そりゃ真っ直ぐに遠くまで飛んだ見事なティショットだったのよ」と笑って語っていた。そんな故事があったので、私も一度はこのコースでプレーしてみたいと思っていた。たまたまオハイを訪れてこのホテルに部屋を取ったのもこういう下心があったからである。
翌朝、突然部屋に電話がかかってきた。何気なく受話器をとると元気な男性の声である。
「マイケル クローネンです。あなたがこのホテルにお泊まりと聞いて、お電話しました。実はあなたに頼み事があるのです」
「何でしょう」と私は訝りながら尋ねた。そして頭の中ではクローネンという名と私の知っているその人物の映像を一致させようと神経を働かせていた。彼の名を思い出すのに苦労はなかった。今までも英国やインドで数回会っていたからである。殊に英国のブロックウッドでは彼を交えた数名のグループで生前のクリシュナムルティが最も好んだという彼の散策コースを二時間近くかけて丹念に辿ったことがあり、その途中いろいろ親切に当時のことを説明してくれたのがクローネンだった。口ひげを生やした大柄な中年のドイツ人である。
「実は今度本を書いたのです。キッチン クロニクル(キッチン日記)というのですが、別題を『J.クリシュナムルティとの1001回のランチ』としました。主として彼のランチの際の会食客に対する様々な彼の話が中心なのですが、何とかこの本を日本語に翻訳して日本で出版出来るように手配して頂けないでしょうか」
「その本は何処で手に入れられますか?」
「財団のマーク・リーさんに連絡してみて下さい。ところであなたは何日までそこに逗留しているのですか。私は今日はロスアンジェルスに用がぁるので一日中いないのですが、明日お時間があったら是非お目にかかっていろいろお話したいのです」
生憎と私はその日夕方にはオハイを引き上げる予定だったのでその旨を伝え、電話での会話は打ち切りになった。
私はその日の午後、時間をつくって財団の事務所を訪れ、クローネンに依頼された彼の著書を手渡された。ズシリと重量感のあるその本は三百頁を越していた。これは大仕事だというのが私の直感だった。翻訳したらゆうに四百頁は越すだろう。そういう厚手の本を、しかも全く無名の著者の本の出版を引き受けてくれる出版社など不況に悩む日本国内にあるだろうか。少しばかリペッシミスティックな気持ちになって帰国した私だったが、肝心の本はそのまま本棚にしまい込んだままだつた。
そんな私の尻を叩くようにクローネンからは私のオフイス宛に長いファックスが送られてきた翻訳と出版を引き受けて貰えると信じ込んでいる彼の喜びが紙面におどっているような文面だった。その情熱は私の重い腰を持ち上げずにはおかなかった。雑務に追われながら、私は意を決して彼の本を読み始めた。
ところがである。この「キッチン クロニクル」は予想に反して大変興味深かった。文字を追っていた私の眉の皺はいつの間にか伸びきっていて、心はすっかり中身の面白さにのめり込んでいた。
正直に言うとクリシュナムルティの本はどれもこれもが例外なく難解だという定評がある。彼が自分で書いたもの、講話の内容をまとめたもの、など今まで刊行されたものは百冊をゆうに越す、その全てが英語で発表されたものであり、使用された英語のボキャブラリー(用語範囲)には難しい専門語など一切含まれていない。文体も正確だし、論旨の進め方も極めて理詰めである。それでいて容易に読解出来ないのだ。文字の意味は理解しても文章の解読に頭がついていかないのである。
これが翻訳本となると翻訳そのものの巧拙度が加算されるので晦渋度は更に原書を上回ることになる。恐らく、理解、知識、欲望、自由、条件づけ、関係、気付き、選択、観察、洞察、二重性、意識、心、頭脳、自我、などという言葉に彼独得の解釈が附加されていること、なども難解の原因になっていると言える。そしてまた、神、聖者、グル、生、死、宗教、真理、瞑想、神、愛などに対する彼の考え方も今まで他の誰からも聞いたことのない解釈がふんだんに盛り込まれているのである。
しかし、腰を下ろして落ち着いて読めば、決して理解し難いこともないし、その独得の解釈にこそ、他のどんな学者や聖者からも学べなかった比類のない新鮮さが溢れているのを発見できるのだが、そこまで忍耐強い読者が中々にいないのもまた当たり前のことかも知れない。したがって、彼の教えが難解だという定評があるのもうなずけるというものだ。
こういう教義を述べるクリシュナムルティという人物が、重厚で生真面日だけの聖者ぶった堅物でないことは、彼のビデオを見ていて、時々洩らす無心な笑顔にもよく現れているのだが、「キッチン クロニクル」は正に彼のジョークに富んだ明るい一面をあますところなく伝えてくれるのに大きな役割を果たしているのだ。
クローネンは高校を卒業後すぐアメリカに移住したが、若い頃からいろいろな宗教に関心を持っていた。たまたまクリシュナムルティに関する本を読み、彼の論旨にひどく興味を覚えた後、インドのマドラスで彼の講話を聞いた瞬間から完全に彼の虜になってしまった。ナチスのヒトラーと同人種であることから、何か世間に対して一種の劣等感を意識していた彼は真剣になって心の安定を求めていたからかも知れない。彼は何人かの同僚と共にクリシュナムルティの講話のスケジュール通りに世界各国をまわって教えの真髄を探り出そうと躍起になった。そして出来るだけクリシュナムルティの身辺にいたかったのでオハイの財団が学校新設のための人手を募集したとき、イの一番に応募したのである。そして採用されて定められた彼の職務は学校関係の食堂の料理人だった。料理には全くズプの素人だった彼がその任務に懸命に励んだのもすべてクリシュナムルティとの関係をより親密なものにしたいという彼の熱望のせいだった。クリシュナムルティに対する彼の惚れ込みようが判るというものだ。そしてその後10数年間もクリシュナムルティがオハイに滞在している間、ずっと彼と彼の客達の料理を作り、殊に会食会では彼自身も食事のお相伴にあずかったのである。食事の前後や食事の合間に、クリシュナムルティと毎日入り変わり立ち替わり訪れる客達との間にいろいろな会話が交わされたのだが、それを傾聴するのが彼の最大の生き甲斐だったのだ。
彼は彼自身も参加したその会話の詳報、特にクリシュナムルティの自由奔放な発言を逐一録音したり、書き留めておいたようで、この本の主題となつているのはそうした会話やクリシュナムルティ自身のあからさまな感想録なのである。
教育、政治、社会情勢に対する彼の忌憚のない見解があますところなく吐露されているが、特にキリスト教などの既成宗教に対する彼の皮肉が痛烈に表明されている。そのどれもが興味あふれるジョークとなって発言されるので食卓はいつも笑いの渦になってしまう。そういう情景が活き活きと描写されていて、一旦読み出したら途中で頁を閉じるのが勿体ない気持ちになる。それが私の偽らない読後感である。
その原文の持ち味を私の訳文がどの程度再現できているのか心細い限りだが、非才は非才なりに最善を尽くす以外道がない。
実はもつとずっと早く出版される予定だったが、中途で帯状疱疹になったり、肺炎をおこしたりして計画が大幅に遅れてしまった。不徳の至すところで弁解の余地はない。
尚この訳本の校正に当たって丸岡(旧姓 田港)陽子、亀田映子、露木純子の諸子にいろいろ協力して貰えたし、表紙の絵は式根和美氏の画才に依存した。特に出版に際しては大野純一氏の協力に負うところが絶大である。紙面を借りて深く感謝の意を表したい。