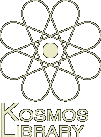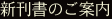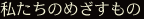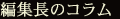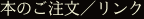第17回
『戦国武将たちの家訓より』
ご無沙汰しております。前回は『ヨブ記』刊行をお知らせし、ついでにイタリア人精神病学者ロンブロゾーが書いた『天才論』の一部をご紹介しました。これはとてもおもしろい本なので、少しづつ読み進め、あちらこちらで引用して紹介しています。
その後、新刊紹介にもありますように、心身一体療法研究所所長で日本トランスパーソナル学会常任理事でもある本宮輝薫さんの著書『真気の入れ方と邪気の抜き方──色彩・言葉・形が気を動かす』を8月に刊行し、次いでドン.ミゲル・ルイス著/大野龍一訳『祈り』を9月に刊行しました。どちらも好評のようです。
特に『祈り』は、『四つの約束』『愛の選択』『四つの約束──コンパニオン・ブック』と併せていちおうルイスの四部作を構成し、これでそのすべてを出すことができました。
また、今後の予定としては、パトリック・ライス著/畠瀬稔+東口千津子訳 『鋼鉄のシャッター──アイルランド紛争とエンカウンター・グループ』を年内に刊行の予定です。『鋼鉄のシャッター』はロジャーズの先駆的エンカウンター・グループの記録で、次のような内容です。
北アイルランド紛争は、英国が12世紀にアイルランド島を支配して以来続いていた。
貧しいカトリックと裕福なプロテスタント。何世紀にも渡った憎しみ合い。紛争は泥沼化していた。1972年、ロジャーズらは、北アイルランドの首都ベルファーストから来たプロテスタント4名、カトリック4名、英国陸軍退役大佐1名と、3日間24時間のエンカウンター・グループをもった。
本書はその記録であり、社会的・国際的紛争解決への示唆を与えてくれるであろう。
『鋼鉄のシャッター』に続き、フォーカシングに関する素晴らしいエッセイ集を出す予定です。これはニール・フリードマン著/日笠摩子訳『フォーカシングとともに(1)──体験過程との出会い』です。かなり厚い本なので、3部に分け、まずその(1)をなるべき早く出したいと思っています。これを読むと、フォーカシングとはなんと幅も奥行きも深い技法なのだろうと素人でも実感でき、改めてフォーカシングの魅力がわかると思います。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
最近、和辻哲郎著『埋もれた日本』(新潮社1951)という本を読みました。戦後間もない時期に書かれたもので、漱石や藤村や露伴の思い出や、『菊と刀』についての批判など、様々なエッセイが収録されています。その中に本書のタイトルとなった「埋もれた日本」という論考があり、とてもおもしろい話が出ていたので、ご紹介したいと思います。副題は「切支丹渡来時代前後における日本の思想的情況」と、ちょっとものものしい感じがしますが、内容は室町時代の生き生きした不雰囲気を教えてくれるとても面白いものです。
特に「新興武士階級」についての話が興味深いのです。もちろん、武力をもって権力を握ろうとする点で旧来の武士階級と異ならないのですが、一つの点ではっきりと違う。それは旧来の武士が「伝統」の上に立っていたのに対し、新しい武家が「実力」の上に立っているということです。「源氏」といった由緒や家柄の上に立っていた古い武家にかわって、民衆運動が勃興してきた後には、武家には実際の「統率力」や「民衆を治める力」が必要となり、そのため由緒のかわりに実力がものをいうようになったのです。それで、政治的才能の優れた統率者が、民衆の英雄待望的気分を背景にして、いわゆる「群雄」として台頭し、民衆の心をつかむようになりました。
「早雲寺殿二十一條」
そのような群雄で最も早いのが北條早雲です。素性のはっきりしない浪人だったのですが、今川氏に内訌(内輪のもめごと)が起こった時に政治的手腕によってそれを巧みに解決し、その功績によって愛鷹山南麓の高國寺城を預かります。それをきっかけに関東に進出し、1495年(明徳4年)に小田原城を、1518年には相模一国を征服しています。彼は善政をおこない、租税を軽減したことで民衆の人気を得たのであり、彼の支配の下で小田原の城下町は大いに繁盛しました。
早雲の名において「早雲寺殿二十一條」というものが残っています。その中では「正直」が最も力説されており、これは伝統的思想と少しも変わらないのですが、それを説く態度がこれまでになく「率直」だというのです。「上たるをば敬い、下たるをばあわれみ、あるをばあるとし、なきをばなきとし、ありのままなる心持、佛意冥慮にもかなうと見えたり」とか「上下万民に対し、一言半句もうそを云わず、かりそめにもありのままたるべし」とかいう場合の、「ありのまま」という言葉にその率直さが現われているというのです。陰謀術策がさかんにおこなわれていた時代に、そうしたやり方を弱者の卑劣さだと認め、「ありのまま」の態度に「強者の高貴性」を認めたのです。和辻先生によれば、こうした掟には禅宗の影響があるとし、武術の訓練よりも学問や芸術の方を熱心に奨めているのはそのせいだろうとし、「力をもって事をなすは下の人であり、心を働かして事をなすのが上の人であるとの立場は、ここにもうはっきりと現われていると思う」と述べています。
これによれば、ブッシュ大統領は「下の人」ということになります。実際、ブッシュ政権下のアメリカは今や、北朝鮮と並んで最も危険な国と評されるようになっています。
「朝倉敏景十七條」
また、早雲と同じ頃に台頭した越前の朝倉敏景という群雄がいます。後に織田信長にとっての最大の脅威となったこの武将は、「朝倉敏景十七條」を残しました。その最も目立つ特徴は「伝統や因習からの解放」で、人事については家柄に頼らず、各人の器用忠節を見きわめて任用すべきことを力説しています。戦争については、吉日を選び、方角を考えて時日を移すといった迷信からの「脱却」を重大な心掛けとして説いています。また、正直者の重用を説き、「理非を絶対に曲げてはならない」こと、断乎たる処分も結局は慈悲の殺生であることなどを力説しています。和辻先生はそこに、精神の自由さと道義的背景の堅固さを感じることができると述べています。
「多胡辰敬家訓」
その後しばらく経った頃に書かれたものに「多胡辰敬家訓」というのがあります。多胡辰敬は尼子氏の武将で、祖先の重俊は将軍義満に仕え、日本一のばくち打ちという評判を取った人でした。その後三代、ばくちの名人が続いたが、辰敬の祖父はばくちをやめ、応仁の乱(1467-1477)の際に京都で武名をあげたということです。辰敬の父も「近代の名人」と評判されたが、実際はばくちを嫌っており、そして「辰敬家訓」として述べられているのも、実はこの父の教訓でした。
辰敬自身は、諸国を放浪している間に、北條早雲のように、「力をもって事をなすは下の人であり、心を働かして事をなすのが上の人」ということを悟りました。そこで彼は「学問の必要」を強く力説しています。そのためこの家訓は、主として「学問の心得」を説いたものになっています。まず初めに手習学問を勧めていますが、それは「文芸」を初め諸種の「技芸」の勧めです。しかもその重点は平安朝の文芸を模範とした教養の理想に置かれ、それが戦国末期の勇猛な武士だというのはとても興味深いことです。「柔よく剛を制する」ということを心得ていたのでしょう。
さらに注目すべきは、「算用」という概念で「合理的思考」を勧めていることです。「算用を知れば道理を知る。道理を知れば迷いなし」というのです。その道理とは、自然現象の中にある「きまり」を意味するとともに、人間がなすべき行為を支配する法則のことでもあり、それがかなり綿密に考察されているのです。例えば「身持が身の程を超えれば天罰を蒙る」という命題。これは「ギリシャ人などが極力驕慢を警戒したのと同じ考えで、ギリシャにおいても神々の罰が覿面(てきめん)に下ったのである」と和辻先生は指摘しています。
重要なのはその後の「位よりも卑下すれば、我身の罰が當る」という部分です。なぜなら、これは「自敬の念」を重視し、「自敬の念を失うことは、驕慢と同じく罰に値する」ということを意味しているからです。「ここに我々は、実力格闘の体験のなかから自覚されてきた人格尊重の念を看取することができる」のです。辰敬は、こうした道義的反省をも「算用」と呼んでいるのです。自分の立場にふさわしく自分を大事にし、品位を保つことも、「自己責任」の一部だと見なしたのでしょう。
また、算用は「公私の区別」にも及んでいます−−家の中で非常に親しくしている仲でも、公共の場では慇懃な態度をとれとか、召使いは客人の前では厳密に規律を守らせ、人目のない時には労ってやれといったように。
算用はさらに人の「躾(しつけ)」にも及んでいます。「小さい不正の度重なる方が、稀に大きい不正を犯すよりは重大である」ということを見抜くのもやはり算用なのです。大きな咎(とが)は稀であるが、小さな咎は日々に犯されるがゆえに、放っておけば習性になる。だから大きい咎は人によって許してよいが、小さい咎はけっして許してはならない、というのです。「塵も積もれば山となる」からです。不正は、大きく育つ前に、芽のうちに摘んでおく必要があるということでしょう。これは、『易経』の中の次の警告を思い出させます。
善行も数多く積まなければ名誉を得るに至らないし、悪事も数多く重ねなければ身を滅ぼすには至らない。ところが小人は、わずかの善行など利益にならぬと考えて行なおうとせず、わずかの悪事ならたいしたことはないと考えて中止しない。しかし、こうして悪事を重ねるうちに、ついには身の破滅は逃れようもなくなる。
これらの家訓を読むと、「戦国の武士の道義的性格は決して弱いものではなかった。また真実を愛し、合理的に物を考えようとする傾向においても、すでに近代を受け入れるだけの準備はできていた」ことがわかる、と和辻先生は指摘しています。
「甲陽軍鑑」
最後に、和辻先生は「甲陽軍鑑」を取り上げています。武田信玄ゆかりのこの書の著者についてはいろいろ説があるようです。が、それはさておき、興味深いのは、「命期の巻」にある「我国をほろぼし我家をやぶる大将」の四種類です。主に戦国武将の考え方を知る上で重要であるだけでなく、現在でもリーダーを見分ける時に十分に参考になるでしょう。第1は「馬鹿なる大将、鈍すぎる大将」です。第2は「利根すぎる大将」、第3は「臆病な大将」、そして第4は「強すぎる大将」です。
第1の「馬鹿なる大将」とは、「自惚れのある人」のことです。けっして知能が足りないということではありません。才能優れ、意志強く、武芸も人に勝っている、そういう人でも自惚れていれば馬鹿になりうるのです。「自分のすることはすべて良いことだと思う」人です。独善。彼は、家来に「ごもっとも」と言われ、おだてられます。で、自分で善悪の判断ができなくなってしまい、したがってますます馬鹿になるのです。
大将が馬鹿の場合、同じような馬鹿者が重用されるようになります。その馬鹿な重役がまた同じような馬鹿者に諸役を言いつける。とうとう家中が「たわけ」だらけになってしまう。10人の内9人までが軽薄なへつらい者になり、互いに利害あい絡んで、仲間ぼめと正直者の排除に努める。しかも大将は、自惚れのゆえにこの事態に気づかない。100人の中に4、5人の賢人がいても目にはつかない。いざという時にはこの4、5人しか役に立たず、常日頃忠義顔をしていた95人は影を隠してしまう。家は滅亡するしかないのです。
第2の「利根すぎる」大将とは、利害打算にはきわめて鋭敏だが、賢明で剛毅でもない人のことで、幸運の時にはふんぞりかえるが、不幸に遭うと萎縮してしまう。口先では体裁のよいことを言うが、勘定高いので無慈悲である。また、見栄坊であって、自分の独創を見せたがり、人まねと思われないように気を配る。
こういう大将は、利にさとい金持ちや町人などにうまくつけこまれるので、やがて家風が町人化し、口先のうまい、利をもって人々を味方につける人がはばを利かしてきます。100人のうち95人が町人行儀になり、残り5人は人々に悪く言われ、気違い扱いにされ、何事にも口が出せなくなる。5人のうち3人はついに町人行儀と妥協し、あとの2人はその家を去る。こうしてこの家中は、家老から小者に至るまで、意地汚い、人を出し抜こうとするような気風になってしまう。
第3の、臆病な大将とは?「心愚痴にして女に似たる故、人を猜(そね)み、富める者を好み、諂(へつら)える者を愛し、……分別なく、無慈悲にして心至らねば、人を見しり給わず」というような、心の剛毅さを欠いた、道義的性格の弱い人物です。「けち」だと言われまいと思って、知行(封土・領地)を多く与えたりするという具合に、「外聞を本にして」動く傾向がある。強い大将なら、ぜひとも物を蓄えるべき時には、貪欲と言われようが意地汚いと言われようが、頓着せずに蓄える。知行を与える場合は、外聞など気にせず、あくまでも人物や忠功を見て決めるのです。
こうした大将の下では、軽佻浮薄な、腹の据わらない人物が跋扈する。おのれより優れたものを猜(そね)み、劣ったものを卑しめる、性格の弱い、道義的背骨のない人物。「そねむ」とは優れた価値を引き下ろすこと、「卑しめる」とは人格に侮蔑を加えることであり、道義的には最も排斥されるべき行為です。法螺吹きを「そしる」とか、自慢話を言い「けす」とかと厳密に区別されるべきなのです。
そして第4は、強すぎる大将ですが、なぜだめなのでしょう?心剛毅にして、明敏で、弁舌さわやかで、知恵も優れ、短気にもならず、よく物事の奥を見きわめることができるのですが、ただ何事についても「弱見なることを嫌う」。この一つの欠点のせいで、いろいろな破綻が生じてくるのです。この性格をはばかって、家老は、内心は穏健に処すべきような事柄についてもそうはっきり言えず、筋道立てて大将を説得するに至らない。その不徹底ぶりに大将は不満を感じる。その隙につけ込んで、野心のある侍が、大将の意にかなうような強硬意見を持ち出すと、大将はただちに乗ってくる。野心家はますますそれを煽り立てていく。その結果どうなるでしょう?
大将は「知謀を軽んじ」、「武勇の士をことごとく失ってしまう」ことになるのです。なぜ?なぜなら、無謀な戦いによって、侍全体の内20%を失ってしまうからです。つまり、「剛強にして分別才覚ある男」(上の部:わずか2%)、「剛にして機のきいたる男」(中の部:わずか6%)、「武邊の手柄を望み、一道にすく男」(下の部:12%)が戦死し、残りの80%の「人並の男」(猿侍)だけが残ることになるからです。そうなれば全滅と変りはないのです。
理想の大将
以上の国を滅ぼす4類型を裏返せば、「理想の大将」の類型が浮かび上がってきます。それは、「賢明な、道義的性格のしっかりした、仁慈に富んだ」人物です。そこには古来の正直・慈悲・智慧の理想が有力に働いているが、特に「人を見る明」が力説されていることが目立っているようです。これはどの時代でも重要ですが、戦国時代の大将がこの「明」を得るには、「自惚れ」や「虚栄心」や「猜(そね)み」などの私心を去らなくてはなりませんでした。が、ひとたび大将がこの「明」を得れば、彼の率いる武士団は強剛不壊のものになってくる。ということは、「道義的性格の尊重」が彼の武士団を支配するということです。ですから、大将の理想は道徳的に優れた人物になることにあったわけです。
自敬の念
正直・慈悲・智慧の理想と並んで、「甲陽軍鑑」全体にわって明白に現われているもうひとつの明白な特徴として、和辻先生は強烈な「自敬の念」を指摘しています。「多胡辰敬家訓」に「位よりも卑下すれば、我身の罰が當る」という言葉がありましたが、それが、武道、男の道、武士道などを問題にする場合によりいっそう顕著に現われているというのです。これらの「道」は本来は争闘の技術を言い表わしていたのですが、そこに「心構え」が問題とされるようになると、明白に道徳的な意味に転化してきます。そしてそこで中心的な地位を占めているのが自敬の念なのです。
おのれが臆病であることは、「おのれ自身において」許すことができない。だからおのれ自身のなかから、「死を恐れぬ心構え」が押し出されてくる。また、おのれの意地汚さや卑しさは、「おのれ自身において」許すことができない。「廉潔」を貴ぶのは、外聞のゆえではなくして、自敬の念のゆえである。このようにして、おのれ自身のなかから「男らしさの心構え」が押し出されてくるのです。自敬の念に基づく心構えが武道とか男の道の主要な内容になってくると、争闘の技術としての武道はむしろ「兵法」という言葉によって現わされるようになる。そこで、武道、男の道、武士の道とは、道徳、自敬の立場に立って卑しさそのものを忌み、「貴さ」そのものを尊ぶ道徳、と言うことができるようになります。これは尊卑を主とする道徳である、したがって貴族的である。そしてこの立場は、「敵を愛せよ」というかわりに「敵を敬せよ」という標語に現わすことができるかもしれない。そう和辻先生は結論づけ、次のように述べています。
信玄家法のなかに、敵の悪口を言うべからずという一項がある。敵を罵ることによって敵を憤慨させれば、それだけ敵が強まることになって損である、という利害打算もあるいは含まれているのかも知れぬが、しかし根本にある考えは、尊敬し得ないようなものは敵とするに値しない、敵に取ったということは尊敬に値する証拠であるというにあるであろう。そういう心持を詳細に説明した箇所もある。信玄自身は謙信に対する尊敬によってこのことを実証していたのであった。信玄の遺言といわれているものは、勝頼に対して、おのれの死後謙信と和睦せよ、和睦ができたらば、謙信に対して頼むと一言云え、謙信はそう云ってよい人物であると教えている。真偽はとにかく、信玄はそういう人物と考えられていたのである。
こうした「自敬の念」は、現代風に言えば、「自己決定」に基づいて「自己責任」として卑しさを忌み、貴さを尊ぶとことと言えるかもしれません。これは「自己規律」の仕方としてきわめて注目すべき態度と言い得るでしょう。なぜなら、他からの強制によるのでなしに、みずからの意志で、自発的に、優雅に自己を律し、気高く、廉潔に生きることを選んでいるからです。これは、現代に生きる私たちにも重要なヒントを与えてくれると思います。なぜなら、私たちは実に放縦な、欲望全開の生活を送っているからです。戦国武将のように、そうした生き方を「おのれ自身において」許さず、みずからを律して、シンプルな生き方に切り換えることが急務なのではないでしょうか?