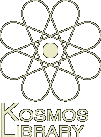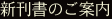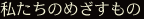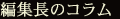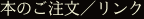第42回
2020年5月7日
『昭和の動乱』に学ぶ――「昭和の日」にちなんで
読者の皆様
いかがお過ごしですか? 新型コロナによるパンデミックが続いているさなか、久しぶりに編集日記を書かせていただきます。それは、4月29日が「昭和の日」という祝日だったということに、うっかり気づかずにいたからです。「何を今更呑気なことを言っているのだ」とご叱正を受けそうですが、本当なのです。そこで改めてWikipediaを見ると、次のようになっています。
昭和の日(しょうわのひ)は、日本の国民の祝日の一つである。日付は2006年(平成18年)までみどりの日だった4月29日。2007年1月1日施行の改正祝日法で新設された。
国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)の一部改正によって2007年(平成19年)に制定された祝日で、日付は昭和天皇の誕生日である4月29日があてられている。同法ではその趣旨を、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」としている。「ゴールデンウィーク」を構成する祝日のひとつでもある。
実は、最近『人間の知恵の歴史―宗教、哲学、科学の視点から 復刻版シリーズ①古代篇』という本を出したところなのです。それで、「昭和の日」にちなんで、改めて「歴史」というものの一端に触れてみたくなりました。
小生は昭和19年11月11日生まれなので、今年75歳、つまり終戦の前年生まれです。11月11日というのは、実は「世界平和記念日」なのです。やはりWikipediaによれば、
世界平和記念日・第一次世界大戦停戦記念日(11月11日 記念日) 1918年(大正7年)のこの日、ドイツとアメリカ合衆国が停戦協定に調印し、4年あまり続いた第一次世界大戦が終結した。主戦場となったヨーロッパの各国では、この日を祝日としている。 この日を忘れず、大戦争を再び起こさないようにしようと設けられた。
ということで、あまり知られていないかもしれませんが、とても由緒ある日なのです。ただし、迂闊にも、編者はこの記念日は「第二次大戦」が終了した「1945年」に設けられたのだとずっと思いこんでいました。つまり、それほど小生の「歴史認識」はずさんだったのです。ただ、全くの思い違いにしろ、昭和、平成を経て令和に至る今まで、ともかくも直接に戦争に巻き込まれずに来たというのは事実です。
ところで、「昭和の日」制定の趣旨は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」となっています。が、この昭和の時代、特に第二次大戦中のことは、おびただしい資料/記録があるにも関わらず、どうもその真実については、あまり見つめたがらない人が多いように思われます。南京大虐殺や従軍慰安婦といった話になると、我が国では反応が入り乱れ、いわゆる識者や論客たちは特に「頭に血が上り」がちのようです。これは諸外国と真逆のようで、ことに韓国や中国では、歴史的事実を忘れないようにすることが教育的に配慮されており、またドイツでも同様で、戦争中何が実際にあったかを忘れないよう、心がけていると思います。こんなことを言うと、すぐに「自虐史観」論者だとレッテルを貼られそうですが。
暗殺されたケネディは、「敵を許すことだ。だが、決してその名前を忘れるな。」と言い残しているそうですが、『夜と霧』のフランクルも、自らが被害者となった、ナチスドイツの所業に対して、「許せ、だが忘れるな」と言ったそうです。二度と再び惨劇を繰り返させないためにも、歴史的事実を決して忘れず、それから多くのことを学び続けなければならないのではないでしょうか?
実は、今回ちょっとお話ししたかったのは重光葵(しげみつまもる)著『昭和の動乱』という本の触りのところです。昭和27年(1952年)に中央公論社から出された上下2巻本ですが、満州事変(1931年)から、2・26反乱(事件)(1936年)、日支事変(1937年)、大東亜戦争(1941年)を経て「降伏」に至るまでを、当事者として冷静に、客観的に、克明に描いています。
これは色々な意味で参考になると思われるので、便宜上以下の項目に沿ってご紹介させていただきます。◎はじめに ◎チャーチルの勇姿 ◎日本人の健忘症 ◎世界情勢と日本の末路 ◎東条大将の述懐と日本軍の弱点 ◎「大智」の必要性 ◎天皇の情勢把握と姿勢◎全面降伏への歩み ◎戦後処理、辞任 ◎ 賢治の『猫の事務所』◎「人類滅亡の悪夢」
◎はじめに
「上巻」の「緒言」(昭和25年3月1日 於巣鴨獄中記」で、著者(1887年(明治20年)7月29日 - 1957年(昭和32年)1月26日)は次のように記しています(文中で、重光さんはご自身のことを「記者」と言っています)。

昭和年間二十餘年の出来事は、日本歴史上内外にわたる大きな動乱であったと同時に、敗戦による開闢以来の革命でもあった。その革命は今日なお継続している。
この動乱は終始支那問題に関係するものが多い。記者は、満州事変勃発当時は中支公使として、また戦時、一時中支大使として日本を支那で代表する地位にあった。満州事変後、三年ほど外務次官として中央に留まり、のち昭和十一(1936)年から昭和十三(1938)年末まで世界動乱の震源地ソ連、それから昭和十六(1941)年6月まで、西欧の中心地英国に大使として欧州に在任し、それから日本が戦争に参加した後、戦争中二年間外務大臣の職にあったので、世界の動向に眼を注ぐ便宜があった。
敗戦の結果、記者は連合国側東京軍事裁判の俎上に上ること二年有半、その間、連日、検事側の提出する多くの材料や弁護側反駁資料に耳を傾ける機会を得た。これらの資料によって、記者のこれまで知らなかったことや、事件の発展について理解のできなかったことが、初めて明らかになった点がすこぶる多い。動乱全部を通じて、多少とも責任のあった記者にしてすでに然り、直接関係のなかった多くの人々には、この内外多年にわたる事件の発展について、合点の行かぬことが少なくなかったに違いない。二年半にわたって繰り広げられた資料を、できるだけ客観的に整理して置くことは、ひとり記者の興味の為のものではない、と信ずるに至った。けだし、昭和動乱は、史上未曾有の出来事として、日本人として仔細に研究し、将来国家再建のための自己反省の資料とすべき多くの事柄を含む、と思われるからである。記録の材料は、記者の過去の地位上知り得たこと、及び裁判資料中その都度手記したもの、または記憶に残ったものが、主たるものであった。そのほか、四年間牢獄生活を共にした他の、過去において、日本の指導に直接関係した人々について聴取し得た貴重な資料をも含むものである。
昭和の動乱について、責任を正当に批判することは容易のことではない。達識ある歴史家でも将来多くの時間を必要とすることと思われる。記者は、もとより、歴史上の審判を試みんとするものではない。単に局に当たったものの義務として、自分の正確であると信じたことを、若干の観察をも加えて、歴史の資料の一つとして提供せんとするにすぎない。
東京軍事裁判は、もとより、戦勝者の敗戦者に対する一方的かつ敵味方の関係においてする軍事的の裁判であって、日本の侵した国際的犯罪の存在を前提として行われたものであった。多数の判事の判定はこれを確認したものであったが、少数判事の判定は、比島(フィリピン)判事の判定を除き、これと全く趣を異にしたものであった。特にインド判事パール氏の判定は、全面的に、多数判事の判定とは反対に、日本の行動を是認したものであった。東京裁判そのものについては、すでに大体世界の定評の存するところである。歴史研究家は多数判定のみならず、少数判定をも見逃すことなく、また裁判資料については、検事側及び弁護側提出の全ての材料について、裁判所において受理されたものまた受理されなかったものも共に、慎重に検討することが必要と思われる。
昭和動乱の由って来たるところ、及びその経過の日本将来に及ぼす影響について、科学的研究が進めば進むほど、日本民族の将来に有益であると思われる。
『昭和の動乱』をざっと通読していると、著者がいかにこの「実証的・科学的」姿勢を堅守し続けているかに感動させられます。つまり、勝手な「思い込み」は厳に慎み、できるだけ「事実(だと確信できるもの)」を伝えるべくことに専心しており、その姿勢は、昭和天皇だけでなく、満州事変がらみの北一輝や大川周明、さらには中心人物の一人、近衛文麿などの言動についての記述にも貫かれています。また、社会全般の風潮についても、次のように記しています(上巻の初めの方にある「金権跋扈」という、第一次世界大戦当時の状況を記した項)。
・・・戦争中の繁栄によって富をなしたのは、明治以来の政商として大をなした三井、三菱、住友等のみでなくして、東京・大阪・名古屋を中心とする大小商人が急に莫大の富を蓄積することができた。これがために、戦後においても日本に成金の氾濫時代が現出した。戦時獲得した一半は、その後の世界的経済激変と、京浜地方の震災とによって失われたが、多くの新興大小財閥は、残存しかつ繁栄することを得て、新興資本家の傍若無人な横暴振りを発揮した。かかる成金風潮が、穿きちがえた自由主義思想に便乗した結果、社会に与えた悪影響は、名状し難きものとなった。国民的道徳は低下し、風俗は乱れ、自由主義は極端に流れ、物質主義は横行した。金権が直ちに政治を左右するようになるのは当然である。
「自由と放縦の穿き違え」というのは、人間に付きまとっている永遠の課題ですが、これが昭和の動乱の根底にもやはりどす黒く渦巻いていたのです。真の自由とは、一つには、そうした自分の貪欲な自己中心性に気づき、「嬉々としてそうした自己を律し、軽挙妄動を慎む」ことにあるのではないでしょうか。「道徳」などという言葉は、特に実業界では敬遠されがちで、例えばアメリカなどでも、どういう社員が「望ましくない」かについての調査において、「高潔な人間」という答えが多かったという話を聞いたことがあります。さもなければ、カジノを組み込んだ「統合型リゾート」などに飛びつかないでしょうから。
◎チャーチルの勇姿
さて、この大著の中で、編者が注目したことの一つは、上巻の「軍部の盲進(阿部、米内軍部内閣)」という編中にある「史上の偉観」という、チャーチルのことが紹介されている箇所です
要するに、ナチスドイツ軍という強大な敵を前にして、「国家存亡の瀬戸際」に立たされとき、英国民および議会を前にして、その代表たるチャーチルがどのように振る舞ったか、その勇姿を、当時英国にいた著者は目の当たりにしたのです。
1940年6月18日の英国議会において、まず、チャーチル新総理は、第一回の戦況報告を行い、「淡々として、北仏(フランス)における(英国の)敗戦を少しの虚飾もなく正当に評価して、その経緯を詳細に叙述し、ドイツ軍の見事な戦術とその大成功とを説き、連合軍は健闘にも関わらず惨敗し、英軍はついに海岸に退却を余儀なくせられたことを述べ、ダンケルクの悲壮にして勇敢なる軍隊の救出状況を敍し、英雄的に闘った仏国軍も、ついに力尽きたることを明らかにした」のです。「現実に即した冷静平明にして、男性的なるその叙述は、聞くものの肺腑をえぐるがごときものがあった」と著者は記しています。
重要なことは、チャーチルが戦況を事実「ありのままに」、つまり「大本営発表」的にではなしに議会/国民に知らせたということです。続けて、「もし仏国が脱落したら、英国は単独でドイツという強国と死闘しなければならない」と指摘しています。彼はさらに英国が直面している状況を述べています。その場に居あわせた著者は次のように記しています。
フランスが脱落したら、英国は単独でこの強敵と死闘しなければならない。敵は対岸に立っている。何時侵入して来るか分からない。今日は、英国歴史始まって以来の最大危機である。自分は、陸海空三軍の首脳部に専門家の意見を求めた。彼らは未だ勝利可能の見込みを捨てていない。英国人の戦意が、ドイツの享有している量的および物的な優越を乗り越え得ることを信ずると言うのである。英国人は、独裁専制の敵に屈するよりも、最後の一人まで戦う決意を持っている。このようにして、英国がついに最終の勝利に到達することを今日なお確信するものである。「今や英国の戦い(Battle of Britain)が展開されようとしている。人類文明の安危は、この戦に掛かっている。四自治領は、我々の戦争継続を全面的に支持している。勝利か、死か、我々はその一つを選ぼうとしている。もし、英帝国が千年の久しきに亘って続くものならば、これぞ彼らの最も光輝ある時(their finest hour)であったと、後世の人をして讃美せしめようではないか」と述べ終わって、熱涙の下るまま頭を抱えて自席に着席したその光景は、これを見た者の忘れることのできぬ光景であった。
この歴史的演説を聴き終わった著者は次のように締めくくっています。
議場の中央に立って演説を終えたチャーチルが、一、二歩後方の自席に引き下がった瞬間に、議場は湧き返った。隣の席にいたチェンバレンは、立ち上がって熱烈に拍手し、ハンケチを振った。議場は総立ちになって、議事日程やハンケチを振り、足摺をして熱狂した。傍聴席も沸いた。この光景は、宣戦布告をした一年前の議会の冷静にして事務的なりしに比して、何と甚だしく異なったものであったことよ。英国人は、時として、かくも血を沸かすことがあるのである。
議会の表示した決意は、英国民一人一人の決意であった。この国家存亡の危機に際して、国民的決意の表示せられた瞬間は、真に光輝ある一時であった。英国民はまた元の冷静に還って、日々の仕事を急いだ。政府も工場も家庭も日夜働き続けた。
記者は本国政府に対して、この歴史的議会を参観した後「史上の偉観」であったと報告した。
以上は『昭和の動乱』上巻の最後の方に出ている記述です。これに続く下巻の冒頭「第七編 日独伊三枢軸(第二次及び第三次近衛内閣)」には、時の内閣総理大臣、近衛公と「長州萩出身で、米国西海岸のオレゴン大学に学んだ」松岡洋右について触れるに先立って、「日本人」についての興味深い記述があります。
◎日本人の健忘症
日本人は健忘症である。第一次近衛内閣が何をしたか、また、日本のためにいかなる存在であったか、は、さらりと忘れてしまっていた。日本人の政治的責任感は、遺憾ながら、一般的に薄い。政治は結局国家の仕事であり、すなわち、国民の責任であることは、いまだ十分に自覚されておらぬ。政治家も、一旦辞職すれば、責任は解除せられるものと、簡単に考えている。日本人は、政治を見ること、あたかも芝居を見るがごとく、鑑賞はしても、自分自身が役者の一人であり、みずから舞台の上にあることを悟ってはいない。いかに手際よく、その日の舞台劇をやって見せるかに腐心するのが、また政治家であって、国家永遠のことを考える余裕を持つ者が少ない。
これは現在まさに言えることではないでしょうか? 古代中国では、「天に声あり、人をして語らしむ」と本当に思い、自らの国政に採り入れていた国王がいたのでしょう。また、宮廷内の歴史記録係は、事実をあるがままに記録しなければならない、たとえ自分が仕えている王であっても、たとえば何らかの不始末をしでかしたとしたら、その事実を正直に記録しなければなりませんでした。実際、馬鹿正直にそれを実行したために殺された記録係がおり、されにそれを引き継いだ息子も改めてその事実を記録して殺されたことがあるようで、その後ようやくその国王がみずからの過ちを認めて、記録を許したという故事がありますが、それぐらい歴史的事実は重いのです。
『昭和の動乱』というのは、まさにそうした事実の記録であり、重光さんは『史記』の司馬遷と同様のことを昭和史の記録で試みたのです。登場人物は昭和史を彩った大小様々な要人が多いですが、重光さんはそうした登場人物の(しばしば「お粗末な」)内面にも迫っています。それは、戦後、最重要人物の一人、近衛公について述べた、次のような手厳しい批判の言葉にも如実に現れています。
近衞文麿とは親交があったが、敗戦後、近衞が戦争に関する自分の責任を回避すべく天皇や軍部に全責任を転嫁するかのような言動に終始したことについては「戦争責任容疑者の態度はいずれも醜悪である。近衞公の如きは格別であるが…」(Wikipedia)
なお、今回の「編集日記」の冒頭にあるチャーチルの紹介に代表されるような「親英米的、民主主義的」言動から、重光さんは一部の人々から煙たがられてきたのではないかと思われます。
◎世界情勢と日本の末路
下巻中の「日本と作戦 その一(全貌)」の冒頭に、重光さんがいかに世界情勢について、また人間について透徹した見方をしていたかを示す言葉があります。
これから記者(重光さん自身)は、第二次世界大戦における、日本の敗戦の冷厳なる歴史を語らねばならぬ。日本の敗戦は、戦争に至る過去十餘年の政治的破綻の集積であることは、今更言うまでもない。
国家としても、個人としても、独善にして反省なき者は、自ら目隠しをして、猛進するようなものである。今日の国際生存競争場裡において、国家として生存を全うするには、大智なくしては不可能である。世界の形勢について、大局的判断を誤れる国の前途は、始めから定まっている。日本は、不幸にして、大局上の判断を誤ったのみではなく、日本的焦燥感につきまとわれた。その結果は、始めから総てが玉砕型に陥ってしまった。政策的玉砕型は、作戦においても玉砕型となり、戦時日本人の心理にも、これが多分に作用した。玉砕は、感激を伴うけれども、堅忍と叡智とは更に貴重である。
欧州戦争が始まった後に、三国同盟を締結して渦中に入り、独ソ戦争の結果が危ぶまれる際に、敢えて南進を決行し、欧州戦争の大勢が定まってきた時に、世界最大の二強国を敵に廻して、世界戦争に突入するというのは、何としても日本的の玉砕型であった。
その大戦争中にあって、作戦上内外における統帥上の不統一があったことは、物質力の測定を誤ったことと共に、敗戦の根本的原因をなした。日本の指導が、政治上、経済上および心理上、その他万般のことにおいて、冷静なる科学的の検討に欠如していたことが、戦争によって遺憾なく暴露された。
◎東条大将の述懐と日本軍の弱点
この記述の直後に、著者は、敗戦後、巣鴨で東条大将と敗戦の原因について話し合う機会があり、次のようなことを聞かされています。
敗戦の「根本は不統制が原因である。一国の運命を預かるべき総理大臣が、軍の統帥に関与する権限がないような国柄で、戦争に勝つわけがない。その統帥がまた、陸軍と海軍とに判然と分れて、協力の困難な別々のものとなっていた。自分がミッドウエーの敗戦を知らされたのは、一ヶ月以上後のことであって、その詳細に至っては遂に知らされなかった。かくの如くして、最後まで作戦上の完全な統一は実現されなかった」と述懐した。沈黙を厳守していた彼が、この最後的の述懐をしたのは、余程のことであったと思われる。東条大将は、最初に陸軍大臣であり、次いで首相兼陸相として、戦争を指導し、最後には参謀総長をも自ら兼ねて、政治と統帥を統制線として、その権力を一身に集めた人である。死を前にした彼の言葉は、少なからず価値のあるものと思われた。
このミッドウエーの敗戦というのは、1942年6月5日のことで、「これが日米戦争の峠であった。アメリカ側の士気は頓に(とみに/一気に)上がり、その巨大なる工業力による戦備は、急激に増加し、軍隊の訓練は急進し、技術は進歩し、その驚くべき物質的機械力により、日米双方の実力の相違は次第に大となり、以後、日本側は遂に形成を挽回することを得なかった」のです。
が、「作戦指導の全般に甚大なる影響を与えた、ミッドウエー日本海軍の敗戦は、日本国民にもまた内閣にも真相は知らされなかった。海軍部内でも、少数の者以外には秘密にされ、現場から帰った者には箝口令が敷かれた(口外が禁じられた)。」
これは、ドイツ侵攻を前にしてチャーチルが率直に現状を知らせたのとは大違いです。このことについて、著者は次のように指摘しています。「日本軍は失敗することを許されない。また失敗を承認することは、なおさら許されない。ミッドウエー戦闘は、敵に対して、我が損害より以上の損害を与えた如く発表された。事実を事実とせず、失敗を失敗とせざるところに、日本軍の根本的弱点があった。これは陸海軍に共通の封建的態度の一現象であったが、真に強き者の態度ではなかった。この陸海軍の態度は戦争の最後まで続いた。」
◎「大智」の必要性
繰り返しますが、重光さんは「今日の国際生存競争場裡において、国家として生存を全うするには、大智なくしては不可能である。世界の形勢について、大局的判断を誤れる国の前途は、始めから定まっている。日本は、不幸にして、大局上の判断を誤ったのみではなく、日本的焦燥感につきまとわれた。その結果は、始めから総てが玉砕型に陥ってしまった。政策的玉砕型は、作戦においても玉砕型となり、戦時日本人の心理にも、これが多分に作用した。玉砕は、感激を伴うけれども、堅忍と叡智とは更に貴重である」と述べています。
現代において、正道を歩むには、何よりも大局的判断を可能にする「大智」を持つことが是非とも必要であり、それによって困難を乗り越えるべく堅忍と叡智を発揮しなければならないというのです。これは、しかしながら、「言うは易く行うは難し」です。なぜなら、そのためには人間として「より高い段階」へと成長発達を遂げていなければならないからです。
例えば、勝海舟や西郷隆盛と意気投合して、江戸城の無血開城に寄与した幕末の英傑、山岡鉄舟は、実は、ある意味で「地球/宇宙中心的スタンス」へと達していたからです。実際、彼は、下町のボロ屋に住んでいて、ネズミ一匹殺さず、暴れまわらせていました。そして190センチもある巨漢で、剣道の指南をしていましたが、実際にはただの一人も殺したことはありません。
大森曹玄著『山岡鉄舟』(春秋社)中の「鉄舟の人と思想」という一章には、「万物一体の理」という項があります。それによると、彼は二十三歳の時に「宇宙と人間」との関係について記しているそうです。そこにはまず図解が示され、冒頭に「宇宙界」と書き、その下に「日月星辰の諸世界」と「地世界」とを描き分け、地世界をさらに「諸外国」と「日本国」に分け、日本国を公卿、武門、神官僧侶学者、農工商の4階級に分けています。要するに、人間と宇宙との一体性を図示しているわけである、と大森先生は指摘し、この概念的把握を、その後の剣禅修行の中で、体得できるものへと深めていったのではないかと指摘しています。そして安政の大獄(安政5年)などがあった、未だ身分制の厳しい時代に次のように述べています。「人のこの世に在るや、各々執るところの職責種々なりと雖も、その務むるところの業にして上下尊卑の別あるにあらず、本来人々に善悪の差あるにもあらず、人間済世の要として、一段の秩序あるのみ。」なお「済世」とは「社会の弊害を取り除き、人民の苦難を救うこと」で、実際、晩年にかけて、「書」が得意だった彼は、描いてくれと頼んでくる貧しい人々に快く分け与え、受け取った人々はそれを誰かに売って生活の足しにしていました。
また、吉田松陰の師で、河上彦斎という刺客に暗殺された佐久間象山という英傑をご存知かと思いますが、実は、彼は次のような言葉を残しています。
「二十歳にして一国(藩)に属するを知り、三十歳にして天下(日本)に属するを知った。四十歳にして五世界(国際社会)に属するを知った。」
彼は元治元年(1864年)、禁裏守衛総督を務める一橋慶喜に招かれて上洛、持説としていた公武合体と開国論を述べました。もちろん象山の言う開国とは西洋に迎合するものではなく、公武合体で日本が一丸となり、開国して、西洋に抗しうる最新の軍備を整えて列強の侵略を防ぐという、当時としては最も現実味のある策です。
しかし開国を説くことで、「西洋かぶれ」と誤解された象山は、帰宅途中、三条木屋町付近の路上で、肥後の河上彦斎らに斬殺されました。享年54。幕末には、今で言う「コスモポリタン」的スタンスを標榜することは、危険極まりないことだったのでしょう。こうした、「より高い、より広い視野を持ち、より開かれた生き方を模索していた」、例えば渡辺崋山(画人として知られる)などは、自害したり、悲惨な末期を迎えたりしています。(なお、余談ながら、刺客、河上彦斎(げんさい)は、幕末の四大人斬りの一人とされています。彼自身も、明治維新後も攘夷を強固に主張しつづけたため、藩と新政府に危険視され、37歳の時に斬首された。また、漫画「るろうに剣心」の主人公、緋村剣心のモチーフとなった。身長が150センチほどと小柄で、色白であったため、一見女性のようだった(Wikipedia)そうです。)
◎天皇の情勢把握と姿勢
ここで、さらに先に進む前に、昭和天皇が第一次世界大戦後の世界情勢をどのように把握していたのか、見ておきたいと思います。実は、天皇は前々から重光外務大臣から世界情勢について「大局的」な立場からの説明を受け、戦争には消極的だったようです。
1941年7月に御前会議が開かれ、「対英米戦を辞せず」という決定がなされた後に、宮中における御前会議でも、重光さんは、時の近衛首相などの要人にも、さらには軍部の本拠たる参謀本部にも出向いて、将校全員に向かって講演し、現下の世界情勢を報告しています。
なぜなら、外交官としての仕事柄、自分が目の当たりにしてきたことを伝え、適切な行動を促すことが責務だと感じたからです。その要旨は以下のようなものです。
まず、長らく駐在していた英国の情勢。「英国民の堅忍不抜の精神はすでに伝統的である。困難に遭えば遭うほど決意は堅くなり、忍耐は強くなるのが英国人である。これを指導するチャーチルは、稀有の闘士であって、鉄血の決意をもって戦時の英国民を率いている。彼は英帝国の総力を動員し、・・・また米国を完全に味方に引き入れている。海上における英国優越は言うに及ばず、空軍における勢力は、時間とともにドイツに接近しつつある。ドイツの海上封鎖は失敗しつつあるに反して、英国の大陸封鎖はますます効果を挙げつつある。
次に、欧州の情勢と国際関係について、ド・ゴール中心のフランス、さらに、事実上参戦している米国について述べ、「ドイツに対する英、米、ソ連の包囲戦が終局の勝利を得ることは、大勢上動かすべからざるところで、戦争はすでに峠を越えている」と述べ、結論として次のように述べています。
「日本は欧州戦争に介入してはならぬ。日本は絶対に戦争不介入方針を堅持し、現に着手している日米交渉を成功せしめ、且つ進んで、支那問題を解決して、日支関係を精算するようにせねばならぬ。日本が戦争に介入せず、外交によってその困難を解決する方針に出ずれば、日本の地位は欧州戦後必ずおのづから向上する。」
問題は、こう述べた重光さんが長い間海外に勤務していたので、その間の日本政府の方針や国内事情については不案内で、軍部の動向や御前会議の決定を知らなかったことです。ですから「みすみす負ける戦争に加入するほど日本人は愚かではない」とひたすら考えていたのです。もちろん、重光さんの講演は、「心ある」将校には相当な感銘を与えたのですが、それ以来「英米派」として宣伝され、「憲兵の尾行も付くようになった」のです。
チャーチルの勇姿を目の当たりにしてきた重光さんには、世界情勢の行く末は明らかだったのに対して、ヒットラーの勇姿に魅せられていた軍部にとってはドイツの勝利が常識であったのです。宣伝工作に長けていたヒットラーは、日本を同盟に引き込むために巧みにドイツの強さを印象付け、軍部はすっかりそれに幻惑されていたのです。そうした困難な状況の中で「適切に知恵を働かせる」ためには、「強靭な柔軟さ」が求められたのではないでしょうか。
こうして、若干の「心ある」重臣や将校がいたり、紆余曲折はあったものの、全体としてはまっしぐらに全面戦争に突入していったわけです。昭和16年9月6日の御前会議で、昭和天皇はいやいや「開戦の決意」を表示せざるを得なくなりました。ただ、この決定に対しては、天皇はあくまでも不満で、それを示すために次のような明治天皇の「御製」を読み上げるのがせいぜいでした。
よもの海みなはらからと思ふ世に
なぞ波風の立ちさわぐらむ
(四方の海、みな同胞と思う世に、
なぜ波風が立ち騒ぐのか)
今回、『昭和の動乱』に目を通して、昭和天皇が基本的に戦争に対して否定的だったことがわかり、また平成天皇が、それを継ぐようにして、遠い異国で非業の死を遂げ、眠っている戦没者に哀悼の想いを寄せ続けていたことへと繋がっていることがわかりました。
◎全面降伏への歩み
その後まっしぐらに全面戦争への道を猛進してきた挙げ句の果てに、とうとう「本土決戦」へと追い詰められてきた、陸海軍の「極端派」、昭和の動乱を通じて軍を動かしてきた実勢力としての「中堅将校」たちは「最後のあがき」とばかり、不穏な動きを示し始めました。彼らは次のように思っていました。
この際、軍の力を持ってクーデターを断行し、終戦の主導力であった天皇側近者や、政府関係者を除き、天皇を擁して戦争を継続し、敵の上陸作戦を阻止し、本土決戦によって一挙に勝敗を決すべし、万が一敗北すれば、国を挙げて玉砕も止むを得ず、少なく共平和は本土決戦までは考慮せず、と主張し、すでに皇室の避難所、政府の移転先も長野県に準備がある。
つまり、総力戦で死力を尽くし、全人民もろとも奈落の底に突き進む覚悟をしていたのです。そして直ちに「クーデター」が実行されました。重光さんはその様子を次のように記しています。
反乱は直ちに起った。陸軍省軍務局の、畑中少佐等の中堅将校を急先鋒とするものであった。彼らは、平和実現の中心である宮城を襲うことを考へた。彼らは近衛師団の参謀やその他の同志とともに、先づ天皇陛下の国民に対する終戦放送を阻止せねばならぬ、と考へた。
彼らは、近衛師団を動かすべく森師団長を訪問し、師団長を説得せんとしたが、その不可能なるを見て、師団長を参謀長とともにその場に惨殺し、師団長の命令書を偽造して、直ちに近衛師団の一部を動かし宮城を襲つた。天皇の側近を捕へ、天皇を擁立して目的を果さんとの直接行動に移ったのである。
鈴木総理大臣及び平沼枢府議長らの私邸が焼き払われたのもこの時である。彼らは先づ、天皇の国民に対する放送盤、即ち玉音入りのレコードを探すことに急であった。宮内省は隅々まで捜索されたが、彼らはついに放送盤も、木戸内府その他も手に入れることがでなかった。 一隊はまた中央放途局を占領して、放送を不可能ならしめんとしたが、十五日玉音放送は、彼らの探知しえなかった放途局より放送された。
東京防衛司令官田中大将は、自ら宮城に至り、反乱軍の幹部中堅将校に対して、その暴拳を諭し、声涙ともに下る読得を試みた。叛徒の幹部は、ついにこの上為すことのできないことを悟って、その場で皆自決してしまった。
かくして軍部のクーデターは不成功に終わった。帝都防衛の責任を持つ田中大将は、すべてを見屈けて自刃して果てた。
このクーデターの試みも、昭和の動乱を通ずる軍部の一貫したる動向の現はれであった。
天皇の玉音放送に対しては、全国民は襟を正した。出先の軍隊も、外国もこれを聴収した。識者の間には予期されたことであったが、事情を窺知することができず、玉砕の宣伝のみを聞かされていた大多数の国民には、真に青天の霹靂であった。しかし、いづれも聖断に感激し、陛下の御裁断によつて、初めて、悲惨なる戦争が止んだ、ことを今更の如く感謝したのであった。
しかし、国民の中には、心中諒解しかねたものが少くはなかった。陸軍にも海軍にも、自殺をもって終戦に抗議するものが続出した。大西軍司令部次長等もその例であった。国民中、元寇の乱の神風を信じていた者は、終戦をもつて国辱となし、思ひ詰めた人々が続々と二重橋に集まって、宮城に対してその苦衷を訴へ、中にはその場で悲憤梗概して自殺するものも数多あって、軍内部の事情と相應し、形勢は必ずしも柴観を許さざるものがあった。
右翼思想団体のある純真なる一団は、代々木練兵場の森に集合し、朝日の昇るのを拝しながら、十数名の若者が割腹自殺して抗議した、と報ぜられ、他のまた一団は、暴動化して愛宕山に立て籠ったことが報ぜられた。
◎戦後処理、辞任

こうした混乱を経て、敗戦処理が始まり、重光さん自ら、不自由な義足の右足でミズリー号によじ登り、甲板衛兵の敬礼を受けて、さらに上甲板の降伏文書調印の式場に登っています。(なお、1932年(昭和7年)1月、第一次上海事変が起きた時、重光さんは欧米諸国の協力の下、中国との停戦交渉を行ったのですが、何とか停戦協定をまとめ、あとは調印を残すだけとなった同年4月29日、上海虹口公園での天長節祝賀式典において朝鮮独立運動家・尹奉吉の爆弾攻撃に遭い重傷を負いました(上海天長節爆弾事件)。にも関わらず、激痛の中「停戦を成立させねば国家の前途は取り返しのつかざる羽目に陥る」だろうと語り、事件の7日後の5月5日、右脚切断手術の直前に上海停戦協定の署名を果たしています。今からちょうど88年前のことです)。
日本側の全権団は重光葵外相、梅津美治郎参謀総長らで、これを迎えたマッカーサー元帥は「相互不信や憎悪を超え、自由、寛容、正義を志す世界の出現を期待する」との演説で終戦を宣言しています。
この歴史的な降伏調印後、重光さんは次のように述べています。
東京に引き上げた上、政府に報告し、さらに宮中に参内して、天皇陛下に復命して(経過や結果を報告して)、重大任務を終了した。数千年の歴史はこれで一応閉じて、新日本の歴史がこれから始まることとなった。否、数千年の歴史が、これによって初めて継続して行きうることとなった。いずれにしても、これから新日本が始まることは確かである。しかし、その新日本の建設は、なお昭和日本の革命であるのである。新日本の将来は、全く日本民族の能力と努力の如何に懸かっている。
人々は、「敗戦による勝利である」という意見を吐いた。日本がこれまでのようでは、勝っても前途は駄目である。心を入れ換えて万事新たに出直せば、繁栄もし生き甲斐もある。一旦苦悩の底を経てこそ、初めて立派になり得る、という意味である。記者はこれを否定することはできなかったが、さらに国家の前途を深刻に考えて、悲痛の念を禁ずることができなかった。
昭和の動乱を当事者として見守り、その根本原因を見抜いていた人の目には、へドロのように積もりに積もった原因を除去することは容易ならざることだとわかっていたからです。蒙古来襲の時のように、神風が吹いて、一発逆転、勝ち戦になってほしいと願っていたような国民がまだまだ多数いて、不穏な空気が漂っていたとき、そもそも「降伏」などという文字を使うというだけでも大変でした。
軍人出身の閣僚は、せめて訳文だけでも「休戦」の文字を使いたいと主張していたと記しています。これに対して重光さんは「surrender」という原語は何といっても降伏ということであり、また敗戦の結果、実際降伏することになったのであって、その事実はこれを十分に承認し、徹底的に意識しなければ、日本の再生はできない、偽装的一方的の考え方は、これからはよさねばならぬ、という外務省の強い考え方を押し通しました。
が、マッカーサー司令部との連絡を司るために、外務省が「終戦連絡事務局」という小部局を新設したいと提案したら、時の内閣府から猛反発を受けと記しています。なぜなら、司令部とのやり取りは重要なので、首相直轄の大部局が必要だからだ、と言うのです。
反対した閣僚たちの本心は、大規模な組織を作って、「これに民間大物を割り込ませる」ことにあったのです。昭和の大動乱の根本原因を成した、大小様々の実業家たちの「強欲」に対する「自己批判」のかけらもなかったのです。が、当時の空気では、一国の玄関である外務省の管轄の下に事務を執り行うことが、過去の軍政に対する反省を示すためにも必要であった、ということを理解してくれる人はほとんどなかったのです。一国として「再生」し、道徳的に振る舞うようになることなど、眼中になかったのです。
まるで時代を逆戻りしようとしているかのような内閣の有様を目の当たりにして、重光さんは、占領軍に取り入り、利権拡張の新たな機会にしようと狙っているような、「旧時代」の人物を一掃し、占領軍と協力して円滑に事を進んでやり得る「新人」を登用するよう「進言」しました。
が、この進言は退けられ、結果、重光さんは辞表を提出し、外務大臣の職を辞しました。その後十日ほどして、マッカーサー司令部は、日本政府に、悪名高き特高警察に関係のあった内務大臣以下、全国にわたる警察部長の「即時免職」を指令してきた、そして内閣はとうとう総辞職するに至った、と結んでいます。
◎賢治の『猫の事務所』
この顛末を読んだ時、不意に宮沢賢治の『猫の事務所』が思い出されました。これはご存知かと思いますが、次のような話です。
軽便鉄道の停車場の近くにある猫の第六事務所は猫のための歴史と地理の案内所。そこには大きな黒猫の事務長、一番書記の白猫、二番書記の虎猫、三番書記の三毛猫、そして、四番書記のかま猫(釜猫、竈猫の表記をとる本もある)がいた。かま猫は三人の書記にいじめられながらも、黒猫の支えやかま猫仲間の応援もあり、仕事に励み続ける。しかし、かま猫が風邪をひいて事務所を休んだ日、三匹の書記の讒言により、黒猫までもがかま猫を憎むようになり、かま猫は仕事を取上げられてしまった。その様子を見た獅子は事務所の解散を命じる。語り手の「ぼくは半分獅子に同感です。」という言葉で物語は閉じられる(Wikipedia)。なお、草稿の段階では、ラストは「みんなみんなあはれです。かあいさうです。かあいさう、かあいさう。」となっているそうです。
この最後に登場する「獅子」がマッカーサーを思い出させたのです。敗戦後の内閣は、なんの反省もないまま、また「利権漁り」をしようとしますが、外圧によってあっけなく「総辞職」させられてしまったのです。
それにしても、草稿の段階でのラスト「みんなみんなあはれです。かあいさうです。かあいさう、かあいさう。」には、どんな思いが込められているのでしょう? そう思って、何気なく検索したら、次のようなQ&Aが出ていました。
<クエスチョン>
宮澤賢治の「猫の事務所」の獅子について
最後に、事務所を廃止させる(権力がある?)獅子が登場しますが、この獅子は、猫の事務所にとって、さらには宮澤賢治にとってどのような意味・存在なのでしょうか? 宗教的・歴史的背景などがあるのでしょうか?
<ベストアンサー>
回答者: marbleshit 回答日時:2010/08/19 16:50
宮沢賢治の作品の鑑賞において、決して等閑にできないのが『法華経』です。
浄土真宗の家に生まれながらも、自身は「生命尊厳・万人成仏」を説く法華経の信者へと改宗し、その故の必然としての、精神的・肉体的・社会的葛藤が、全作品に滲み溢れています。
「猫の事務所」は1926年、賢治29歳の作品で、花巻小学校教員を退職した直後の作品です。
四匹のネコの織り成す、コメディータッチの描写は、官僚組織化した学校職員現場の風刺のようでもあり、世事に振り回される、庶民の愚かさのアイロニーかもしれません。
獅子のせりふの、「そんなことで地理も歴史も要った話ではない」というのは、「そのような痴態を演じている者が、学問を膾炙することに何の意義があるか」との示唆であろうと思われます。
『法華経』における『妙法蓮華経』とは、「座して天命を待つ」でも
「極楽浄土」を希求するものでもなく、今自身が在る所の現実社会を、
「常寂光土」へと変革する、ある種の実践哲学ですので、これに背反するかのような、ネコたちの病的な俗物振りへの一喝であろうかと察します。
また法華経の眼目は万人救済ですので、このネコたちに対しても慈悲の眼差しを持つが故に、作者賢治は「半分獅子に同感です」なのだろうと推察します。
◎「人類滅亡の悪夢」
ここで、唐突ながら、ロシア文学者/文芸評論家、高橋誠一郎氏がホームページで公表しておられる「黒澤映画《夢》の構造と小林秀雄の『罪と罰』観」の中にある、『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフが見た「人類滅亡の悪夢」のことに触れさせていただきます。
それは、「知力と意志を授けられた「旋毛虫」におかされ、自分だけが真理を知っていると思いこんだ人々が互いに自分の真理を主張して殺し合いを始め、ついには地球上に数名の者しか残らなかった」という「悪夢」です。なお「旋毛虫(せんもうちゅう)」ですが、これは「線形動物門に属し、主に哺乳動物の筋肉組織中に寄生する寄生虫。ヒトに感染すると旋毛虫症を引き起こす。分類学上は旋毛虫属(Trichinella)をあて、Trichinella spiralisほか少なくとも9種が含まれている」(Wikipedia」ものです。
これは、ラスコーリニコフが取り憑かれてしまった「超人理論」と関連しているような気がします。文芸評論家の浜崎洋介さんはこう述べています。「この小説を読む上で見逃せないのは、故郷喪失者=ラスコーリニコフの近代的孤独です。田舎から人工都市ペテルブルクに出てきた一人の青年知識人であるラスコーリニコフには頼るべきものがない。いや、もし、かろうじて頼れるものがあるのだとしたら、それは彼自身の「意識」しかない。そして、そんな孤独な「意識」が編み出したのが、この世を進歩させる天才には、凡人たちを踏み超える権利があるという「超人理論」でした。彼は、それによって動き、また高利貸しの老婆と、その妹を殺してしまうのでした。」
『昭和の動乱』を読んでいると、動乱の主因であった、第一次大戦後の「軽佻浮薄」な上層部の拝金的風潮、腐敗、儲けた大金を世の中の改善(貧富の差の解消、疲弊した農村の救済など)に向けずに遊蕩三昧にしている有様などを目の当たりにして、「世直し」を図ろうとした、純真な将校たちの思いが浮かんできました。問題は、それを実現するためのしっかりした羅針盤役を果たせる導き手がいなかったことで、そのために、標的の暗殺といった過激な手段に訴え、一部の不満な国民の支持を得たものの、結局自分たちが追求した世直しは「幻想」に終わってしまったのではないでしょうか。もちろん、北一輝の『日本改造法案大綱』などが、「天剣党」(昭和時代初期の青年将校、西田税が北一輝の思想に影響を受けて結成を目論んだ、国家改造主義団体。1929年に西田が「天剣党規約」なる趣意書を起草・配布したが、実際の組織創設には至らなかった)の青年将校や軍の革新計画者の教科書として熱心に読まれはしたが、と重光さんは記しています。
いずれにせよ、ラスコーリニコフが取り憑かれた「超人理論」などの幻想に人間は弱いようです。第一次大戦後の日本でもそうで、色々の「思想」が入り乱れており、それについて重光さんは次のように記しています。
共産勢力に対する反動は・・・ようやく激しくなり、国粋思想は、急に台頭して、左右両翼の思想の暗闘が相当長く続いた。
この思想混乱時代に、よく世界の大勢と文明の潮流に沿って、日本の思想を善導して行く人物は、遂に出現することがなかったのみでなく、条理を尊重する合理主義すらも排斥せられ、一般は唯々混迷のうちに、深慮もなく自省もなく、新奇を追って極端から極端へと走る有様であった。
日本をかくの如く政治上、社会上乃至は思想上の混乱に陥れたのは、全く自由主義の弊害である、と浅薄にも宣伝に乗せられ、これに対する革新が叫ばれるようになった。左翼を攻撃する国粋派は、共産主義と自由主義の見境いができなくなってきた。彼らにとっては、皇室は絶対の存在であり、天皇に対する忠誠は国家の存立上当然のことで、これを議論することすら、全て「危険思想」であり、国民の義務に背くものであった。思想の自由はすでにこの点において危険である、と論ぜられ、自由主義の中道論は排斥せられ、革新は、まず自由主義の排斥から始めなければならぬ、と言われるようになった。
国家の機構を根本から破壊することによって、革命を成就せんとする共産主義運動に対して起こった盲目的反動国粋運動が、結局、同様の手段によって、漸次自由主義的中道論者を圧迫して、政治的訓練なき国民を指導するに至った。
まさに「知力と意志を授けられた「旋毛虫」におかされ、自分だけが真理を知っていると思いこんだ人々が互いに自分の真理を主張して殺し合いを始めた」のです。動乱の時代には、とりわけ「自由」や「民主主義」あるいは「共産主義」を唱える思想家が忌み嫌われ、人々は「デモクラシー」的訓練を十分に積むことができず、「自由主義者」たちは「西洋かぶれ」とされて敬遠/弾圧されていたわけです。
『昭和の動乱』はこうした流れを大局的観点から教えてくれます。様々な「意見」に惑わされず、何が「事実」かを見極め、真偽の識別力を磨き、過去の過ちを二度と再び繰り返さないために役立てていただければ幸いです。
また、『人間の知恵の歴史』復刻版シリーズ①古代篇の刊行に際して、危機の時代に「知恵」がどう働くかを見てみる上での参考とするため、重光さんの親切なガイドによって昭和という時代を見直し、ひいては我が国の現状を理解するためにも、ご笑覧いただければと思います。