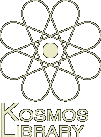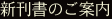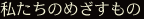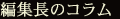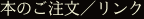第11回
前回ご紹介したメレジコフスキーの『トルストイとドストエーフスキー』の中の屠場の箇所について、会員の横山さんから反論ないし抗議の手紙が届き、それに対して岡野主幹から「『よだかの星』を超えて」という一文が寄せられました。これはサングラハの主宰者としての自然な対応だと思いますし、筆者としては拙文が元でこうしたやりとりがなされ、それが全体としてサングラハ会員の皆様のより建設的な思索の糧になってくれればと願っております。
またこの際最小限の補足をさせていただくとすれば、前回の紹介に際しては、屠場で働いていらっしゃる方々へのいかなる差別の気持も--少なくとも意識的には--働いていなかったということを申し添えております。ただし、自分の心の暗い洞窟を覗いて、自分の内面にはいかなる種類の差別意識も見出せない、と明言することはできません。この差別一般の問題について私たちにできることは、さしあたり私たち一人ひとりが真摯に自問し、自分の内面とを直視し、事実と向き合うことだけではないでしょうか?
前回の紹介はあくまでも小生の読書感想の域を出ておらず、これこれこういう本があって、その中にこういうことが書いてありましたというお知らせにすぎず、それをもって直ちに読者に肉食をやめましょうなどとお説教するといった余計なことをする気持などもうとうありませんですし、また、牛肉を食べないとしても革靴を着用すればやはり牛のお世話になるわけであって、ものごとがそうすっきりいくとは少しも思っておりません。
むしろ、生きることに含まれる「すっきりしなさ」から私たちは目をそらすことはできないし、そこに人間存在というものがかかえているやっかいさや、逆に思索・行動へのバネのようなものが感じられるということを、自戒の念を込めて指摘したかったのです。例えば、ご存じのように、インドでは牛を殺すことは憲法で禁じられており、さすがのマクドナルドもそれを破ることはできないわけですし、また、別に牛肉を食べなくてもインド人は元気に増え続けています。前回ご紹介したように、もし人類が進化すれば肉食および動物の残酷な殺戮を辞退するようになるだろうとメレジコフスキーが予言していますが、その点では少なくとも総体としてインド人は肉を食する人々より進化していることになり、インド憲法は動物との関わりについてのある画期的な答えを与えていると思います。が、その同じインドに、非差別民の元型たる不可触賤民が依然として多数暮らしています。屠殺場をなくしても、依然差別はあり続け、社会制度の中に組み込まれているのです。
にもかかわらず、牛の屠殺を禁止しているインド憲法の精神の由来をはるかに辿って行くと、前回ご紹介した「生ける動物に対するこの際限無きアリアン族の憐憫より、仏教は生じた。しかしてそれは堰を破る洪水のごとく、かつて世に存した文化的建物のうち最も強く最も頑固なものを破壊した。すなわち神と動物との隔りよりも一層ひどくバラモン族とパリア族とを容赦なく隔離せるインドの階級を打破したのである」というメレジコフスキーの指摘中にあるような仏教の誕生に突き当たるのです。人類が総体として依然として持ち続けている暴力性・残忍性というものを考える時、今から二千年以上前にインド人の祖先たちの多くが、動物だけでなく同胞に対しても抱いた慈悲心が仏教として結実したという事実は、少なくとも筆者にはとても感動的なことに思えるのです。
メレジコフスキーはこうした事柄に関連して、次のような古いインドの伝説を紹介しています。
ある時悪魔が世界の救主なる仏陀を試みようとして、禿鷹に扮して鳩を逐った。鳩は仏陀の懐に逃れ、仏陀はこれを庇護しようとした。すると禿鷹の曰く、「汝はいかなる権利があってわが獲物を横取りしたか。鳩が自分の爪牙にかかるか、但しは自分が餓死するか、とにかく吾々の一つは死なねばならぬ。汝は何故に鳩にのみ同情して私に同情せぬのか。もしも汝が慈悲深くて吾々二羽のいずれをも殺したくないと思うならば、わがために汝自身の肉体より鳩と同じ量の肉片を切り取れ。」 そこで二枚の皿のついた一つの天秤が持ち出された。そして鳩は一方の秤盤に下りた。仏陀はその体から一片の肉を切り取って、他方の秤盤の上に置いた。けれども秤盤は動かなかった。彼は更に一片を投じた。更に更に一片ずつ投じた。ついに血がだらだらと流れ出し骨も露になるまでその体全体を切り取った。けれども秤盤は依然として動かなかった。そこで最後の力を奮い起こしてその秤盤に近づいて、彼はその中に身を投げ入れた。その時秤盤は下がって、鳩の方が上った。
これを読んだ時、思わずあの有名な苦行中の仏陀座像--骨と皮ばかりで、肋骨の浮き出た--を思い出しました。その時仏陀の内面では、右に描かれたような人間としてなしうるギリギリの思索がおこなわれていたのでしょうか。これは仏教の教えというよりはむしろジャイナ教の教えそのものであり、『よだかの星』のよだかの考えたことの源流のように思われますし、また『死霊』の著者、故埴谷雄高がジャイナ教をその思想の中核に据えていたことはよく知られています。
☆ ☆ ☆
それにしてもなぜ人間は二千年以上昔からこうした問題に悩まなければならかなったのでしょう? この問いに迫るため、ここで改めて「魂」というものに注目してみたいと思います。エルキンスとは別の視点から魂の問題に迫った
『魂のプロセス--自己実現と自己超越を結ぶもの』(コスモス・ライブラリー 1999年)の著者ヴィーダマンは、地上における魂の運命について様々な示唆を与えてくれます。彼は魂についての諸説を紹介する中で、次のように述べています。「……魂があらゆる種類の危険をはらんでいる点をも理解する必要がある。たとえば、多くの伝統的な思想家たちはこう信じていたようだ。魂がその幸福なる神との一体感を捨て去る選択をするのは、この闘争に満ちた、戦争によって傷ついた惑星上に人間の肉体を持って現れるためである。このような決心は、素晴らしいが故の危険性をはらんでいる。危険にさらされることこそ、何が魂を満足させるのかを立証する唯一の方法だとホルトは断言する」。なお、ホルトは『ユング心理学と魂の癒し』という本の著者です。
右の一文を読んだだけでも、魂というものがいかに厄介な代物かおわかりになると思います。しかも、地上に降りてきて受肉した時にはすでに「幸福なる神との一体感を捨て去る選択」をしたことなど忘れているのです。その上、地上のどの国のどの階級や集団や家族に生まれるかを自分で選ぶことはできないのです。ですから、もしインドの不可触賤民の子として生まれれば、恐らく一生理不尽な差別に苦しみ続けるといった不幸を味わったり、あるいは生まれて間もなく餓死するといった悲惨な目に合わなければならない場合もあるのです。
ヴィーダマンによれば、もっとも一般的には「魂とは、さまざまな形で隠れたり現れたりしながらも、一生を通じて私たちの中に留まり続ける神性の中核、断片、または本質を意味する。」 他に、「もの」ではなく「プロセス」として魂を理解する方法もあるのですが、いずれにせよ、魂は肉体を持たなければならず、その途端に身体の持つ制限に服従し、一生涯を通じて日々の現実の領域留まらなければならないのです。
「トランスパーソナル学研究・第4号」中の「魂と超越「存在」」という評論の中で、著者の宇都宮隆史氏は次のように述べています。「穏やかで、平凡な人間にあっては、自我と魂は好ましい形で融合しており、外から二者の区別など判別できないし、当の本人もそれを自覚できないのが普通である。しかし、そんな一見健康な人間、つまり魂と自我が対立するようなことがない人間も、一生の間に一度くらいは魂が暴れだして、自分でも大いに当惑するのである。魂はあたかも、この世で何らかの使命や役割を果たすべく、人間の肉体に宿った感がある。しかし、普通魂は自我と融合し、そこに安らっている。しかし、自我はきわめてこの世的知恵で自分を律しているから、魂と折り合いがつかなくなるときもある。」
つまり、私たちが現実生活において順境にある(あるいは、そう思っている)ときは魂は発現しにくく、逆に、逆境にあり、日常的現実・この世での生活に「違和感」を持ち、生きることに苦痛を感じ、苦悩するとき、それは魂が発現していることの徴候だということです。極端な場合には、プラトンのように「死による身体からの解放を切に待ち受ける他者」として魂を捉える方向も出てくるわけです。危険にさらされることを覚悟でこの世での生を選んだはずなのに、いざ肉体をまとってこの世で暮らすと切にそこから解放されたいと願うのですから、魂とは実に逆説に満ちた存在だと言えます。
ヴィーダマンによれば、かつては純粋な聖霊であった魂が「人間」となるとき、遺伝的・環境的要素、家族の期待、文化的・社会的なすりこみ、教育など様々な「かせ」によって、覆われ、トランスパーソナル学者たちの言う「人間のメロドラマ」に巻き込まれ、あっけなく本来の使命は失われれ、自分の目的を表現し、実現するようなキャリアを築くべく努力するよりも、親の遺産で暮らすといった安楽な人生を選ぶようになるのです。
そこで魂がその受肉の本来の目的である「神との同一性」としての真のアイデンティティの回復をめざすためには、「悪いカルマ」を積まないようにし、「良いカルマ」を積むことが実践的な道となるのです。私たちはそれぞれの立場に立ちつつ、この道を具体化することができるでしょう。例えば、無益な殺生をしないこと、児童や動物を虐待したり、ペットを捨てたりしないこと、特定の集団や職業に就いている人々に理不尽な差別意識を持たないこと、などなど。
ですから、魂とカルマという観点から見れば、横山さんが言うように、もし筆者の前回の記事が差別問題に対して無神経だったとすれば、そうした悪いカルマの見返りとしての有害な影響を被る(自分でまいた種を収穫する)のはむしろ筆者であって、屠場で日々勤労にいそしんでおられる方々ではないのです。この点をくれぐれも御理解いただきたいと思います。