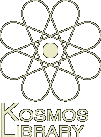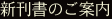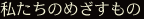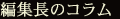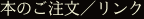第25回 クリシュナムルティと第三の道
その季刊誌は『ひとりから:対等なまなざしの世界をめざして』という名のものです。弁護士の金住典子さんと原田奈翁雄さんのお二人が編集・刊行してきたもので、その最新号の39号(2008年9月15日発行)に、拙文が記載されました。
原田さんについては、『お聞きください,陛下』(径書房)というご著書中で次のように紹介されています。
●紹介
陛下よ、あなたは「神様」だったのです。動かぬ事実で天皇の戦争責任を問いかける。戦争の負債(おいめ)を誰が継ぐのか。
●著者プロフィール
原田奈翁雄。1927年東京生まれ。1952年明治大学卒業、筑摩書房に入社。
「展望」編集長などを務めるが、1978年倒産に伴い退社。1980年径書房を創業。1993年代表を退き、相談役に。
著書に『本のひらく径』(エディタースクール出版部)、『どう生きる、日本人』(東方出版)
また、径書房(こみちしょぼう)についてはWikipedia で次のように紹介されています。
筑摩書房で、『展望』『終末から』などの編集長などを務めた、原田奈翁雄が、1980年創業。
1988年に人種差別に関わるとして一斉に絶版となった絵本『ちびくろサンボ』について、問題提起をした書『『ちびくろサンボ』絶版を考える』を1988年に刊行し、1999年にはヘレン・バナーマンによる原作の翻訳書を刊行した。
つまり、かつて『展望』の編集長をお務めになった、出版界では有名な方です。その後立ち上げた、径書房の出版物のなかでも『長崎市長への七三〇〇通の手紙』は、増刷も間に合わぬほどとてもよく読まれたようです。
また、金住典子(かなずみふみこ)さんには以下の著書があります。
『鬼に勝つ――「わたし」を自由に生きるために』(三一書房、1998年)
対等なまなざしや人間関係が阻まれる社会を「鬼」と呼ぼう。自分自身にも刷り込まれた非対等なまなざしを誠実に凝視しつづけてきた一女性弁護士が語る「鬼に勝つ」ための模索の旅。
『女性のための法律教室――いざという時、誰があなたを助けるか』(PHP研究所、1982年)
このお二人で出し続けてこられたのが『ひとりから』なのです。その印象的な赤い表紙には「貝寄せの風。ひとり浜に立っている。ひとりになれないものは二人にもなれないそうな」という言葉が掲げられています。そして最近の御関心は「憲法九条改悪阻止」に向けた署名活動にあるようです。
いわば歴戦の勇士でるあるお二人が熱い思いで出し続けてこられた季刊誌に、クリシュナムルティの紹介をすることになったわけで、いささか躊躇しましたが、結果的には拙文をとても喜んでくださいましたので、ほっとしております。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
インドに生まれたクリシュナムルティは、かつて一宗教教団に「世界教師」と仰がれ、組織の力も財力も十分に持つ救世者であった。その指導者が、みずからその教団を解散して、おのれの地位も投げ捨てた。「いかなる人間も、外側から諸君を自由にすることはできない。組織化された崇拝も、大義への献身も諸君を自由にはしない……鍵は諸君自身の自己なのだ。その自己の開発と浄化の中に、その自己の不滅性の中に、その中にのみ〈永遠の王国〉は存在する……私の関心はただひとつ、それは人々を、完全に、かつ無条件に自由たらしめること」(星の教団解散宣言。大野純一訳)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
大野純一
このたび知人の篠原英雄氏を通じて、『ひとりから』への寄稿を金住さんから依頼されました。大変光栄なことなのですが、なにぶんこの雑誌の読者の皆様はクリシュナムルティのことをご存知ないと思いますので、本題に入る前に、先ず読者の皆様とある程度関心を共にできればと思います。
そもそも人間には、周知のように「外側に向かう傾向」(外向性)と「内側に向かう傾向」(内向性)があり、両者が混在しているというのが実情だと思います。わが国でも、社会変革などいわば西洋型の外向的活動に携わってきた人々のなかに瞑想に関心を向けつつある人々が出てきている一方、伝統的な修行に飽き足らず、環境問題などへの関わりを通じて、自己変革と並行させつつ外部的変化をもたらそうとする人々が出てきており、徐々にではありますが内向きの動きと外向きの動きが相補的な形で進行しているようです。
例えば、吉田敦彦氏は、その著『ホリスティック教育論――日本の動向と思想の地平』 (日本評論社 一九九九)中で、「神秘主義的宗教思想」の系譜に位置づけられる教育者としてユング、シュタイナー、ガンジー、ケン・ウィルバーらと並んでクリシュナムルティを含めているだけでなく、「地球市民教育」に関連した「外(社会)と内(自己)の同時変容」について、次のように述べています。
「内面性」が他の歴史的問題や地球的問題に結びつけられているもう一つの意義は、自己自身の問題を棚上げにして外なる問題の解決はできないこと、あるいは逆に、現に直面している社会問題の一つにきちんと向き合うことなく、心の内面だけで解決はできないという点にある。それをセルビー氏は、「外へ向かう旅は、内へ向かう旅である。同様に、内へ向かう旅は外へ向かう旅である」と表現している。現代の社会の問題は、私たち一人ひとりの内面が抱える問題の反映であり、同時にまた、私たちの内面の問題は、私たちの外なる社会の問題の反映でもある。どちらが先かではなく、内と外、社会性と内面性は分かち難く結びついていて、その両方が噛み合いながら変化が生じる。これは「ホリスティックな変化」と呼ばれるが、ホリスティックな地球市民教育は、従来の社会変革運動が外向的にすぎる傾向があったのに対し、自己自身の変容や深まりといった内向性と結びつけて、「自己が変わり、世界が変わる。世界が変わり、自己が変わる」という相互関係をたいせつにする。
これからご紹介するJ・クリシュナムルティ(一八九五〜一九八六)もまたその九十年にわたる生涯を通じて数多くの本を著し、講話(トーク)をおこない、それらの中で個人と社会・世界の問題を探究し、人間を真に自由な、歓喜に満ちた生へと誘うべく手を貸し続けました。その彼の思想・教えについて述べる前に、ごく簡単に彼の足跡をご紹介します。
反逆者としてのクリシュナムルティの生涯
ジッドゥー・クリシュナムルティは、一八九五年、南インドのマドラス(現在はチェンナイ)近辺の小さな丘の町に生まれました。ジッドゥー家はバラモン階級で、曾祖父も祖父も有名な学者でした。八番目の子供として生まれた彼は、ヒンドゥー教の伝統に従って、クリシュナ神(第八子とされている)にちなんで、クリシュナムルティと命名されました。父のナリアニアは、マドラス大学を卒業後、英国行政下で徴税局の官吏をしていました。彼はタシルダール(地代徴集官)で、地方長官の地位にまで上っており、比較的恵まれた生活をしていました。が、一九〇七年に五十二歳で退官後は、年金だけで大勢の子供(次々に死んでいきましたが)を養わねばならず、楽ではなくなりました。そこで、神智学協会員であった彼は、会長のベサント夫人に奉職を願い出ました。条件として彼は子供も一緒に協会の構内に移り住むことを求めたため、ベサント会長は彼の願いを受付ないでいたのですが、運よくアシスタントの職が欠員となり、就職することができました。これが、クリシュナムルティと神智学協会との運命的な結びつきの始まりとなったのです。
近代インドの宗教運動を網羅的にまとめた『現代インドの宗教運動』(ファルカール著、一九二九年)によれば、神智学とは「最初ブラヴァツキー夫人によって教示され、後に夫人ならびにオルコット大佐によって一八七五年にニューヨークで創設された協会に盛り込まれた、宗教、科学および実生活の一体系であり、近年ベサント夫人とリードビーター氏によって一層の進展を見せたもの」です。神智学は、さまざまな宗教の創始者や哲学の教師たちによって教えられてきた究極的真理を包摂したものであり、チベットあたりの山岳地帯に住んでいるといわれる数人のマスター(大師)またはマハトマ(大聖人)によって新たにブラヴァツキー夫人に開示された、とされています。
そして神智学協会は次の目的のために結成されました。(一)人種、信条、性、カーストまたは皮膚の色の区別を超えた、人類の普遍的大連帯の中核となること。(二)比較宗教、哲学および科学研究の推進・奨励。(三)自然に関する未解明の諸法即則および人間の潜在諸能力の調査・研究。
クリシュナムルティとの関係でこの協会が問題になる時期は、ベサント夫人とリードビーターによって指導されていた一九〇七年から三三年にかけてです。そして神智学によれば、ロード・マイトレーヤ、「世界教師」は、これまで二度、濁世に新しい教えを授けるために化身し、その最初の方は紀元前四世紀のシュリー・クリシュナであり、然る後にイエスとしてそのお姿を現わしたのです。さらにこの世界教師は間もなく、再度人間の形を借りて下界にそのお姿を現わすはずである、とされていました。そしてその降臨に際して、その「乗り物」(器)として選ばれたのがクリシュナムルティだったのです。一九〇九年、彼が十四歳の時のことでした。そしてその世界教師が現われた時に、彼を迎え入れ、その指導を仰ぐために作られたのが「星の教団」で、一九一一年、クリシュナムルティを長とし、ベサント夫人とリードビーターを保護者として発足しました。
クリシュナムルティ少年は、この教団の指導者として働くための素養を身につけるべく、弟のニティヤとともにヨーロッパに留学することになり、以後十年余りヨーロッパで過ごすことになりました。重要なことは、この時期にクリシュナムルティが鋭い観察力と強烈な懐疑・反逆・自立精神を養ったことです。後に、インドからカリフォルニアへとさらに旅した彼は、それまでの自分の歩みをまとめ、一九二八年に『探求』と題する講話の中で披露しています。その中で、彼は次のように述べています。
少年の頃から、多くの若者がそうであり、そうあるべきであるように、私は反抗してきた。何ものも私を満足させなかった。私は傾聴し、観察し、単なる空言を超えた何か……を求めた。私は自分自身で目標を発見し、確立したかった。私は誰にも頼ろうとは思わなかった。……
初めてヨーロッパに行った時、私は、裕福で、教養豊かで、社会的に権威ある地位を持つ人々の間で暮らしたが、しかし彼らは私を満足させなかった。私はまた、神智学徒とそのあらゆる専門用語、理論、集会、そして人生についての彼らの説明にも反抗した。集会に行くと、講師たちは同じ観念や考えを繰り返すだけで、それは私を満足させることも、また幸福にすることもなかった。私はますます集会から遠ざかるようになり、神智学の観念を繰り返すだけの人々にはますます会わなくなった。私はあらゆることに疑義を呈した。自分自身で見出したかったからである。私は通りを歩きながら、人々の顔を観察し……劇場にも行った。そして人々が自分の不幸を忘れようとしていかに娯楽を求めるか、浅薄な興奮で心を麻痺させることによって問題を解決しつつあると思っているかを見た。また私は、政治的、社会的、宗教的な権力を持ちながら、にもかかわらず人生において唯一不可欠なものである幸福を得ていない人々にも会った。
私は労働者の集会や共産主義者の集会にも参加し、彼らの指導者の発言に耳を傾けた。彼らは総じて何かに抗議していた。私は興味をおぼえたが、しかし彼らは私を満足させなかった。ある類型から別のそれへと観察を重ねることによって、私は様々な経験を蓄えた。あらゆる人の中に、不幸と不満の火山が潜んでいた。
初めてヨーロッパに行った時、私は、裕福で、教養豊かで、社会的に権威ある地位を持つ人々の間で暮らしたが、しかし彼らは私を満足させなかった。私はまた、神智学徒とそのあらゆる専門用語、理論、集会、そして人生についての彼らの説明にも反抗した。集会に行くと、講師たちは同じ観念や考えを繰り返すだけで、それは私を満足させることも、また幸福にすることもなかった。私はますます集会から遠ざかるようになり、神智学の観念を繰り返すだけの人々にはますます会わなくなった。私はあらゆることに疑義を呈した。自分自身で見出したかったからである。私は通りを歩きながら、人々の顔を観察し……劇場にも行った。そして人々が自分の不幸を忘れようとしていかに娯楽を求めるか、浅薄な興奮で心を麻痺させることによって問題を解決しつつあると思っているかを見た。また私は、政治的、社会的、宗教的な権力を持ちながら、にもかかわらず人生において唯一不可欠なものである幸福を得ていない人々にも会った。
私は労働者の集会や共産主義者の集会にも参加し、彼らの指導者の発言に耳を傾けた。彼らは総じて何かに抗議していた。私は興味をおぼえたが、しかし彼らは私を満足させなかった。ある類型から別のそれへと観察を重ねることによって、私は様々な経験を蓄えた。あらゆる人の中に、不幸と不満の火山が潜んでいた。
彼はさらに若者たちの娯楽、放縦を見守り、また貧民街で人助けをしたがっている人々を見ましたが、「しかし、彼ら自身が無力であった」と述べています。このようにして彼は自分自身の目で人生を観察しつつ、ヨーロッパからインドへと旅し、さらにカリフォルニアへと渡りました。そこで彼は、病気の弟の看病をしながら、真理を探求し続けました。やがて、看病のかいもなく、彼の補佐役を務めてくれるはずだった弟が死んでしまいます。幼くして母親に死なれ、やがて父親から引き離され、さらに一九二五年、三十歳の時、最愛の弟を失って、彼は大いなる悲しみを味わいました。それから少し経ってから、彼は次のように自分の心境を打ち明けています。
われわれ二人の兄弟のこの世での楽しい夢は終わった。一緒におり、お互いにしていることを見つめ合い、一緒に旅し、話し合い、冗談を言い合い、そして清々しい、愉快な人生のためになるすべての細々したことについての夢は終わったのだ。
……二人にとって沈黙は特別な喜びであった。その時二人はお互いの考えや気持ちを容易に理解できたからである。たまに苛立つことはもとよりあったが、それはほんの数分も経てば消え去り、二人はまた仲良く流行歌を口ずさんだり、詠唱に時を忘れたりしたものである。われわれは二人とも同じ雲、同じ木そして同じ音楽が好きだった。気質は違っていたが、人生を愛する点では同じだった。われわれはなぜか難なくお互いに理解し合うことができた。……幸福な生活だった。が、私はこれから死ぬまでこの世で弟に会うことはないのだ。
古い夢は過ぎ去り、新しい夢が芽生えつつある。固い大地を突き抜けて一本の草花が顔を出すように、新たな視界が開け、新たな意識が生まれつつある。
……苦悩から生まれた新たな力が血管を脈打ち、過去の苦しみから新たな共感と理解が生まれつつある。他の人々の苦しみを軽くし、たとえ苦しむとしても彼らがそれに気高く耐え、あまりにも多くの傷跡を残さずにそれを抜け出してほしいと、より一層願うようになった。私は泣いたが、他の人々が泣くことを望まない。しかしもしも彼らが泣くなら、それが何を意味するか今の私にはわかる。
肉体的には引き裂かれはしたが、しかしわれわれはけっして別々ではない。われわれは一つになったのである。クリシュナムルティとして、私はこれまで以上の熱情と、信念、そしてこれまで以上の共感と愛を具有するに至った。なぜなら、私の中には今やニティヤナンダの身体、存在も溶け込んだからである。……私は依然として泣くことを知っているが、しかしそれは人間的なことである。今や私は、これまで以上の確信をもって、外部のいかなる出来事によっても壊されえない真実なる生の美、真の幸福、束の間の出来事によってけっして弱められることのない偉大なる力、そして永遠にして不壊であり、何ものにも屈することなき大いなる愛があることをはっきりと感ずる。
古い夢は過ぎ去り、新しい夢が芽生えつつある。固い大地を突き抜けて一本の草花が顔を出すように、新たな視界が開け、新たな意識が生まれつつある。
……苦悩から生まれた新たな力が血管を脈打ち、過去の苦しみから新たな共感と理解が生まれつつある。他の人々の苦しみを軽くし、たとえ苦しむとしても彼らがそれに気高く耐え、あまりにも多くの傷跡を残さずにそれを抜け出してほしいと、より一層願うようになった。私は泣いたが、他の人々が泣くことを望まない。しかしもしも彼らが泣くなら、それが何を意味するか今の私にはわかる。
肉体的には引き裂かれはしたが、しかしわれわれはけっして別々ではない。われわれは一つになったのである。クリシュナムルティとして、私はこれまで以上の熱情と、信念、そしてこれまで以上の共感と愛を具有するに至った。なぜなら、私の中には今やニティヤナンダの身体、存在も溶け込んだからである。……私は依然として泣くことを知っているが、しかしそれは人間的なことである。今や私は、これまで以上の確信をもって、外部のいかなる出来事によっても壊されえない真実なる生の美、真の幸福、束の間の出来事によってけっして弱められることのない偉大なる力、そして永遠にして不壊であり、何ものにも屈することなき大いなる愛があることをはっきりと感ずる。
こうして苦悩を乗り越えた彼は、「生の源泉」から溢れ出る清水を飲むことを欲して、なおも探求を続けました。そして自分と目標との間に横たわるあらゆる障害物の打破に着手し、自分が蓄積してきた不要物を放棄し、自分を束縛しているあらゆるものから自分自身を解放させることによって、ついに真理を見出し、「本然の生」を実現し、「解放の海」に入ったのです。こうして彼は、星の教団の団員たちに次のように訴えかけています。
真理に至るために、いかなる組織、いかなる宗教にも加わる必要はない。なぜならそれらは束縛し、制約し、諸君を特定の崇拝対象や信念へと拘束するからである。もし諸君が自由を切望するのなら、私がしたように、あらゆる種類の権威と闘わなければならない。……諸君の精神あるいは心をいかなるもの、いかなる人によっても束縛させてはならない。もし束縛させれば、諸君は別の宗教、別の寺院を作り上げてしまうだろう。私はあらゆる伝統の束縛、あらゆる崇拝の偏狭、心を腐敗させるあらゆる追従に対して闘っている。もし諸君が自由……を見出したければ、諸君はまず不満の炎を燃やし、反抗し、周囲のあらゆるものに内面で反抗することから始めなければならない……
諸君はしばしば「私は指導者に従う」という言い方をする。が、誰がその指導者なのだろう? 私はけっして指導者ではありたくない。けっして権威を持とうとは思わない。私は、諸君が諸君自身の指導者になることを望む。 生は単純にして荘厳であり、麗しく、神聖なものだ。が、諸君は夜明けや静かな夜のあらゆる美しさを、自分たちが崇拝できるように狭い円の中に閉じ込めようとする。夕暮れに浜辺に降りてみると、さわやかなそよ風が吹き、草の葉という葉がそよいでいる。砂粒が舞い、木々の梢が揺れ、そして波と波がぶつかりあっている。が、諸君はそれらすべての美を狭い寺院の中に閉じ込めようと願うのだ。気高く生きるには、いかなる信念も不要である。にもかかわらず、諸君は言う。「私は神々を崇拝しなければならない。寺院に参詣しなければならない。これに従い、それをしなければならない。」永劫の「ねばならない」である! そのような生き方は少しも生とは言えないのだ。
私のまわりに寺院を建立することだけはやめてほしい。私はその中に閉じ込められることはないだろう。私は諸君にとって、さわやかなそよ風のような友でありたいと思う。私は諸君を諸々の制約から自由にし、かくして諸君自身の内部の創造性、独自性を鼓舞したいのだ。
諸君はしばしば「私は指導者に従う」という言い方をする。が、誰がその指導者なのだろう? 私はけっして指導者ではありたくない。けっして権威を持とうとは思わない。私は、諸君が諸君自身の指導者になることを望む。 生は単純にして荘厳であり、麗しく、神聖なものだ。が、諸君は夜明けや静かな夜のあらゆる美しさを、自分たちが崇拝できるように狭い円の中に閉じ込めようとする。夕暮れに浜辺に降りてみると、さわやかなそよ風が吹き、草の葉という葉がそよいでいる。砂粒が舞い、木々の梢が揺れ、そして波と波がぶつかりあっている。が、諸君はそれらすべての美を狭い寺院の中に閉じ込めようと願うのだ。気高く生きるには、いかなる信念も不要である。にもかかわらず、諸君は言う。「私は神々を崇拝しなければならない。寺院に参詣しなければならない。これに従い、それをしなければならない。」永劫の「ねばならない」である! そのような生き方は少しも生とは言えないのだ。
私のまわりに寺院を建立することだけはやめてほしい。私はその中に閉じ込められることはないだろう。私は諸君にとって、さわやかなそよ風のような友でありたいと思う。私は諸君を諸々の制約から自由にし、かくして諸君自身の内部の創造性、独自性を鼓舞したいのだ。
この『探求』が重要なのは、その中で述べられていることの多くが、その後のクリシュナムルティの生き方のほぼ一貫した支柱になっているからです。すなわち、指導者、権威に依存せず、自分自身の偏らない目でものごとを観察し、それによって気づき、理解したことを、その「ありのままに」伝えるという姿勢、真理と自分との間にいかなる仲介もはさませないこと、真理の発見にとって不要なすべてのもの(形骸化した伝統、組織、権威、形式、儀式、寺院、導師、等々)を一掃し、懐疑を傾けて虚偽を否定すること、等々。
当時の神智学協会や星の教団のメンバーは、指導者のベサント夫人、リードビーターの指導に従い、経典(創始者のブラヴァツキーが書いた大著『シークレット・ドクトリン』など)を読み、学ぶことによって「弟子道」を歩んでいたのです。これに対してクリシュナムルティは、真理をめざして山頂へと登るには「軽装」でなければならない、したがってそうした経典も脇に置かねばならないと訴えたのですが、これは容易には聞き入れられませんでした。なぜなら、それは彼らのそれまでの生き方を根底から覆すことを意味したからです。
そして彼の言うことをほとんど誰も聞き入れないことがわかった時、彼は一九二九年、三十四歳の時星の教団を解散したのです。その「解散宣言」の中で、彼はおおよそ次のように述べています。真理は、そこに至るいかなる道も持たない土地である。真理は組織化されえない。それゆえ、ある特定の道をたどるように人々を指導し、あるいは強制するようないかなる組織も結成されるべきではない。真理探求の目的で組織を創立するなら、組織は松葉杖となり、束縛となって、人を不具にし、真理探求に必要な個々人の独自性の成長をかえって阻害してしまう。真理到達のための唯一の方法があるとすれば、それは仲介者を通すことなく、真理それ自体の使徒となることである。霊的成長にはいかなる儀式も不要である。真理はわれわれ一人ひとりの中にある。「生」そのものを目標とし、ガイド、大師、そして神とすることの方が、仲介者や導師(グル)の助けを借りるよりもはるかに簡単なことだ。真理が与えるのは、希望ではなくて「理解」である。理解する人間でありさえすれば、彼の進化段階のいかんを問わず、解放は可能である。
実は、この解散宣言の冒頭でクリシュナムルティは、スーフィーの小話を出しています。
ある人が道を歩いていると、その後を二人の見知らぬ男がついて行きました。しばらく歩いて行くと、彼は何かとてもきらきらと輝くものを見つけ、それを拾い上げ、じっと見つめてからポケットに入れました。後の二人はその様子を観察し、そのうちの一人が相手に言いました。「これはひどくやっかいなことになりましたな。」すると相手――実は悪魔――はこう答えました。「なるほど、彼が拾ったのは真理だ。しかし私は、彼がそれを組織化するのを手助けするつもりだ。」
もし真理というものが生きたものであれば、それを固定したり、組織化したりすることは、そもそも無理な話です。そよ風を瓶の中に閉じ込めるようなものだからです。そしていったん組織が作られるやいなや、真理そのものよりも組織の維持や拡大の方が重要になってしまい、本末転倒になってしまいます。やがて組織が大きくなるにつれて、内部の階級化、権威化が進み、上下関係ができあがり、対外的にはプロパガンダが必要になり、他のいかなる組織よりも優れていることが強調されます。こうしてさらに組織が大きくなるにつれて、真理とは無関係の怪しげな人間たち――票田めあての政治家など――が群がって来るのです。かくして宗教と政治は、双児の狩人として、現代人の「虚しい心」を格好の狩り場として信者を集め、巨大な利権組織を築き上げていくのです。
そしていったんある教団やカルトが彼らの「真理」を標榜するとどうなるかは、オウム真理教が如実に示しました。まさに真理は「気違いに刃物」と化し、信者たちは「マインド・コントロール」の対象とされたのです。指導者たちは、一般社会でと同様、信者たちを「徹底的に条件づける」ことに邁進したのです。ちょうど、原田さんが告発された第二次大戦中のわが国における徹底した天皇崇拝教育のように。そのような場所には真理の余地などあるはずがないのです。ついでながら、クリシュナムルティは真理と美は不可分だと言っています。そして彼は終生、美意識を養うことがいかに重要かを強調し続けました。
オウム事件のあった当時、筆者は、あの富士の裾野に立っている巨大な棺桶のような、美意識のかけらも感じられない建物、信者たちの内面を象徴するような、外界から遮断され、美しい自然に背を向けている建物を見て、はからずもイタリアの作家アルベルト・モラビアがその『私の中国観』の中で言及している次の史実を思い出さざるをえませんでした。「それは第五回十字軍、俗にいう少年十字軍のことである。一二一二年に、ステファーノという名の十二歳になる狂信的な牧童が、キリストに召されたという文面の手紙をたずさえ、ヨーロッパ各地から何千という少年少女を呼び集めることに成功した。彼は断言する。自分たちが海についたとき、ユダヤ難民の行く手で紅海が開かれたように、海は開き、自分たちは足を濡らさずにイエルサレムについて、聖地を解放させるであろう、と。しかしマルシリアに着いても、海は開かなかった。その代りに、怪しげな商船の船倉が開いて、子供たちを乗せ、聖地にではなくアルジェリアに連れていった。そしてそこで一人残らず奴隷として売りさばかれたのである。」
モラビアがこれに言及したのは、毛沢東全盛時代の中国で、彼を完全に信頼し、いわば「徹底した宗教心が、無知で狂信的な少年少女を明日にも北ベトナムの戦闘や北朝鮮の戦線に送り込まないとはかぎらない」状況を示すためでした。筆者の目には、あのオウムの建物――様々な理由で現代社会に背を向け、あるいは超能力の獲得をめざし、あるいは解脱や悟りを開くために出家して修行に励むために若者が入っていったあの建物――が、まさに少年十字軍を運んでいった怪しげな商船と映ったのです。事実、もっともらしいサンスクリット語まがいの称号を持ち、異例の早さで出世していった、幹部と目される一握りの若者(+若干の中年男女)以外は、修行の名の下に様々な労働に従事させられていたわけです。
ルネ・フェレというフランス人の研究家は、『クリシュナムルティ――人と教え』の中で、星の教団解散直前のクリシュナムルティについて次のように述べています。
歴史上、少なからぬ人間が、クリシュナムルティが現在直面している選択に迫られた――彼のメッセージを純粋なままに保ち、信奉者の大部分を失うか、それとも彼の教えを引き下げて、凡俗のレベルに適合させ、それによって彼の信者の数を増やすかという。躊躇なく、彼は困難な道を選び、そしてすばらしい宣言でもって星の教団を解散してしまうのである。
神智学協会も星の教団も、主に良家の子女をメンバーとし、解散当時、星の教団は世界四十ヵ国に四万人余りのメンバーを持つ国際的宗教団体に育っており(ちなみに、わが国では今日出海さんのお父さんが唯一の会員でした)、しかもきわめて裕福な団体でした。しかしクリシュナムルティは、富と権力の強い誘惑に少しもたじろがなかっただけでなく、救世主として享受すべき一切のものを放棄して、より広い世界へと出てったのです。
彼は、自分はグルではないと言います。「私は皆さんに何か大事なことを指摘しているつもりですが、しかしそれを受け入れるかどうかは皆さんの自由です。なぜなら、指摘されたものを取り上げて、それを自分のために役立てるかどうかは、皆さん一人ひとりの仕事だからです。」そして彼は言います。「個々の人間にこそ希望があるのです。社会にも、諸々のシステムにも、組織化された宗教にも希望はありません。希望は、皆さんの中、そして私の中にあるのです。」
彼はまた、生とは関係だと言います。妻、子供、隣人との。そして動物、植物、大地、海、川との。そして関係は、その中に自分自身を見出すための鏡だと。ですから日常生活の中で自分を観察し、自分の言動を見守り、それにありのままに気づくことが重要なのです。いわば日常生活を道場にして、観察・洞察・理解力を磨く必要があるというのです。するといやおうなしに、自分の内部の混乱、悲嘆、貪欲、野心、競争心、葛藤などが白日の下にさらけ出されるでしょう。しかし、いやでもそれらから目をそむけないこと。それがまさにクリシュナムルティが言う意味での「修行」だと言えるでしょう。そこで、この意味での修行の参考になりそうなクリシュナムルティ自身の言葉を引用しながら、彼の教えの一端に触れてみたいと思います。
個人と社会・世界
個人の問題は世界の問題である。もし個人が不幸で、不満で、満たされていなければ、彼のまわりの世界は悲しみと不満と無知に沈む。もし個人が彼の目標を見出さなければ、世界は目標を見出さないであろう。個人と世界とを分かつことはできない。もし個人の問題が理解によって解決されれば、それによって世界の問題は解決されうる。他の人に理解を与えることができるためには、あなた方自身がまず理解しなければならない。
重要なのはあなた方自身であって、世界を変えるためにあなた方が何をするかでも、どのようにするかでもない。もしあなた方が心優しくて親切なら、もしあなた方の表情があなた方の思考・感情を示していれば、そしてもしあなた方が本当に嬉々としていれば、その時には、なぜあなた方がこの混乱した世界でそのようにしていられるのかを見るために、あらゆる人があなた方のところにやって来るであろう。
個人対社会の関係はどうあるべきなのか? 明らかに社会が個人のために存在するのであって、その逆ではない。社会は、人間の結実のためにある。それは、個人に自由を与えることによって、彼が最高度の英知を目覚めさせる機会を持つことができるようにするためにあるのだ。この英知は、技術または知識の単なる養成ではない……。英知は自由において見出されるべきものなのだ。
われわれは個人であると同時に社会的存在である。……平和があるためには、人間と市民との間の正しい関係を理解しなければならない。もちろん国家はわれわれが完全に市民であることを望んでいる。しかしそれは為政者側の愚かしさである。われわれ自身は、人間を市民に譲渡することを欲している。なぜなら、市民であることは、人間であることよりも容易だからである。善き市民であることは、社会の枠内で能率良く機能することである。能率と順応は市民を強固にし、無情にするので、彼はこれらを要求される。そしてそうなれば、彼は市民のために人間を犠牲にすることができるわけだ。善き市民は必ずしも善き人間ではない。しかし善き人間は必ず――特定の社会や国のものではない――正しい市民である。彼は何よりも先ず善き人間だから、彼の行為は反社会的ではなく、彼は他の人間に対立したりはしないだろう。彼は、他の善き人間たちと協力し合って生きることだろう。彼は権威や権力を追い求めたりはしないだろう。彼は冷酷になることなく、能率的に働くことができるだろう。市民は人間を犠牲にしようと企てる。しかし至高の英知を捜し出しつつある人間は、当然ながら市民の愚行を避けるだろう。それゆえ国家は善き人間、英知の持ち主に反対するだろう。しかしかくのごとき人間は、あらゆる政府や国から自由なのである。
世界はあなたと別個のものだろうか? 社会の構造はあなたや私のような人々によって築き上げられてきたのではないだろうか? その構造に根源的な変化を引き起こすためには、あなたや私が根本的に自分自身を変容させねばならないのではあるまいか? もしもそれがわれわれから始まらなければ、いかにして諸々の価値の深い革命がありうるだろうか? 現在の危機において助けになるには、人は新しいイデオロギー、新しい経済計画を捜し出さねばならないのだろうか? それとも人は自分自身の内部の葛藤や混乱――その投影がすなわち世界だ――を理解し始めねばならないのだろうか? 新しいイデオロギーは人と人の間の和合をもたらしうるだろうか? 信念は人と人とを反目させないだろうか? われわれはイデオロギー的な障壁――というのは、あらゆる障壁はイデオロギー的なものだから――を片づけ、われわれの問題を結論や公式の偏重によらずに、直接に、かつ偏見なしに検討してみなければならないのではあるまいか? われわれはけっしてわれわれの問題と直接に関係しないで、常に何らかの信念や公式を介在させる。われわれは、問題と直接に関係する時にのみ、それらを解決できるのだ。人と人とを戦わせるのはわれわれの問題ではなく、それらについてのわれわれの観念なのである。問題はわれわれを結びつける。しかし観念はわれわれを分離させる。
混乱と不幸は単に西洋だけのものではない。なぜなら世界中の人間が同じ苦境に陥っているからだ。個人の問題はまた世界の問題でもあり、両者は二つの離れた、別個の過程ではない。われわれの関心は人間の問題にある。その人間が東洋にいようと西洋にいようと――洋の東西は勝手な、地理的区別なのだ――人間の全意識は神、死、正しい、幸福な生活に、子供たちと彼らの教育に、戦争と平和に関心がある。このすべてを理解せずには、人間の治療はありえない。
人間にとっての根本問題は、いかにして戦争をとめるかでも、どの神がどの神より優れているかでも、どの政治・経済体制のほうが良いかでも、どの政党に投票したらいいか(どの政党も不正にまみれている)でもない。アメリカ、インド、ソ連などどこに住んでいようと、人間にとっての根本問題は「片隅」から自由になることである。そしてその片隅とは「われわれ自身」のことであり、われわれ自身のちっぽけな精神・心のことなのだ。
重要なのはあなた方自身であって、世界を変えるためにあなた方が何をするかでも、どのようにするかでもない。もしあなた方が心優しくて親切なら、もしあなた方の表情があなた方の思考・感情を示していれば、そしてもしあなた方が本当に嬉々としていれば、その時には、なぜあなた方がこの混乱した世界でそのようにしていられるのかを見るために、あらゆる人があなた方のところにやって来るであろう。
個人対社会の関係はどうあるべきなのか? 明らかに社会が個人のために存在するのであって、その逆ではない。社会は、人間の結実のためにある。それは、個人に自由を与えることによって、彼が最高度の英知を目覚めさせる機会を持つことができるようにするためにあるのだ。この英知は、技術または知識の単なる養成ではない……。英知は自由において見出されるべきものなのだ。
われわれは個人であると同時に社会的存在である。……平和があるためには、人間と市民との間の正しい関係を理解しなければならない。もちろん国家はわれわれが完全に市民であることを望んでいる。しかしそれは為政者側の愚かしさである。われわれ自身は、人間を市民に譲渡することを欲している。なぜなら、市民であることは、人間であることよりも容易だからである。善き市民であることは、社会の枠内で能率良く機能することである。能率と順応は市民を強固にし、無情にするので、彼はこれらを要求される。そしてそうなれば、彼は市民のために人間を犠牲にすることができるわけだ。善き市民は必ずしも善き人間ではない。しかし善き人間は必ず――特定の社会や国のものではない――正しい市民である。彼は何よりも先ず善き人間だから、彼の行為は反社会的ではなく、彼は他の人間に対立したりはしないだろう。彼は、他の善き人間たちと協力し合って生きることだろう。彼は権威や権力を追い求めたりはしないだろう。彼は冷酷になることなく、能率的に働くことができるだろう。市民は人間を犠牲にしようと企てる。しかし至高の英知を捜し出しつつある人間は、当然ながら市民の愚行を避けるだろう。それゆえ国家は善き人間、英知の持ち主に反対するだろう。しかしかくのごとき人間は、あらゆる政府や国から自由なのである。
世界はあなたと別個のものだろうか? 社会の構造はあなたや私のような人々によって築き上げられてきたのではないだろうか? その構造に根源的な変化を引き起こすためには、あなたや私が根本的に自分自身を変容させねばならないのではあるまいか? もしもそれがわれわれから始まらなければ、いかにして諸々の価値の深い革命がありうるだろうか? 現在の危機において助けになるには、人は新しいイデオロギー、新しい経済計画を捜し出さねばならないのだろうか? それとも人は自分自身の内部の葛藤や混乱――その投影がすなわち世界だ――を理解し始めねばならないのだろうか? 新しいイデオロギーは人と人の間の和合をもたらしうるだろうか? 信念は人と人とを反目させないだろうか? われわれはイデオロギー的な障壁――というのは、あらゆる障壁はイデオロギー的なものだから――を片づけ、われわれの問題を結論や公式の偏重によらずに、直接に、かつ偏見なしに検討してみなければならないのではあるまいか? われわれはけっしてわれわれの問題と直接に関係しないで、常に何らかの信念や公式を介在させる。われわれは、問題と直接に関係する時にのみ、それらを解決できるのだ。人と人とを戦わせるのはわれわれの問題ではなく、それらについてのわれわれの観念なのである。問題はわれわれを結びつける。しかし観念はわれわれを分離させる。
混乱と不幸は単に西洋だけのものではない。なぜなら世界中の人間が同じ苦境に陥っているからだ。個人の問題はまた世界の問題でもあり、両者は二つの離れた、別個の過程ではない。われわれの関心は人間の問題にある。その人間が東洋にいようと西洋にいようと――洋の東西は勝手な、地理的区別なのだ――人間の全意識は神、死、正しい、幸福な生活に、子供たちと彼らの教育に、戦争と平和に関心がある。このすべてを理解せずには、人間の治療はありえない。
人間にとっての根本問題は、いかにして戦争をとめるかでも、どの神がどの神より優れているかでも、どの政治・経済体制のほうが良いかでも、どの政党に投票したらいいか(どの政党も不正にまみれている)でもない。アメリカ、インド、ソ連などどこに住んでいようと、人間にとっての根本問題は「片隅」から自由になることである。そしてその片隅とは「われわれ自身」のことであり、われわれ自身のちっぽけな精神・心のことなのだ。
戦争・革命・平和について
これらの言葉からおわかりのように、クリシュナムルティにとってはまず何よりも「個人」が重要なのですが、ただしそれは利己的な存在としての個人ではなく、自己変革を通じて世界の平和に寄与できる存在としての個人です。様々な形で表わされる暴力性、自分を条件づけ、制約している様々なものから本当に自由な、自立した個人、諸々の虚偽の上に成り立っている社会にとっては危険な存在でもある、そういう個人を生み出すことができるだろうか? それが彼の大きなテーマだったのです。なぜなら、依存的な、混乱した、弱い人間がいくら結集して組織を作っても、そうした弱点を組織の中に持ち込み、結局は社会の混乱に寄与してしまうだけだからです。彼は日記の中で次のように書いています。
新しい意識、まったく新しい倫理が、現在の文化、社会構造を根本的に変革するのに必要とされる。これは自明なことだが、左翼も右翼も、革命論者もそれを軽視しているらしい。どんな教義、信条、イデオロギーであろうと、それは古い意識の一部にすぎない。そんなものは、右、左、中心と分裂・断片化する思考が捏造したものにすぎない。こうした動きには、かならず右か左の流血がある。あるいは全体主義への道をたどる。これは現在、私たちのまわりで起こっていることだ。社会的、経済的、倫理的な変革の必要性はだれもが認めるが、その反応は古い意識からくる。その立役者は思考である。人類が陥っている困難や、混乱、窮状は、古い意識の領域にある。それを根こそぎ変えてしまわない限り、人間の為すことは、政治、経済、宗教、そのすべてが互いに滅ぼし合い、地球を破壊するだけだろう。正気なら、まったくもって明らかなことだ。
私たちが核戦争の危機と生態系破壊という二重の根源的危機を避けて生き残りたいのなら、何よりも必要なのは、戦争を必要悪とするイデオロギーに対して平和のイデオロギーをもって、経済成長のイデオロギーに対して環境保護のイデオロギーをもって、結局はまたしても「戦う」ことではなく、われわれ個々人の根源的変容、いわば「魂の革命」である。そうクリシュナムルティは言っているのです。
これまでの「革命」については今さら述べるまでもないかもしれませんが、クリシュナムルティの革命と対比させため、少しだけ紹介させていただきます。例えば、『事典 哲学の木』の中で山泉進氏は、政治哲学者アレントに言及しつつ次のように述べています。
アレントは、近代革命を次のように定義している。「ある新しいはじまりという意味で変化が起り、暴力がまったく異なった統治形態を打ち立て、新しい政治体を形成するために用いられ、抑圧からの解放が少なくとも自由の構成をめざしている」歴史的出来事であると。しかし、現実には、フランス革命、ロシア革命、あるいは戦後のカンボジアにおけるポル・ポト政権の共産主義化にいたるまで、多くの歴史上の革命は抑圧からの解放を目指しながら、自由のための独裁を産出してしまった。
筆者はだいぶ以前(一九七九年)、ある同人誌にカンボジアでの悲劇について書いたことがあります。いささか気負った文章で恐縮ですが、当時のことをそれなりに伝えているのではないかと思います。
カンボジアの悲劇は、われわれに特定のイデオロギーが偏狭な指導者によって掲げられた時の恐るべき結末を伝えている。理想国家の建設のために流された民衆のおびただしい血はどうあがなうのであろうか。無数の骸骨の上にどんなユートピアを作ろうというのだろう。死んだ人々の毛髪で鳥が巣を作っているという光景は、まるで死の国そのものではあるまいか。恐るべき革命理論とその実践のうちに我々は、上に立つ者の度し難い倨傲、あきれるばかりの無神経、無知、同朋愛の全き欠如、人命軽視、未来のために現在を犠牲にする愚行を見るのである。世のいわゆる革命の多くはその名に値しない。それが革命であるならば、それは人間としての共感の上に人と人との協力を生むはずであり、指導者と被指導者といった対立はなくなるはずである。しかし実際は皆野心に動かされているだけなのであり、己れの理論、考え方の下に他者を支配しようとしているだけなのではないか。資本家も労働者もそれぞれ野心や出世の階段を上ろうとしている限り、基本において変りはない。組合幹部が買収されるゆえんである。
革命は内部で起こらなければならない。我々一人ひとりがエゴイズムに由来する諸々の問題を検証し、深くかつたゆみない認識の光のもとで、他者との間に正しい関係を打ち立てなければならない。
大切なことは質であって量ではない。一個の人間の愛の革命は自らその光を外部に投げかけるであろう。
また、魯迅は次のように言っています。「むかし景気のよかったものは、復古を主張し、いま景気のいいものは、現状維持を主張し、まだ景気のよくないものは、革新を主張する。相場はこんなところだ、相場は!」「革命、反革命、不革命。革命者は反革命者に殺される。反革命者は革命者に殺される。不革命者は、革命者と見なされて反革命者に殺されるか、反革命者と見なされて革命者に殺されるか、あるいは、何でもないものとされて、革命者もしくは反革命者に殺される。革命、革革命、革革革命、革革……」(『魯迅作品集3』竹内好訳)。
魯迅は仙台の医学専門学校で医学を学んだのですが、「病気よりも同胞の精神的貧困を救うほうが急務」だと考えるようになって、二年ばかりで医専を退学しています。しかし祖国の現実は厳しく、教え子の何人かの大学生を銃殺されて失っています。彼らは処刑場に隣接する畑地に密かに埋葬され、肥料同然に扱われたと言われています。訳者の竹内好氏は「解説」中で次のように述べています。
清朝が倒れて中華民国がうまれたので、すぐにも自分たちの理想が実現できるものと、魯迅をふくめて当時のインテリゲンツィアは考えた。ところがこの革命は、上層部の首をすげかえただけで、社会革命に発展しなかった。帝国主義を背景にした軍閥が、一人の皇帝に代って支配者になっただけであった。自由も正義も実現しなかったし、民衆の貧困と無知は旧のままだった。革命家の血はいたずらに流され、忘れられたのである。このことは魯迅に深刻な打撃を与えた。そのためかれは、ほとんど絶望に近い状態に陥っていた。この絶望からの脱出が、再度の文学的出発にとって決定的な動機になったと考えられる。
一九二九年に星の教団を解散した後、一九三三年にクリシュナムルティは神智学協会に招かれ、そこで一連の講話と質疑応答をおこないました。当時の世界は、第一次世界大戦の悪夢も覚めやらぬうちにヒットラーが台頭してきて着々と全体主義への道をたどりつつあり、一方では共産主義が勢いを得つつあるといった緊迫した情勢の中にありました。「平和の使徒」として、彼は、平和を妨げ、戦争の直接の原因となっている「ナショナリズム」が疫病のように全世界に蔓延しており、それがほかならぬ神智学協会をも冒しているのを見ました。
この協会は前述のように「人類の普遍的大連帯の中核」となることを標榜していました。が、現実には、世界各国の会員の多くは社会的には上流に属し、したがってそれぞれの祖国の利害と自分の利害が密接に結びついており、それゆえ「協会員」としての自分と「国民」としての自分との間に分裂がありました。これは普段は問題にしないですみましたが、現実の危機に際して表面化せざるをえませんでした。一九一四年、第一次世界大戦が勃発した時、指導者の一人リードビーターはその頑固な大英帝国主義者としての一面をむき出しにしました。興味深いことに、もう一人の指導者ベサント夫人の方はインド自治獲得のための闘いに熱中しており、政治的にはリードビーターと対立関係にあったのです。
やがてリードビーターは、戦争で殺されることは偉大なる祝福であるとまで言うようになります。「新人類」の身体の中で神智学の一族へとすみやかに再生するために、西洋人から古い自我を抜き取ってしまうことは、オカルト的階層組織(ヒエラルキー)構想の助けになるからだというのです。神智学の理想実現のためには、若者が戦死した方がむしろ望ましいというわけです。
この考えをもう少し押し進めれば、いつか人類の普遍的大連帯、友愛を実現するためには、いま少々の犠牲が払われてもさしつかえないということになります。「理想」「大義」のためには現在の人間を犠牲にしてはばからないというのは、ナショナリズムと密接にからんだ狂気の沙汰です。こうしたことを踏まえて以下の質疑応答をお読みいただければと思います。
質問:もし明日戦争が勃発し、ただちに徴兵法が布かれ、武器を取るようあなたを強いたら、一九一四年に神智学協会の指導者たちがしたように、あなたは軍隊に加わって「武器には武器を」と叫びますか? それとも、戦争を無視しますか?
クリシュナムルティ:神智学協会の指導者たちが一九一四年に何をしたかは気にしないでおきましょう。ナショナリズムがあるところ、そこには必然的に戦争があります。いくつかの主権政府があるところ、そこには必然的に戦争があるのです。個人的には、私はいかなる種類の戦争活動にも加わらないでしょう。なぜなら私はナショナリストではなく、階級意識にも所有欲にも駆られていないからです。私は、たんに傷病兵を治療し、再び傷つかせるために彼らを戦場に送り込むために存在しているような組織には加わらないでしょう。むしろ私は、戦争の脅威が迫る前に、これらのことについて理解するようにするでしょう。
さて、少なくともさしあたりは、実際の戦争はありません。戦争が来れば、煽動的なプロパガンダがおこなわれ、仮想の敵に対してありもしないことが言われ、愛国心や憎悪が煽られる。国民は祖国へんp献身に熱狂し、そして「神はわが側にあり、罪悪は敵にある」と叫ぶ。そして幾世紀もの間ずっと、彼らはまさにそれと同じ言葉を叫んできたのです。敵味方共に、神の名において戦い、どちらの側でも、こともあろうに司祭が軍備を祝福するのです。ナショナリズム、彼ら自身の階級的または個人的安泰という病気に取りつかれているので、彼らは爆撃機をも祝福するでしょう。
ですから、私たちが平和――「平和」というのは、敵対的武装のたんに一時的な中断を述べる奇妙な言葉ですが――な時、ともかくお互いに戦場で殺しあっていない時、私たちは何が戦争の原因かを理解し、それらを免れることができるはずです。そして、もしあなた方が、自分の理解、自由において、その自由が含意しているすべてと共に明晰なら、その瞬間が来る時、正しく行動することでしょう、それがどんな行動であれ。あるいは、戦争マニアに従うことを拒否することで、銃殺されるかもしれませんが。
そのように、問題は戦争が来たら自分は何をするかではなく、戦争を防ぐためにいま自分が何をしているかなのです。常日頃私の否定的態度を非難しているあなた方は、まさに戦争の原因である当のものを一掃するために何をしておられますか? 私は戦争の真因について話しているのです。各々の国が軍備を増強してれば必然的に高まる直接の戦争の原因だけではなく。愛国心があるかぎり、階級差別、選民意識、所有欲があるかぎり、必然的に戦争が起こるのです。それを防ぐことはできません。もしあなた方が、戦争の問題にいま直面すべき問題として本当に直面していれば、決然たる行動、明確かつ積極的な行動に出ることでしょう。そしてあなた方のそうした行動によって、戦争の唯一の予防薬、英知、を目覚ますのを助けるでしょう。しかし、そうするためには、あなた方は「わが神、わが国、わが家族、わが家」という病気を自分自身から払い落とさなければならないのです。
クリシュナムルティ:神智学協会の指導者たちが一九一四年に何をしたかは気にしないでおきましょう。ナショナリズムがあるところ、そこには必然的に戦争があります。いくつかの主権政府があるところ、そこには必然的に戦争があるのです。個人的には、私はいかなる種類の戦争活動にも加わらないでしょう。なぜなら私はナショナリストではなく、階級意識にも所有欲にも駆られていないからです。私は、たんに傷病兵を治療し、再び傷つかせるために彼らを戦場に送り込むために存在しているような組織には加わらないでしょう。むしろ私は、戦争の脅威が迫る前に、これらのことについて理解するようにするでしょう。
さて、少なくともさしあたりは、実際の戦争はありません。戦争が来れば、煽動的なプロパガンダがおこなわれ、仮想の敵に対してありもしないことが言われ、愛国心や憎悪が煽られる。国民は祖国へんp献身に熱狂し、そして「神はわが側にあり、罪悪は敵にある」と叫ぶ。そして幾世紀もの間ずっと、彼らはまさにそれと同じ言葉を叫んできたのです。敵味方共に、神の名において戦い、どちらの側でも、こともあろうに司祭が軍備を祝福するのです。ナショナリズム、彼ら自身の階級的または個人的安泰という病気に取りつかれているので、彼らは爆撃機をも祝福するでしょう。
ですから、私たちが平和――「平和」というのは、敵対的武装のたんに一時的な中断を述べる奇妙な言葉ですが――な時、ともかくお互いに戦場で殺しあっていない時、私たちは何が戦争の原因かを理解し、それらを免れることができるはずです。そして、もしあなた方が、自分の理解、自由において、その自由が含意しているすべてと共に明晰なら、その瞬間が来る時、正しく行動することでしょう、それがどんな行動であれ。あるいは、戦争マニアに従うことを拒否することで、銃殺されるかもしれませんが。
そのように、問題は戦争が来たら自分は何をするかではなく、戦争を防ぐためにいま自分が何をしているかなのです。常日頃私の否定的態度を非難しているあなた方は、まさに戦争の原因である当のものを一掃するために何をしておられますか? 私は戦争の真因について話しているのです。各々の国が軍備を増強してれば必然的に高まる直接の戦争の原因だけではなく。愛国心があるかぎり、階級差別、選民意識、所有欲があるかぎり、必然的に戦争が起こるのです。それを防ぐことはできません。もしあなた方が、戦争の問題にいま直面すべき問題として本当に直面していれば、決然たる行動、明確かつ積極的な行動に出ることでしょう。そしてあなた方のそうした行動によって、戦争の唯一の予防薬、英知、を目覚ますのを助けるでしょう。しかし、そうするためには、あなた方は「わが神、わが国、わが家族、わが家」という病気を自分自身から払い落とさなければならないのです。
しかし、戦争をとめるためにはまず私たち自身が変わらなければならないという彼の指摘は、容易には受け入れられませんでした。例えば彼はある質疑応答集会で、「差し迫った戦争や原子爆弾の脅威の前では、単に個々人の変容に傾注するというのは無駄なのではないでしょうか?」という質問を受けています。これに対して彼は、次の答えに明快に応えています。
これは非常に複雑な問題であり、したがって慎重に調べてみなければなりません。……われわれは何が戦争の原因か知っています。それらはいたって明白であり、学童ですらそれらを言うことができるでしょう――すなわち、貪欲、ナショナリズム、権勢欲、地理的・国家的区別、経済的衝突、主権国家の存在、愛国心、右のであれ左のであれ、一方的に他に押し付けられるものとしてのイデオロギー、等々です。これらの戦争の原因はあなたや私によって生み出されるのです。戦争は、われわれの日常生活の壮大で血生臭い現れなのではないでしょうか? われわれは自分自身をある特定の集団――国家、宗教、民族的集団――と同一化させます。なぜならそれはわれわれに力の意識を与えるからです。そして力は必然的に破局をもたらすのです。
戦争の責任はあなたや私にあるのです。ヒットラーやスターリン等々のスーパーリーダーにではなく。戦争の責任は資本家や頭の狂った指導者たちにあると言うのは便利な言い逃れです。心底では各人が豊かになり、権勢を持つことを望んでいます。それらが戦争の原因なのであり、その責任は私やあなたにあるのです。戦争はわれわれの日常生活の結果であり、ただずっと壮大で、血生臭いだけだというのは、ごく明白だと思われます。われわれが国境、境界、関税障壁を持つ社会を作り上げるのは、自分自身の所有物を貯え、札束をうず高く積み上げようとしているからです。そしてある国の利害が他の国のそれと衝突する時、それは必然的に戦争に行き着くのです――これは一個の事実です。……
われわれは戦争に直面しており、それゆえその責任は誰にあるのかを見出さなければならないのではないでしょうか? 正気な人なら責任は自分にあることを見抜き、そして言うでしょう。「そう、私がこの戦争を引き起こしているのであり、それゆえ私は国家主義的であることをやめ、愛国心に駆られないようにし、国籍にこだわらないようにし、ヒンドゥ?ー、イスラムあるいはキリスト教徒であることをやめ、ただの人間であるようにしよう。」そのためにはとてつもなく明晰な思考と知覚が必要ですが、われわれのほとんどは事実に直面することを望みません。もしあなたが個人的に戦争に反対しているなら、……どうしたらいいでしょう? 戦争に反対している正気な人は何をすべきでしょう? まず彼は自分の精神から、貪欲など、戦争の諸原因を洗い落とさなければならないのではないでしょうか? 戦争の責任はあなたにあるのですから、あなたが戦争の原因から自分を自由にすることが大切なのです。それはとりわけ、あなたが愛国的であることをやめなければならないということです。そうするつもりがあるでしょうか? 明らかにありません。なぜならあなたはヒンドゥ?ー、バラモン、等々と呼ばれること、レッテルを貼られることを好むからです。つまり、あなたはレッテルを崇拝し、正気に、理性的に生きることを二の次にするのです。こうしてあなたは、好むと好まざるとにかかわらず、破滅への道を歩むのです。
もし人が戦争の原因を免れたければ、彼はどうしたらいいのでしょう? どうやって戦争をとめたらいいのでしょう? 差し迫った戦争をとめることはできるでしょうか? 貪欲のはずみ、勢い、ナショナリズムの力は、すでにあらゆる人がつけてしまっています。それはとめられるでしょうか? 明らかにとめられません。戦争は、ロシア人、アメリカ人、われわれの全員が直ちに自分を変容させ、ナショナリズムを放棄しよう、ロシア人、アメリカ人、ドイツ人、イギリス人であること、あるいはヒンドゥ?ー教徒、イスラム教徒であることをやめ、ただの人間であるようにしようと言うとき、レッテルのないただの人間同士として、一緒に幸福に暮らすようにしようと言うとき初めてとめられるでしょう。もし戦争の原因がわれわれの精神・心から根絶されれば、戦争はなくなるでしょう。
が、戦争の勢いはなお続いています。例えば、もし家が燃えていたら、どうしたらいいでしょう? われわれは家ができるだけ火災を免れるようにするため、家事の原因を調べ、適切な煉瓦、耐火材料、改良された家屋構造、等々を見つけて、新しく家を建てるでしょう。言い換えれば、われわれは燃えている家は放置するということです。同様に、文明が崩壊し、自滅に向かっている時は、それについてもはや自分には何もできないと気づいた正気な人々は、不燃性の材料で新しい家を建てようとするでしょう。それこそは唯一の行動の仕方、唯一の理性的方法なのです――単に古い家を改修したり、燃えている家にパッチワークを施すことではなく。
戦争の責任はあなたや私にあるのです。ヒットラーやスターリン等々のスーパーリーダーにではなく。戦争の責任は資本家や頭の狂った指導者たちにあると言うのは便利な言い逃れです。心底では各人が豊かになり、権勢を持つことを望んでいます。それらが戦争の原因なのであり、その責任は私やあなたにあるのです。戦争はわれわれの日常生活の結果であり、ただずっと壮大で、血生臭いだけだというのは、ごく明白だと思われます。われわれが国境、境界、関税障壁を持つ社会を作り上げるのは、自分自身の所有物を貯え、札束をうず高く積み上げようとしているからです。そしてある国の利害が他の国のそれと衝突する時、それは必然的に戦争に行き着くのです――これは一個の事実です。……
われわれは戦争に直面しており、それゆえその責任は誰にあるのかを見出さなければならないのではないでしょうか? 正気な人なら責任は自分にあることを見抜き、そして言うでしょう。「そう、私がこの戦争を引き起こしているのであり、それゆえ私は国家主義的であることをやめ、愛国心に駆られないようにし、国籍にこだわらないようにし、ヒンドゥ?ー、イスラムあるいはキリスト教徒であることをやめ、ただの人間であるようにしよう。」そのためにはとてつもなく明晰な思考と知覚が必要ですが、われわれのほとんどは事実に直面することを望みません。もしあなたが個人的に戦争に反対しているなら、……どうしたらいいでしょう? 戦争に反対している正気な人は何をすべきでしょう? まず彼は自分の精神から、貪欲など、戦争の諸原因を洗い落とさなければならないのではないでしょうか? 戦争の責任はあなたにあるのですから、あなたが戦争の原因から自分を自由にすることが大切なのです。それはとりわけ、あなたが愛国的であることをやめなければならないということです。そうするつもりがあるでしょうか? 明らかにありません。なぜならあなたはヒンドゥ?ー、バラモン、等々と呼ばれること、レッテルを貼られることを好むからです。つまり、あなたはレッテルを崇拝し、正気に、理性的に生きることを二の次にするのです。こうしてあなたは、好むと好まざるとにかかわらず、破滅への道を歩むのです。
もし人が戦争の原因を免れたければ、彼はどうしたらいいのでしょう? どうやって戦争をとめたらいいのでしょう? 差し迫った戦争をとめることはできるでしょうか? 貪欲のはずみ、勢い、ナショナリズムの力は、すでにあらゆる人がつけてしまっています。それはとめられるでしょうか? 明らかにとめられません。戦争は、ロシア人、アメリカ人、われわれの全員が直ちに自分を変容させ、ナショナリズムを放棄しよう、ロシア人、アメリカ人、ドイツ人、イギリス人であること、あるいはヒンドゥ?ー教徒、イスラム教徒であることをやめ、ただの人間であるようにしようと言うとき、レッテルのないただの人間同士として、一緒に幸福に暮らすようにしようと言うとき初めてとめられるでしょう。もし戦争の原因がわれわれの精神・心から根絶されれば、戦争はなくなるでしょう。
が、戦争の勢いはなお続いています。例えば、もし家が燃えていたら、どうしたらいいでしょう? われわれは家ができるだけ火災を免れるようにするため、家事の原因を調べ、適切な煉瓦、耐火材料、改良された家屋構造、等々を見つけて、新しく家を建てるでしょう。言い換えれば、われわれは燃えている家は放置するということです。同様に、文明が崩壊し、自滅に向かっている時は、それについてもはや自分には何もできないと気づいた正気な人々は、不燃性の材料で新しい家を建てようとするでしょう。それこそは唯一の行動の仕方、唯一の理性的方法なのです――単に古い家を改修したり、燃えている家にパッチワークを施すことではなく。
クリシュナムルティは「もしも人間が機械的な存在であり、自動機械であれば、未来を予見し、完全なユートピアの計画を立てることはできる。そのときは、周到に未来社会の計画を練って、それに向かって働くことができるだろう。だが人間は、ある特定のパターンに従って作り上げられる機械ではない」と、いわゆる改革や革命に異議を唱えているのです。しかも現在と未来の間には無数の予見できない事態があり、それらが私たちに無数の影響を及ぼしうる。にもかかわらず改革者たちは未来を輝かしいイメージで飾りたて、美しい言葉で描き、人々を眩惑し、現在を犠牲にして、ありもしない未来へと導こうとする。が、そもそもなんの権利があって他人に自分の理想を押し付けることができるのか? 理想は、その唱道者があれこれの本から引っぱり出したものに自分の混乱した願望、野心、恐怖といったものを混ぜてこね上げたものにすぎないかもしれないではないか。しかも暴力的な手段で平和な世界の実現をめざしているが、そんなことは不可能だ。そう、クリシュナムルティは言うのです。もし本当に今とは違う社会――病的な羨望、野心、出世欲、競争、貪欲といった心理的要素に基づいていない社会――を実現したいのなら、建設のための「材料」を吟味し、堅固な材料、腐敗しない材料を選ばなければならないと言うのです。
では、戦争に反対の人々は平和のために結集し、反戦組織を作るべきなのでしょうか? ここで注意すべきことは、参加者の善意にもかかわらず、組織は力の場となり、そこには力が集まってくるということです。しかるに、戦争の主因は力、権力、権勢です。まさに反戦のために結束していく過程で、私たちは新たな力の場を作り上げてしまうのです。そこに組織的運動の難しさがあるのです。
結局、重要なのは組織ではなく、人間同士の間の相互理解、愛情、思いやりであり、それに基づいた助け合いです。だから問題は常に私たち一人ひとりの精神・心のあり方へと戻ってくるのです。世界の問題と個人の問題は直結しているのであり、たとえ世界に何十億の人間がいようと、私たちはその数の大きさに眩惑されてはならないのです。結局、私たち一人ひとりが戦争の原因である病的な物欲、支配欲、権力志向、あるいは他を犠牲にして、あるいは無視して自分だけが安定しようとする自己中心的衝動から自由にならなければ、戦争はなくならないのです。
戦争をとめ、世界に平和をもたらすためには、個々人――あなたと私――に革命が起こらなければなりません。この内的革命を伴わない経済的革命は無意味です。なぜなら、飢餓は、われわれの心理状態――貪欲、羨望、悪意、所有欲――によって生み出された不均衡な経済状態の結果だからです。悲しみ、飢え、戦争を終わらせるためには、心理的革命が起こらなければなりません。が、われわれのごくわずかしかそのことに直面しようとしていません。平和について討論し、そのための立法を計画し、新しい連盟、国連等々を組織するかもしれません。が、われわれは平和を勝ち取ることはないでしょう。なぜなら、われわれは自分の地位、権威、金銭、財産、愚かしい人生を放棄しないでしょうから。他の人に頼ることはまったくの無駄です。他の誰もわれわれに平和をもたらすことできないのです。いかなる指導者も、政府も、軍隊も、国も、われわれに平和をもたらすことはないのです。平和をもたらすのは内面的変容であり、それが外面的行動となって現われるでしょう。内面的変容は孤立ではなく、外面的行為から引き下がることではありません。それどころか、正しい思考がある時にのみ正しい行為がありうるのであり、そして正しい自己認識がないかぎり正しい思考はないのです。あなた自身を知ることなしには、平和はありえないのです。
外なる戦争を終わらせるためには、あなたはまず内なる戦争を終わらせなければならないのです。……世界の不幸と戦争は、あなたが危険を察知し、自分の責任を認め、それを他の誰かに任せないときにのみとめられるでしょう。もしあなたが苦しみに気づき、即座の行動が急務であることを認識し、それを延期しないとき、あなたは自己変容を遂げるでしょう。そして、あなた自身が平和なとき、隣人と平和に暮らすときにのみ、平和が訪れるでしょう。
彼は戦争について、さらに次のように述べています。
戦争はわれわれの内面的葛藤の最終的表現である。実業界、政界、宗教界で、あるいは様々なグル同士、セクト間、ドグマ間で絶えず戦争が続いている。
われわれは第三次世界大戦を回避することはできないかもしれないが、しかし敵意を生み、愛を妨げる暴力やその他の原因から精神と心を自由にすることはできる。すると、この暗い世界に、心の清らかな人々が現れ、そして彼らから多分真の(平和な)文化の種子が芽生えるであろう。
われわれは第三次世界大戦を回避することはできないかもしれないが、しかし敵意を生み、愛を妨げる暴力やその他の原因から精神と心を自由にすることはできる。すると、この暗い世界に、心の清らかな人々が現れ、そして彼らから多分真の(平和な)文化の種子が芽生えるであろう。
第二次大戦後私たちはしきりに「反戦平和」を唱えるようになりましたが、ふだんの日常生活において私たちは内面的に本当に平和に生きているでしょうか? これに関連して、鋭利な文芸評論家として知られていた正宗白鳥の書いた「内村鑑三」という評伝の一部を紹介させていただきます。白鳥によると、第二次大戦後、鑑三が日露戦争・第二次大戦の頃、熱烈に徹底的に戦争反対を唱導していたことが思い出され、反戦論者として再評価され、改めて敬意を寄せられるようになったというのです。そもそも、「日清日露戦役の時には、戦争反対説などは何処にも現われていなかった」と白鳥は回想しています。鑑三でさえ、日清戦争の時には、それを「正義の戦」であるとして、英文で書いて、世界に向かって宣伝したりしていたのです。キリスト信者が戦争反対を唱えるのは当然なはずなのに、その当然のことを敢行する者が滅多になかったというわけです。第二次大戦中の宗教者たちの戦争協力についてはいろいろ議論され批判されてきたようですが、実はそれ以前から問題があったのです。日露戦争に反対して非戦論を唱えたのは、幸徳秋水などの社会主義者の他には、キリスト教徒の内村鑑三ぐらいだったようです。
日露戦争の頃、白鳥は読売新聞の記者として社会の各方面に取材しに出かけ、「戦争景気をよく見聞していたのだが、戦争を呪詛していた日本人は何処にもなかったと云ってよかった。大抵は讃美者であった」のです。さらに「文学者美術家教育家などに、戦争行為に対して懐疑の念を抱いていた者は絶無のようであった。そして戦争反対を唱える者がたまにあるとすると、それは変人奇人と思われるに過ぎなかった」というのです。鑑三もまた変人奇人の類いと見なされていたのでしょう。
近松秋江の家の近所に山県五十雄という人が住んでいたそうだが、内村が時々その家を訪問して、大きな声で戦争を罵倒するのを秋江は聞いていたそうだ。「内村さんもあれだから困るよ」、と秋江は笑って私に語った。彼も私と一緒に内村の文学講演を二三度、青年会館に聴きに行ったことがあって、内村に対して平生多少の敬意を持っていたのであった。
日露戦争中のある夏、私は、新聞の文学関係記事の担任者として、当時小川町に住んでいた佐々木信綱氏に招かれて晩餐を饗せられたことがあったが、その時の相客は老文学者依田学海と上田敏とであった。雑話のうちにトルストイの徹底的の非戦説が出ると、翁は「口先で話が極らなければ、腕ずくで勝負をつけるより外為方がないじゃないか」と、口角泡を飛ばして論じた。「トルストイは先生より年下ですよ」と上田が云うと、「そうか、年下のくせに生意気だ。学海先生のお説を聞きに来い」とふざけた口を利いて一座を笑わせた。トルストイの無抵抗主義なんかは、真面目に人に取合われない時代であった。内村のように馬鹿正直に、真剣に無抵抗主義を唱え、戦争廃止を唱えるのは、むしろ奇異の振舞なのであった[現代仮名遣いに改め]。
日露戦争に勝利し、第一次大戦では対岸の火事の乗じて儲けた後、第二次大戦へと至る過程では「鬼畜米英」に勝るとも劣らぬほどの強欲ぶりを発揮して領土を拡大し、資源を確保し、大儲けをしようと思ったのが、あにはからんや徹底的に苦汁をなめてから、ようやく反戦論者が多数出現することになったのです。私たちは?支配者・権力者だけでなく、被支配者・服従者も――実はとてつもなく残忍で暴力的なのではないでしょうか? しばらく前に紹介したルネ・フェレは、現代文明の実態について次のように述べています。
個人は、今や社会的エンジン内の歯車にすぎない。彼の生ははななだしく空虚で、かつ不毛である。彼の内面的貧困は、彼に所有や気晴らしを渇望させる。さらに、所有すらもが気晴らしにされる。なぜなら、いったん事物がその正当な用途から切り離されるや、それは娯楽の種にしかすぎなくなるからである。刺激と回避とが普遍的になり、人間の思考はもっぱら娯楽と逃避に向けられている。事物への絶えずつのりゆく要求は、もうすでに行き過ぎている産業的発展をなお一層加速化させており、人間は、自分自身の蓄積物の重圧で押しつぶされているにもかかわらず、もっと多くを要求しているありさまである。人々は、原材料や市場、領土や政治的権力を求めて、核による全滅の戦慄すべき予兆に脅かされる限界点まで、陰険に戦い合うのである。人間は、財産と快楽の過剰の中に、あまりにもすぐに、そして名状しがたい恐怖に終わるかもしれないような、生の強烈さを追い求めるのである。
あらゆる個人が、他のあらゆるものを犠牲にして、肉体的、精神的により一層膨張し、蓄積することを欲する。彼は、彼の利己的な衝動の輪の中に、数名の彼の家族や友人を含めるかもしれないが、しかし世界のその他の人々は彼の合法的犠牲者である。なぜなら、競走に勝ち、弱い者を押えつけることは、世間公認の、ごくあたり前な行動だからである。個人は、社会という肉体の癌細胞になったのである。そして社会という肉体は、個人の盲目的で無法な衝動のゆえに腐り、ずたずたに引き裂かれるのである。社会的肉体のすべての細胞が病んでおり、各々が他を犠牲にしている時には、なおのことそうである。集合的有機体は、異常に肥大化し、そしてその機能のとてつもない複雑さで身動きがとれなくなって、その重みの下で崩れてしまうのである。
家族について
フェレは「家族」に言及していますが、十分に気をつけないがぎり、それは利己主義の中心になっていくのです。クリシュナムルティはその家族について次のように述べています。
家族とは何だろう? 「これは僕の家族だ」と君[訳註 :インドのクリシュナムルティ・スクールの生徒に向かって答えている]が言う時、それは何を意味しているのだろう? 君の父母、兄弟姉妹、親密感、同じ家に住んでいるという事実、両親が君を保護してくれているという気持ち、一定の財産、宝石やサリーその他の衣服の所有――このすべてが家族の基盤である。そして君の家族のように他の家に住み、君たちとまさに同じことを感じ、「私の妻」、「私の夫」、「私の子供」、「私の家」、「私の車」という気持ちを抱いている他の家族がある。同じ土地にそのような多くの家族が住むようになると、彼らは他の一群の家族によって侵略されまいと思うようになる。やがて力のある家族が上に立ち、大きな財産を獲得し、より多くの金銭、より多くの衣服、より多くの車を所有し、そして結集して法律を制定し、他の家族に何をすべきか命令するようになる。こうして次第に、法律、規制、警官、陸軍、海軍を備えた社会ができ上がっていく。そしてついには地球全体が種々さまざまな社会によっておおい尽くされていく。すると下層の抑圧されている人々は敵対的な観念を持つようになり、高い地位におさまっている人々、権力の手段を一手におさめている人々を打倒しようと思うようになる。こうしてその特定の社会を打倒して、別のを作り上げる。
われわれは子供たちを自分の気まぐれのゲームにおける「ポーン」[訳註 チェスで使われる駒で、将棋の歩に近いもの]として使い、そして不幸の上に不幸を重ねていく。われわれは子供たちを、われわれ自身からの逃避のもう一つの手段として用いるのだ。
家族は社会に対立する構成単位ではないだろうか? それはあらゆる活動をまち散らす中心、他のあらゆる種類の関係を支配する排他的な関係なのではないだろうか? それは、区別、分離、高位者と低位者、強者と弱者を生み出す自己閉鎖的な活動ではないだろうか? 制度としての家族は、すべてのものに逆らっているように思われる。各々の家族は他の家族、他の集団に対立しているのだ。家族は、その財産とともに、戦争の一因なのではないだろうか?
人類は進路をまちがえたのではないか?
われわれは子供たちを自分の気まぐれのゲームにおける「ポーン」[訳註 チェスで使われる駒で、将棋の歩に近いもの]として使い、そして不幸の上に不幸を重ねていく。われわれは子供たちを、われわれ自身からの逃避のもう一つの手段として用いるのだ。
家族は社会に対立する構成単位ではないだろうか? それはあらゆる活動をまち散らす中心、他のあらゆる種類の関係を支配する排他的な関係なのではないだろうか? それは、区別、分離、高位者と低位者、強者と弱者を生み出す自己閉鎖的な活動ではないだろうか? 制度としての家族は、すべてのものに逆らっているように思われる。各々の家族は他の家族、他の集団に対立しているのだ。家族は、その財産とともに、戦争の一因なのではないだろうか?
人類は進路をまちがえたのではないか?
なぜこんなことになってしまったのでしょう? クリシュナムルティと晩年にかけて親交のあった、世界的に有名な理論物理学者デヴィッド・ボーム(一九一七?一九九二)との間の長い対談集『時間の終焉 (The Ending of Time)』(邦訳なし)があるのですが、その冒頭でクリシュナムルティは「人類は進路をまちがえたのではないでしょうか?」と尋ねています。これに対してボームは、「ええ、たぶん。以前ある本を読んでアッと思ったのですが、人間は五、六千年前、他人を略奪し奴隷化できるようになりはじめてから、進路をまちがえ、以来もっぱら搾取と略奪に明け暮れるようになったらしいのです」と答えています。
この由々しい事実と密接に関連しているのは、「人類の約九十パーセント余りは奴隷の子孫である」(心理学者アドラー)ということです。そして私たちは何千年もの間、自分より強い者に服従し、弱い者をいじめるように「条件づけ」られてきたということです。
魯迅は「燈下漫筆」という随想録の中で次のように述べています。
……学者たちがもったいをつけて、歴史の時代区分に当って「漢民族発祥時代」「漢民族発展時代」……など、耳ざわりのよう項目をいくらならべようとも、……いかにも表現がまだるっこい。次のような、もっと単刀直入の言い方があるのだ――
一、奴隷になりたくてもなれない時代
二、しばらく安全に奴隷でいられる時代
一、奴隷になりたくてもなれない時代
二、しばらく安全に奴隷でいられる時代
魯迅はさらに次のように述べています。
……じつは私たちの側で、とっくに貴賎、大小、あらゆる差別を自分でつくって、受け入れ態勢をととのえつつあるのだ。自分が他人から虐げられても、べつの他人を虐げることはできる。自分が他人の餌食にされても、べつの他人を餌食にすることができる。一段、また一段、抑圧可能の仕組みができていて、その中では身動きはかなわず、また身動きしようともしない。かりに身動きしたところで、めったに得はなく、むしろ損するばかりなのだ。ここに古人のえがいた見事な図式をお目にかけよう――
「天に十日(十干)あり、人に十等あり。下の上に事うるゆえん、上の神に共うるゆえんなり。ゆえに王の臣は公、公の臣は大夫、大夫の臣は士、……輿の臣は隷、隷の臣は僚、僚の臣は僕、僕の臣は台。」(『左伝』昭公七年)。
「天に十日(十干)あり、人に十等あり。下の上に事うるゆえん、上の神に共うるゆえんなり。ゆえに王の臣は公、公の臣は大夫、大夫の臣は士、……輿の臣は隷、隷の臣は僚、僚の臣は僕、僕の臣は台。」(『左伝』昭公七年)。
では、「台」には臣がいないのか? いや、心配御無用。もっと位の低い、力の弱い妻子がいるからだ。しかも、子にも希望がないわけではない。成人して「台」に昇格して結婚し、子どもを持てば、妻子を顎で使えるようになるからである。さらに妻は、もしも息子が結婚して嫁が来れば、嫁いびりができる……。こうして、食物連鎖のように支配と服従の循環体系が出来上がっていく。そう魯迅は指摘しています。
こうした連鎖が何世代にもわたって続いていけば、人はいやおうなしに相互虐待傾向を強めていくわけですから、「心の医者」をめざした魯迅は、まず何よりも人民の内面深くに巣食っている奴隷根性から彼らを自由にすることを願ったのです。
これはクリシュナムルティにとっても同様に大きな課題でした。しかし、人々が権威に隷従し、それを甘受することを「自己決定」「自己選択」している限り、それから彼らを自由にすべく促すことは容易ではないでしょう。
クリシュナムルティは、人間の一般的混乱の原因として、彼が現状に満足せず、心理的にたえず何かになろうとしているという事実を挙げています。たえずもっと多くほしがり、より安楽に、より安定したがり、知的に優越したがり、そしてその過程で他者を利用し、より自己中心的領域を広げていき、かくして自分という断片をたえず他の断片と衝突させ続けてきたのです。国家間、イデオロギー間の衝突、戦争、かつての植民地支配はその最終的な帰結です。たえず何かになろうとする心理的習性は、根深い条件づけの結果であり、それがいかに破壊的かに気づくことは容易ではありません。しかしこの心理的メカニズムをとめないかぎり、われわれは永久に本然の生を生きることはできないのです。
いま生きるかわりに、いつか生きるため、社会や自分自身が立てた目標に向かってたえずせわしなく、不毛な努力を繰り返し続けていくだけです。悟りを得るため、非暴力的になるために修行し努力する間中ずっと、奇妙にも狭量で暴力的であり続け、生の芳香にけっして浴することはないのです。風にそよぐ草、壮麗な日没、子供たちの歓声、小川のせせらぎ、鳥の鳴き声などの生の歓喜は、何かになろうとして不毛な努力を重ねている者のかたわらを通り過ぎてしまうからです。
そしてクリシュナムルティは、人間が「内面的に貧しければ貧しいほど、それだけ外面的なものをより多く蓄えようとする」ことを見抜きました。逆に言えば、内面的に豊かであればあるほど、人間は外面的に多くを求めず、必要最小限の衣食住に甘んじ、喜々として「シンプル・ライフ」を生きるようになるということです。
ヴァン・ゴッホはかつて、弟のテオとの会話の中で、「キリストがあれほど限りなく偉大なのは、どんな家具も、その他の愚劣な付属品も、彼の行手を邪魔しなかったからだよ」と言ったそうです。
そこでクリシュナムルティは、彼自身が現に生きているところの、内面的に豊かな生の障害となっているものを指摘し、誰もがそういう豊かな生――あるいは「本然の生」――を生きることができるように手を貸し続けたのです。
観察・気づき・否定的アプローチ
現在の大量生産・大量消費の背景には、内面的貧しさゆえの外面的貪欲があり、ゆえに人類の未来はこの貪欲にどう対処するかにかかっていると言っても過言ではないでしょう。クリシュナムルティの先祖である古代インドのバラモンたちは、言わば欲望の水門をできるだけ閉じるようにしていたのですが、現代人はその水門をまさに全開にしてしまったのです。この締まりのない状態から抜け出すには、言うまでもないことですが、自分が置かれている状況を「観察し」、自分自身の内面の状態に「ありのままに気づく」ことが必要です。
そして「虚偽を虚偽と見、虚偽の中に真実を見、真実を真実と見る」ことが必要であり、そのためにクリシュナムルティは一種の消去法に基づいた否定的アプローチ、いわば「ネガティブ・ウエイ」とでも言うべきものに訴えます。そのエッセンスは次の言葉に簡潔に表わされています。
諸君の望まざる所有物や理想は何々であるかをみずから見出せ。自分が何を望まぬかを知り、それを消去することによって、諸君は精神の重荷を下ろすであろう。そのときはじめて、精神はそうなってもなおかつ肝要なものを理解するであろう。
信ずるな。ただし、諸君自身をも含むいかなるものも。諸君の不信とともにぎりぎりまで歩め。そうすれば、疑いえたあらゆるものは虚偽であったこと、そして最も激しい懐疑の炎に耐えうるもののみが真理であることを見出すであろう。なぜなら、そうなってもなおかつ残るものが、懐疑を自己浄化過程とする「生」に他ならないからである。
この、烈々たる、めらめらと燃え上がるような「懐疑あるいは否定の炎」こそは彼の本質であり、そしてそれは彼を生涯にわたる「反逆者」にしたのです──ただし「虚偽」に対しての。そのことは、一九二九年におこなわれた有名な『星の教団』解散宣言の中で、団員たちに向けて放った次の言葉が如実に物語っています。
虚偽と非本質的なものにその基盤を置いているすべての社会から、諸君はどれだけ自由であり、どれほどはみ出し、そしてそのような社会に対してどの程度危険な存在になっているだろうか?
信ずるな。ただし、諸君自身をも含むいかなるものも。諸君の不信とともにぎりぎりまで歩め。そうすれば、疑いえたあらゆるものは虚偽であったこと、そして最も激しい懐疑の炎に耐えうるもののみが真理であることを見出すであろう。なぜなら、そうなってもなおかつ残るものが、懐疑を自己浄化過程とする「生」に他ならないからである。
この、烈々たる、めらめらと燃え上がるような「懐疑あるいは否定の炎」こそは彼の本質であり、そしてそれは彼を生涯にわたる「反逆者」にしたのです──ただし「虚偽」に対しての。そのことは、一九二九年におこなわれた有名な『星の教団』解散宣言の中で、団員たちに向けて放った次の言葉が如実に物語っています。
虚偽と非本質的なものにその基盤を置いているすべての社会から、諸君はどれだけ自由であり、どれほどはみ出し、そしてそのような社会に対してどの程度危険な存在になっているだろうか?
あるいはまた、インドでの教師との討論中の次のような発言(『英知の教育』春秋社)。
「否定」という言葉の意味をご存じですか? 過去を否定する、ヒンドゥー教徒であることを否定するとはどういう意味なのでしょう? 否定には真の否定と偽りの否定があります。動機のある否定は偽りの否定です。目的を持つ否定、意図的な否定、未来をめざした否定は否定ではないのです。もし、より多くのものを得るために否定するなら、それは否定とは言えません。これに対して、なんの動機も伴わない否定があるのです。否定し、その結果将来自分に何が起こるか関知しないこと――それが真の否定なのです。ヒンドゥー教徒であることを否定し、どんな組織に属することも否定し、特定のいかなる教義や信条も否定し、まさにその否定によって自分自身をすっかり不安定にさせること、そのような否定をご存じですか? 未来に何が起こるか関知せずに、既知のものを否定することができますか?
この、虚偽あるいは非本質的なものの否定はクリシュナムルティの終始一貫した姿勢となっています。そこで彼は、例えば、「真理とは何か」と問うかわりに、彼は「何が真理ではないか」と問い、「虚偽を虚偽と見、虚偽の中に真理を見、真理を真理と見よ」と言い、真理を発見するためにはまず、虚偽を虚偽と見抜くことが先決であると強調します。あるいは愛とは何かと問うかわりに、何が愛ではないかと問い、そして「嫉妬は愛の現れですか、そもそもちっぽけなあなたの自我には愛の余地があると思いますか?」と言うのです。
そして私たちがこの虚偽の否定のプロセスをたどり続けていくと、そこにはいい知れない「解放感」とそれに伴う歓喜がわき起こるでしょう。こうして私たちは着実に重荷を降ろし、さわやかな風が吹き渡る「本然の生」へと近づいていくのです。
「方法なき気づき」としての瞑想
クリシュナムルティのいわば「否定的アプローチ」は、彼の言う瞑想についても適用できます。つまり、彼は、「瞑想とは何か」と問うかわりに、「何が瞑想ではないか」と問います。これは、本質的なものに迫るためにそのまわりにこびりついている非本質的なものをまず剥ぎ取るという、一種の整理術でもあるのです。
彼のアプローチが瞑想に対してどう適用されるかをわかりやすく述べるため、かつて精神世界雑誌『フィリ』がまとめた「ニューエイジ用語辞典」に出ていた「クリシュナムルティ」の項の一部をここで取り上げさせていただきます。
……一九二九年、「真理は道なき道である」と追随者たちの前で語り、以降、いかなる導師・教義も真理へ導くものではないということを主張し、世界中で講演活動を行う。一九八六年死去。約束された「救世主」の座を蹴っ飛ばしたため、清廉潔白な印象があり、ニューエイジ界にもファンが多い。でも、すべての(悟りのための)技法を否定したクリシュナムルティとニューエイジって相性悪い気がするんですけど。
これに対して(もしこの解説を読んだら)彼はおそらくこんなふうに言うでしょう。「なるほど、おっしゃるとおり私は方法とか技法といったものを否定しました。が、いわゆる座禅、ヨーガ、TM、ホロトロピックセラピー等々を実践なさることによって、あなた方は現代社会の心理構造を構成している病的な所有欲、支配・権勢欲、あるいは嫉妬・羨望、野心、飽くことなき消費的快楽の追求、体験願望、そしてなによりも陰湿な競争や家庭内暴力など様々な形で現われる暴力性から自由になりましたか? もし少しでも自由になられたのなら、おおいに結構です。私の言うことなど無視してどうかお続けなさい。が、どう見てもあなた方はあまり楽しそうではないですし、心の中に歓喜が沸き上がっているようにも、あるいは仲良く平和に暮らしていらっしゃるようにも思えないのですが、いかがですか?」
クリシュナムルティにとっての瞑想とは、実は右にスケッチしたような現代社会の心理構造を突き抜け、その外に出ることなのです。なぜなら、その中には真の平和はないからです。彼は言います。
瞑想は世俗からの逃避ではない。それは孤立的で自己閉鎖的な活動ではなく、世界とそのあり方を理解することである。社会は衣食住以外には与えるところ少なく、それが与える快楽は大きな悲嘆を伴うのが常である。
瞑想はそのような世界を豁然として離れ去ることであり、人は全的にアウトサイダーでなければならない。そのときこの世は意味を帯び、天と地はその本来の美を不断に開示する。そのとき愛は快楽の影を宿さない。そしてこの瞑想こそは、緊張や矛盾、葛藤、自己満足の追求、力への渇望などから生まれたものではない、全ての行為の源泉である。(『クリシュナムルティの瞑想録』平河出版)
瞑想はそのような世界を豁然として離れ去ることであり、人は全的にアウトサイダーでなければならない。そのときこの世は意味を帯び、天と地はその本来の美を不断に開示する。そのとき愛は快楽の影を宿さない。そしてこの瞑想こそは、緊張や矛盾、葛藤、自己満足の追求、力への渇望などから生まれたものではない、全ての行為の源泉である。(『クリシュナムルティの瞑想録』平河出版)
クリシュナムルティは、現代社会は(心理的に)「腐った卵」あるいは「泥舟」であり、もしその中で窒息したくなければ、あるいは沈没していく船とともに奈落の底に沈みたくなければ、一刻も早くそこから抜け出すしかない、と言います。ですから、まさにこの現代社会の現状をどう見なすかが、クリシュナムルティとの決定的な分かれ目になるのです。「確かに環境・資源問題や政治家の腐敗、教育の荒廃といったものを見るかぎり、おっしゃるように泥舟の様相を呈してはいるが、しかしあちらこちらを修繕すればまだなんとかなる」と言う人は、改革者として泥舟の沈没を必死に食い止めようとするでしょう。そしてクリシュナムルティの言うことは極端すぎると言って、彼から離れていくでしょう。
が、「確かにあなたのおっしゃることには一理ある。沈みつつある泥舟から飛び出す以外、人類の未来はないかもしれない」と思う人は、クリシュナムルティとともに歩み始めることでしょう。そしてその人はまず、泥舟の乗客である当の自分自身をありのままに見つめてみるでしょう。しかもそれを山奥の庵の中でではなく、騒然たる都会の中のオフィスでの人間同士の「関係を鏡にする」ことによっておこなうことが必要であることに気づくでしょう。なぜなら、そこでこそまさに自分たちの本性がなまなましくぶつかりあっているからです。これこそはクリシュナムルティの言う瞑想の唯一の行法なのであり、それを実践していくと、実は泥舟と自分自身とが同じ材料でできているという戦慄すべき事実に直面するでしょう。
ここで注意すべきことは、私たちが生きていくにつれて、とりわけ人生後半にかけて、私たちの内面にはいつの間にか「魂の沼地」とでも言うべきものが出来上がり、そこに無数の「無気味な住人」が住みつくようになるということです。これらの住人は「内なる被抑圧者」と呼ぶこともできるかもしれません。私たちが生きていく中で、無視され、心の隅に追いやられ、出て来ることができずにいる私たちの心の部分です。ユング派の分析家ジェイムズ・ホリスは、その著『ミドル・パッセージ――生きる意味の再発見』(コスモス・ライブラリー)の中で、次のように述べています。なお、「ミドル・パッセージ」とは、中年期における苦悩・惨めさから意味ある人生に向かう途中の通り道のことです。
成人初期の思い込みがくつがえされて、それがわたしたちをしぶしぶミドル・パッセージへと船出させるように、わたしたちが強くねがっているものを失うことは、自我にとって非常に大きな打撃である。そうした幻想の中で最大のもののひとつは、どこかに幸せという名の桃源郷があって、それが発見でき、そこで永遠に暮らせるだろうというものである。残念ながら、それよりもっと多く起きそうなことは、たましいの沼地にはまり込み、そこに住む無数の不気味な住人に悩まされることである。
沼の住人たちとはまず、寂しさ、喪失、悲しみ、疑い、抑うつ、落胆、不安、罪悪感、裏切りなどである。しかし幸いにも自我は、自分でそう思っているような全能の司令官ではない。こころは、意識の支配を超えたところに明確な目的をもっており、わたしたちに課されているのは、この状態を生き抜き、その意味を見いだすことである。たとえば、何かを失って覚える深い悲しみは、経験されたことの価値を認識する機会といえる。経験されたからには、それが完全に失われてしまうことはありえない。それは心の底と思い出の中に保持されて、これからの人生を助け導くものとなる。あるいは疑いを例にとってみよう。必要は発明の母であると言われてきたが、疑いもそうである。疑いはそれが開示されるときは脅威になるかもしれないが、にもかかわらずそれは開くのである。人間理解における大きな進歩は、すべて疑いから生まれた。抑うつでさえ、生き生きとした何かがそれまで「おさえつけられてきた」という、有用なメッセージを伝えているのである。
わたしたちはその沼地から逃げ出すようにではなく、そのぬかるみの中を進み、その先にどんな新しい生の萌芽が待ち受けているか見るよう、招かれているのである。これらの沼地のそれぞれの領域は、現在のこころの状態を表している。もしも勇気を出してそこに乗り出して行くなら、わたしたちはその意味を見出すことができるだろう。ミドル・パッセージの船が沼の中を必死に進んでいるとき、わたしたちは問いかけてみなければならない。「これはわたしにとって何を意味しているのか。わたしのこころは、何を言おうとしているのか。わたしは、それに対してどうすべきなのか」と。
自分の感情の状態に直接向き合い、それらと対話することには勇気がいる。しかし、自分本来の完全性への鍵がそこにある。たましいの沼地には、意味と、意識の領域を広げる招きがあるのである。これを引き受けることは、人生におけるもっとも大きな責任といえる。わたしたちは、たったひとりでその船の舵を握ることしかできない。そしてわたしたちがそれを行なうとき、[それに乗り出す際に感じた]恐怖は、意味によって、威厳によって、目的によってあがなわれるのである。
これから団塊の世代の人々の中には、会社勤めなどから解放され、晩年にかけての意義ある生き方を模索する方が出て来ることでしょうが、そのためにはまず、それまでに内面深くに追いやったまま抱え込んできた様々な「影」の部分と対面し、それらの心の部分から多くのことを学ばねばならなくなるでしょう。もしもそうした影の部分をたくさん抱え込んだまま、それらに耳を貸さずに生き続ければ、せっかくボランティアやその他の活動に関わっても、結局はそれらをそうした活動に持ち込み、かえって混乱を募らせかねないでしょう。あるいは死期が迫ってから、病床で突然今まで抑え込んでいた恨みつらみを一気に爆発させ、見守っている近親者や友人を困惑させたりしかねません。ですから、自分の内面の沼地にどんな住人が棲息しているか、手遅れにならないうちに確認し、彼らの言い分に耳を傾けることがきわめて重要なのです。
私たちはそれぞれ、本来はかけがえのない一個の「全体」なのですが、会社員、生産者、消費者、夫、妻、家族の一員といった「断片」として生きるよう強いられ、それに異義を唱えないかぎりそこそこの生活を保証されるので、若い頃は少しはあったかもしれない反逆心もいつしか影を潜め、自分の「全体性」など少しも視野に入らなくなり、そんなものは哲学者や宗教家といった専門家に任せておけばいいというようになるのです。
チャールズ・タートというトランスパーソナル心理学者は、その『覚醒のメカニズム――グルジェフの教えの心理学的解明』(コスモス・ライブラリー)の中で、個人にとって非本質的な要素から成る人格を「偽りの人格」と呼び、また本来実現されるべきであった人間の潜在可能性を「本質」という言葉で言い表わし、次のように述べています。
ある一つの文化は人々がどうあるべきかについてのそれ自体の考えを持ち、そしてこれらの考えは、ある一個人の独特の潜在可能性をほとんど気に留めないことがしばしばある。……若干だが幸運な人々がいる。彼らの「本質」の願望と才能の多くが、彼らの文化で求められているものと符合しているのである。が、われわれのほとんどにとって、性別にかかわらず、自分の「本質」の多くは否定される。
こうした否定がわれわれの人生をだめにする可能性がある。なぜなら、「本質」はわれわれの生命に関わる部分、真に生きている生命のきらめきだからである。それは、草原、木立、せせらぎ、大地、そして見なれたあらゆる光景の中に見出された光である。偽りの人格がわれわれの生命エネルギーのほぼ全てを使い果たしていくにつれて、光は薄れ、人生は一組の機械的で自動化した習慣と化し、生気のない他の自動人形化した犠牲者たちの群れと一緒にわれわれを気の抜けたように動かし、さらにわれわれの抑鬱と空虚感を強める。グルジェフはそれを実に苛酷に言い表わし、通りすがりにあなたが見かける人々の多くは死んでいると述べた。「本質」がそのエネルギーのあまりにも多くを奪われ、偽りの人格があまりにも機械化し、自動化してしまったので、真の変化の望みがないのだ。これらの人々は機械的な物になり果て、機械的な人生を生き、機械的な死を死ぬべく運命づけられるのである。
こうした否定がわれわれの人生をだめにする可能性がある。なぜなら、「本質」はわれわれの生命に関わる部分、真に生きている生命のきらめきだからである。それは、草原、木立、せせらぎ、大地、そして見なれたあらゆる光景の中に見出された光である。偽りの人格がわれわれの生命エネルギーのほぼ全てを使い果たしていくにつれて、光は薄れ、人生は一組の機械的で自動化した習慣と化し、生気のない他の自動人形化した犠牲者たちの群れと一緒にわれわれを気の抜けたように動かし、さらにわれわれの抑鬱と空虚感を強める。グルジェフはそれを実に苛酷に言い表わし、通りすがりにあなたが見かける人々の多くは死んでいると述べた。「本質」がそのエネルギーのあまりにも多くを奪われ、偽りの人格があまりにも機械化し、自動化してしまったので、真の変化の望みがないのだ。これらの人々は機械的な物になり果て、機械的な人生を生き、機械的な死を死ぬべく運命づけられるのである。
こうした過酷な現実に直面し、それから抜け出すべく人生の意味を再発見するためにも、山奥の道場ではなく、日常生活を最高の道場として活用すべきなのです。そしてその道場で自分自身の内面の混乱、醜悪さに気づくのに特別な瞑想の方式など不要なのではないか、とクリシュナムルティは言うのです。自分の日常生活の中でこそ私たちは自分の正体をさらけ出しているのであり、ゆえにそれから目をそらさず、正直にそれを見つめることが、クリシュナムルティの言う瞑想の基本なのです。かくして彼は次のように言います。
瞑想は生と離れて別にあるものではなく、それはまさに生の精髄であり、日々の生活の真髄である。教会の鐘の音、妻と連れ立って過ぎ行く農夫の笑い声、あるいはまた通りすがりの少女が乗った自転車のベルの音──瞑想が開示するのはそのひとつひとつの断片ではなく、そうした生の全体なのである。(クリシュナムルティの瞑想録』)
要約するなら、指導者、権威に依存せず、自分自身の偏らない目でものごとを観察し、それによって気づき、理解したことをありのままに伝えること、真理と自分との間にいかなる仲介もはさませないこと、真理の発見にとって不要なすべてのもの(形骸化した伝統、組織、形式、儀式、寺院、私は真理を体現していると自称するグル、等々)を一掃し、懐疑を傾けて虚偽を否定し、それによって虚偽に立脚した社会の心理構造の外に出、そして歓喜に満ちた「本然の生」を生きること──その全体が、クリシュナムルティによって示されたものとしての瞑想であり、未曾有の危機に直面している人類に残された数少ない活路のひとつだということです。
「フォーカシング」という、静かに、心に感じられた「実感」に触れ、そこから意味を見いだす方法として知られ、カウンセリングなどで利用されている技法があります。その研究・実践家で、現在「円座禅」というフォーカシング技法を開発中の土江正司さんは、この秋に刊行予定の『心の天気』(コスモス・ライブラリー)の末尾で次のように述べています。
円座禅も出会いの場です。しかし人生にはもっと大事な出会いがあります。それは家庭をはじめとする身近な人間関係という出会いです。私は二十五歳の時インドに渡り、ヨーガの師(グル)に巡り会い、その家の十二番目の家族として迎え入れられ半年間過ごしたのですが、日本への帰り際にグルがこう語ってくれました。
「息子よ。ヨーガの修行は山や森に入って孤独に行うものではない。本当の修行は家庭の中にある。」
私はこの言葉の真実性を疑ったことがありません。この言葉に巡り会うための渡印だったのだ改めて思い返すことができます。
円座禅が森や山に入ることに相当することだとすると、それは身近な人間関係という最高の出会いの場に帰るための準備にすぎません。どうか円座禅で培った洞察の力を、身近な人たちへの洞察的理解とそれに基づく洞察的世話として結実させていただきたいと願ってやみません。
人類の未来
世界の紛争現場で長年「平和建設」活動に携わってきたアメリカ人女性ルイーズ・ダイヤモンドは、その著『平和への勇気――家庭から始まる平和建設への道』 (コスモス・ライブラリー)の中で、次のように述べています。
私は、人類がある特定の進化周期の終点に達し、別の周期に入ったと信じています。これがたまたま新しいミレニアムの始まりと一致しており、必然的に大変動と混乱の時期を伴うということは、私にとって完全に意味をなすのです。
私たちは何世紀もの間、還元主義の知的・体系的世界観のなかで生きてきました。宇宙をその構成部分へと還元し、その働きを機械論的に理解しようと努めるその世界観は、当然ながら直線的で、合理的で、問題志向的思考様式を、また社会的関係においては、区画化された、分離的な、支配型のアプローチを偏愛します。
率直に言えば、この世界観、およびそれを維持し促進するために確立されたすべての制度は、そのサイクルの最期を迎えたのです。現実の性質または自然法則と調和していない生き方を押し付けようとするこの世界観は、それ自体の消滅の種子を常に内包し続けてきたのであり、そしてそれらの種子が今熟したのです。
一方、新たなサイクル、私たちが一体であるという認識から生ずるサイクルが始まりつつあります。関係的で、直感的で、機会志向的思考様式を、また社会的関係に対するコミュニティ志向的、相互結合的、パートナーシップ型のアプローチを良しとするこの新しいあり方は、私たちにとって明らかになりつつある普遍的な真実についての理解の上に築かれています。すなわち、私たちは事物を最小の物質片に還元することはできない。物質は意味と動きを持ったエネルギーである。生命は静止してはいない。それは流れである。私たちはばらばらではない。私たちは全体である。もし私たちが他人を虐げれば、私たちは自分を虐げる、という。
この世界の真にホリスティックな性質をますます多くの人々が認識するにつれて、地球上のあちこちで広範囲にわたる意識の転換が起こりつつあります。市民権運動、女性運動、ますます高まる環境意識、東洋や先住民哲学への関心、主流になりつつあるホリスティックな医学的アプローチ、職場での個人参加型チームワークおよび士気の役割への注目、新しい物理学など、様々な仕方で表れているこの意識の変容は、二十一世紀からさらにその先へと私たちを導く新しい波なのです。
古いシステムが崩壊し、消え去ろうとしている今まさに、私たちのうちの先駆者たちが、私たちは一体であるという真実を尊重する、新たな生き方と力の合わせ方を創り出しつつあります。私はたまたま、平和建設はこの波の最前部にあり、その先駆者たちは新しい時代の最も偉大な闘士であり擁護者であり、今後もそうあり続けるだろうと信じています。
私たちは何世紀もの間、還元主義の知的・体系的世界観のなかで生きてきました。宇宙をその構成部分へと還元し、その働きを機械論的に理解しようと努めるその世界観は、当然ながら直線的で、合理的で、問題志向的思考様式を、また社会的関係においては、区画化された、分離的な、支配型のアプローチを偏愛します。
率直に言えば、この世界観、およびそれを維持し促進するために確立されたすべての制度は、そのサイクルの最期を迎えたのです。現実の性質または自然法則と調和していない生き方を押し付けようとするこの世界観は、それ自体の消滅の種子を常に内包し続けてきたのであり、そしてそれらの種子が今熟したのです。
一方、新たなサイクル、私たちが一体であるという認識から生ずるサイクルが始まりつつあります。関係的で、直感的で、機会志向的思考様式を、また社会的関係に対するコミュニティ志向的、相互結合的、パートナーシップ型のアプローチを良しとするこの新しいあり方は、私たちにとって明らかになりつつある普遍的な真実についての理解の上に築かれています。すなわち、私たちは事物を最小の物質片に還元することはできない。物質は意味と動きを持ったエネルギーである。生命は静止してはいない。それは流れである。私たちはばらばらではない。私たちは全体である。もし私たちが他人を虐げれば、私たちは自分を虐げる、という。
この世界の真にホリスティックな性質をますます多くの人々が認識するにつれて、地球上のあちこちで広範囲にわたる意識の転換が起こりつつあります。市民権運動、女性運動、ますます高まる環境意識、東洋や先住民哲学への関心、主流になりつつあるホリスティックな医学的アプローチ、職場での個人参加型チームワークおよび士気の役割への注目、新しい物理学など、様々な仕方で表れているこの意識の変容は、二十一世紀からさらにその先へと私たちを導く新しい波なのです。
古いシステムが崩壊し、消え去ろうとしている今まさに、私たちのうちの先駆者たちが、私たちは一体であるという真実を尊重する、新たな生き方と力の合わせ方を創り出しつつあります。私はたまたま、平和建設はこの波の最前部にあり、その先駆者たちは新しい時代の最も偉大な闘士であり擁護者であり、今後もそうあり続けるだろうと信じています。
そしてこの潮流の中で、難民問題で活躍された緒方貞子さんに代表されるように女性が重要な役を果たしているというのは、人間精神の荒廃を招いてきた「左脳一辺倒」の計算的思考に基づいた生き方を是正するために「右脳」を活性化することが急務となりつつあることと考え合わせて、きわめて注目すべきことだと思います。
「来るべき人類」――ホイットマンの言葉
参考までに、人類の未来についての、ある予言的な言葉をご紹介しておきます。これは、一九〇一年に出版された、意識進化に関する先駆的な研究書『宇宙意識』中のウオルト・ホイットマンについての章に出ているものです。それによると、ある日ホイットマンは著者のバックに次のように言ったそうです。「結局、どんな特別な自然の風景も――つまりアルプスもナイヤガラも、ヨセミテも、その他の何でも、ごく普通の日没や日の出、天と地、平凡な樹や草などより壮大でも美麗でもない――これが大きな教訓ですね。」これに対してバックは次のように述べています。「もし適切に理解されれば、この言葉は彼の制作と生涯との中心的な教えを示唆するものと私は信ずる――すなわち、通常のものこそはすべてを通じての最も壮大なるものであること、いかなる方面でも例外的なものは通常のものよりも立派でも善くも美しくもないこと、そして、真に欠けていることは、我々が我々の現在もたぬものをもつことではなく、我々のすべてがもっているものを見るために我々の眼を、感じるために我々の心を、開いておくことである、ということである。」そしてバックは、ホイットマンの次の言葉を「来るべき人類を予言するもののように思われる」として紹介しています。
適切に生れ、育てられ、屋内、屋外を問わず、調和と活動性とを有する正しい状態において生長した民族は、たぶん、それらの状態から、またそれらの状態のなかで、単に生きることだけで十分であると知るであろう――そしてかれらの空、空気、水、樹木、その他との関係において、また無数のありふれた出来事との関係において、また「生」の事実そのものにおいて幸福を発見し、達成するであろう――それは夜となく昼となく健全な陶酔にみたされた「実在」とともにある幸福であり、その陶酔は、富、娯楽が与えうる悦楽のみならず、喜ばしき知性、学識、あるいは芸術の感性が与えうるあらゆる悦楽をも超えたものである。
これこそはまさに「生のアーティスト」であるクリシュナムルティが実現し、その中で終生生き続けた境地であり、もしホイットマンがクリシュナムルティに会っていたら、あるいは彼の著作を読んでいたら、間違いなく彼を新しい人類の一人として認めたことでしょう。なぜならクリシュナムルティもまた、私たちに「生」を愛せよと命じているからです。そしてそれこそが、初期トークにおいてだけでなく、晩年に至るまで、彼が一貫して私たちに訴え続けたことなのです。それは、彼が若い頃に書いた詩の中に生き生きと脈打っています。
〈生〉を愛せ、
そうすれば汝の愛はいかなる腐敗も知ることはないであろう。
〈生〉を愛せ、
そうすれば汝の判断は汝を支持するであろう。
〈生〉を愛せ、
そうすれば汝は理解の正道を踏み外すことはないであろう。
(「生の詩」)
〈汝〉の眼の中に
旋風が、
微風が、
聖なるヒマヴァットが、
平原が、
幸福の谷が、
そして青空が――
あらゆるものが〈汝〉の中にある。
(「不滅の友」)
千の視野を持つ千の眼、
千の愛を持つ千の心、
それが私だ。
清き川も濁った川も
受け入れ、
頓着しない海のように、
そのように私はある。
山間の湖は深く、
泉の水は澄んでいる、
そしてわが愛は事物の隠れた源泉だ。
ああ、ここへ来てわが愛を味わえ、
そうすれば、涼しい黄昏時に
蓮が誕生するように、
君は自身の心の秘密の願望を見つけるだろう。
ジャスミンの香りが夜気に充満し、
深い森の奥から
過ぎ行く日の叫びが届く。
わが愛する〈生〉は重荷を下ろして軽やかだ、
それを達成することが究極の自由だ。
(「生の詩」)
付記
今回はクリシュナムルティのことをご存知ない方のために、彼がどのような歩みをたどり、人間、人生、社会、世界をどのように見ていたのか、革命や戦争についてどう考えていたのかといったことを中心に述べさせていただきました。実は彼は教育に特別な関心を持ち、イギリスとアメリカに各一校、インドに六校ほど彼の名を冠した学校があり、生前はそれらを定期的に訪問して教師や生徒たちと多くの討論をし、彼らに向かって講話をおこないました。これについては今回はご紹介できませんでしたので、もし関心のある方は以下の邦訳書をお読みいただければと思います。
■クリシュナムルティ自身の著作
『阿羅漢道』 今武平訳 一九二四年(大正十四年)
『自己変革の方法』 十菱珠樹訳 霞ヶ関書房 一九七〇年
『自由への道』 菊川忠夫訳 霞ヶ関書房 一九七四年
『道徳教育を超えて』 菊川忠夫他訳 霞ヶ関書房 一九七七年
『英知の探求』 勝又俊明訳 たま出版 一九八〇年
『自我の終焉』 根木宏他訳 篠崎書林 一九八〇年
『暴力からの解放』 勝又俊明訳 たま出版 一九八二年
『クリシュナムルティの瞑想録』 大野純一訳 平河出版社 一九八二年
『クリシュナムルティの日記』 宮内勝典訳 めるくまーる社 一九八三年
『真理の種子』 大野純一他訳 めるくまーる社 一九八四年
『生と覚醒のコメンタリー・1?4巻』 大野純一訳 春秋社 一九八四年
『クリシュナムルティの神秘体験』 中田周作訳 おおえまさのり監訳 めるくまーる社 一九八四年
『生の全体性』 大野純一訳 平河出版社 一九八六年
『英知の教育』 大野純一訳 春秋社 一九八八年
『未来の生』 大野純一訳 春秋社 一九八九年
『学びと英知の始まり』大野純一訳 春秋社 一九九一年年
『思考のネットワーク』 渡辺充訳 JCA出版 一九九一年
『生の全変容』 大野純一訳 春秋社、一九九二年
『瞑想と自然』 大野純一訳 一九九三年
『自由とは何か』 大野純一訳 春秋社 一九九四年
『子供たちとの対話』 藤仲孝司訳 平河出版社 一九九二年
『人類の未来』 渡辺充訳 JCA出版 一九九三年
『ザーネンのクリシュナムルティ』 ギーブル恭子訳 平河出版社 一九九四年
『私は何も信じない││クリシュナムルティ対談集』 大野純一編訳 コスモス・ライブラリー 一九九六年
『恐怖なしに生きる』 有為エンジェル訳 平河出版社 一九九七年
『学校への手紙』 古庄高訳 UNIO 一九九七年
『大師のみ足のもとに』 田中恵美子訳 竜王文庫 一九九八年
『瞑想』 中川吉晴訳 星雲社 一九九八年
『あなたは世界だ』 竹渕智子訳 UNIO 一九九八年
『クリシュナムルティの瞑想録』〔文庫本〕 大野純一訳 サンマーク出版 一九九八年
『私は何も信じない││クリシュナムルティ対談集』〔新装版〕 大野純一編訳 コスモス・ライブラリー二〇〇〇年
『クリシュナムルティの教育・人生論││心理的アウトサイダーとしての新しい人間の可能性』 大野純一著編訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇〇年
『白い炎││クリシュナムルティ初期トーク集』 大野純一著編訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇三年
『知恵のめざめ――悲しみが花開いて終わるとき』 藤仲孝司+小早川詔訳 UNIO 二〇〇三年
『自由と反逆││クリシュナムルティ・トーク集』 大野龍一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇四年
『花のように生きる――生の完全性』 横山信英+藤仲孝司訳 UNIO 二〇〇五年
『人生をどう生きますか?』大野龍一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇五年
『しなやかに生きるために――若い女性への手紙』大野純一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇五年
『生と出会う――社会から退却せずに、あなたの道を見つけるための教え』 大野龍一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇五年
『クリシュナムルティの教育原論――心の砂漠化を防ぐために』 大野純一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇七年
『既知からの自由』 大野龍一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇七年
『変化への挑戦――クリシュナムルティの生涯と教え』(DVDブック)柳川晃緒訳 ココスモス・ライブラリー 二〇〇八年
■クリシュナムルティ関連文献(伝記その他)
『クリシュナムルティの世界』 大野純一著編訳 コスモス・ライブラリー 一九九七年
『グルジェフとクリシュナムルティ││エソテリック心理学入門』 ハリー・ベンジャミン著 大野純一訳 コスモス・ライブラリー 一九九八年
『リシバレーの日々――葛藤を超えた生活を求めて』 菅野恭子著 文芸社 二〇〇三年
『片隅からの自由││クリシュナムルティに学ぶ』 大野純一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇四年
『クリシュナムルティとは誰だったのか││その内面のミステリー』 アリエル・サナト著 大野純一+大野龍一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇四年
『クリシュナムルティの生と死』 メアリー・ルティエンス著 大野純一訳 コスモス・ライブラリー 二〇〇七年)
『新しい精神世界を求めて――ドペシュワルカールの「クリシュナムルティ論」を読む』 稲瀬吉雄著 コスモス・ライブラリー 二〇〇八年