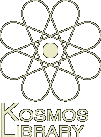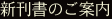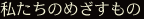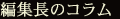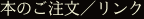第9回
****************
ウスペンスキーの思考の出発点は、〈秘教(エソテリシズム)〉の実在性への確信である。これを表明した時点で、彼は西洋近代の知の体系に別れを告げている。彼はこの「秘教」という観点から、現代思想の信奉するさまざまな「幻想」を暴き立てる。その一つが「進化」という概念である。
この論文は元々単独の作品として出版されたもので、ウスペンスキーの処女作にあたる。これによって彼は「四次元数学者」の異名を取ることになった。しかし彼の手法は厳密な数学者のそれではない。彼の「心理学的手法」は、先駆者C・H・ヒントンに倣ったアナロジー(類比)を駆使する。
秘教の観念は、必然的に〈超人〉の観念を含んでいる。ウスペンスキーの説く超人は、ニーチェのそれをより「ありのままに」述べたものである。ニーチェの超人にはかなりドラマチックな空想が混じっているが、ウスペンスキーはその本質のみを抽出して語る。
福音書の教えについて、秘教的な観点から解釈した斬新な試み。当時、このアイデアがあまりにも大胆すぎたために、ロシア正教会の逆鱗に触れ、本章を収録していたがために『新しい宇宙像』がロシアで出版できなかったといういわくつきの論文である。
オカルト研究家にとっての必須アイテムである「タロット」の紹介と解説。第一部でタロットの概略、歴史、それが含む意味について述べ、第二部では「大アルカナ」のそれぞれのカードをテーマに断章的な物語が語られる。一時期タロットの研究に没頭していたというウスペンスキーの洞察が凝縮された作品である。
今では西洋や日本でもヨガに関するあらゆる知識を比較的簡単に手に入れることができるが、ヨガの本質をこれほど的確に、しかも簡潔にまとめた論文はいまだ類を見ない。ヨガの流派を一通り論じた後で、最後に〈システム〉=〈第四の道〉の存在を仄めかしている。
前半は夢についてのウスペンスキー自身の実験の報告で、後半は催眠術を「暗示」が果たす重大な影響という観点から論じている。冒頭の注釈で精神分析を手厳しく批判しているが、後に彼の教えを受けた人々の中には精神分析医のキャリアを経た者が少なくない。
コリン・ウィルソンが「ウスペンスキーが書いた文章の中で最も興味深いもの」と述べたこの章は、『ターシャム・オルガヌム』を執筆していたときの著者の内面世界についてのドキュメントとして読むとさらに興味深さを増す。後にオルダス・ハクスレーが彼自身の「体験」に基づいて『知覚の扉』という有名な作品を書くことになるが、彼がウスペンスキーのこの文章を読み、その影響を受けていたことはほぼ確実であろう。
後に同名のタイトルで出版された有名な本とはまったく別の作品で、ウスペンスキーがグルジェフに出会う前の世界旅行で体験した出来事を綴ったもの。場所ごとに記された六つの断章(スケッチ)からなり、いずれも若きウスペンスキーの繊細で詩的な感受性に溢れた読み物である。
本書全体の白眉とも言えるこの章は、第一部で相対性理論までの現代物理学の発展を概説し、第二部でウスペンスキーのまったくオリジナルな宇宙像を解説する。存在のリアリティ(実相)は六次元(空間の三次元プラス時間の三次元)であるとするウスペンスキーの次元論はきわめて独自な発想であるが、グルジェフも後にその価値を認めているところから見て、単なる奇想とも思われない。ここに含まれている材料は、今後、さらに練り直され、発展の余地があると考えられる。既存の科学的概念を破壊する潜在力を秘め、未来への大きな可能性を孕んだ論文である。
前半では、ウスペンスキー思想の柱であると言ってもいい「永劫回帰eternal recurrence」を解説し、後半は秘教の観点から見た社会秩序のあり方をマヌ法典に基づいて考察する。永劫回帰のテーマは終生ウスペンスキーに宿命的に付き纏った。弟子のロドニー・コリンは、ウスペンスキーの全生涯は永劫回帰のサイクルを脱出することに向けられていたという趣旨の発言をしているが、あながち的外れでもあるまい。 マヌ法典の唱える「カースト制」を理想的な社会秩序とみなし、革命前のロシアがその理想に近かったと語るウスペンスキーは、文章の端々に、革命によって「アウトカースト」の身分にされた彼自身のニヒリスティックな時代認識を漂わせている。
タイトルだけ見ると、一九六〇年代ヒッピー世代によるフリー・セックス運動の先駆けのような内容を連想させるが、実際の中身はむしろ保守的と言ってよい。セックスをノーマルなもの、下等なもの(インフラ・セックス)、高等なもの(スープラ・セックス)に分け、異常で倒錯した下等な性愛を退け、ノーマルな性愛を通してのみ性エネルギーの変容としての高等な性愛に達しうるのだと述べる。同様の主張は『奇蹟を求めて』でグルジェフの口を通しても語られている。また、恋愛とそれを支配する途方もない力についての記述は、『ターシャム・オルガヌム』の「愛と死」についての章と併せて読むと興味深い。