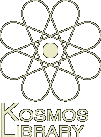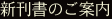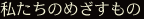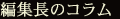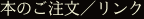第10回
残暑と言うよりは、このままずっと暑い日が続くのではないかと思われるほどの暑さが続いておりますが、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
編集者は現在、イギリスにおけるロジャーズ研究の第一人者の一人、ブライアン・ソーン先生著『カール・ロジャーズ』の刊行を準備中です。この本は200ページほどの分量ですが、「カウンセリングの神様」ロジャーズの生涯、理論、臨床実践、ロジャーズ批判とそれに対する反論、そしてロジャーズの仕事が与えた広範な影響を手際よくまとめたレベルの高い入門書で、付論としてさらに、今回監修を引き受けてくださった日本トランスパーソナル学会会長でもある諸富祥彦千葉大学教育学部助教授が日本におけるロジャーズ派の重鎮畠瀬稔先生とおこなった「ロジャーズをめぐる対話」を巻末に収録してありますので、カウンセリングを学んだり、実践しておられる方々にきっとお役に立つと拝察しております。ロジャーズ生誕100年を迎えるという今年このような入門書を刊行できることを、編集者として喜んでおります。
また、まだ現段階でははっきりした内容は言えませんが、フォーカシング関係書の出版も企画しております。小社刊『やさしいフォーカシング──自分でできるこころの処方』は静かではありますが、着実に読まれ続けており、各方面の方々のお役に立っているようでほっとしております。
◇ ◇ ◇ ◇
なお、私事にわたって恐縮ですが、現在「サングラハ」(このホームページの管理人でおなじみの重田さんが事務局長をしておられる団体の機関誌)9月号が「代表的日本人」をテーマとした特集を組むとのことで、それに寄稿する原稿を準備中です。「代表的日本人」というとすぐ内村鑑三を思い出されると思います。岩波文庫から出ているこの本で、著者は西郷隆盛(新日本の創設者)、上杉鷹山(封建領主)、二宮尊徳(農民聖者)、中江藤樹(村の先生)、日蓮上人(仏僧)を取り上げています。
そもそも「代表的日本人」という場合、その選定基準はどのようなものなのか? それによって様々な人物像が浮かび上がってくるのではないでしょうか? 私見では、この日本という国に住んでいた(あるいは住んでいる)人で、私たちが意識的無意識的に抱いている人間としての望ましい発達可能性を非常に高い程度まで実現した人というのが、一つの基準なのではないかと拝察します。つまり、この国の気候風土、風習、政治的・経済的・社会的条件や特殊性を背景にしつつ、様々な制約条件の下で、最高度に自己実現を遂げ、さらには自己超越まで果たした人は、私たちが自分では無理なのだが、そうありたかったという切望を満たしてくれるような存在なのだと思います。さしあたりこの基準に照らしてみて、読者の皆様はどんな人物を思い浮かべますか?
編集者は最初、浅学非才ゆえとてもこのようなテーマで何か書くことはできそうに ないとあきらめかけていたのですが、ふと「近藤富蔵」という名が浮かび上がってきました。柳田國男が『島の人生』(創元社、昭和26年)で一部紹介しているので、民俗学や離島の歴史に関心がある方はご存じだと思うのですが、『八丈実記』の著者として知られている人です。父親は蝦夷地探検で有名な近藤重蔵ですが、若い頃いろいろ経緯があって文政9年(1826年)に江戸槍ケ崎で一家7人殺しを起こし、そのために八丈島に流罪になりました。富蔵はそこで60年余り過ごし、明治20年に83歳で死去しました。そして八丈島での長い生活のかたわら書き続けたものをまとめたものが『八丈実記』なのです。これは緑地社という出版社の社長、小林秀雄さんという方(文芸評論家の小林秀雄とは別人です)の手で昭和39年から51年(1964〜76年)にかけて7巻本で刊行されており、編集者もこの本のことを評論家の小林秀雄のエッセイで知り、全部取り揃えたのです。いつか時間をとって読んでみたいと思っていたのですが、結局今日までまともに読まずにきてしまいました。これからもまとまった時間があるかどうかわかりませんが、一通り目次に目を通しているだけでなんとも言えないヒーリング効果があるのです。
今回はこの本の関連資料として入手した「海外雄飛豪快伝」から、ちょっと面白い文章をご紹介したいと思います。昭和4年に当時の平凡社から刊行された『伊藤痴遊全集』の第11〜12巻を構成しているもので、その中で近藤重蔵の蝦夷探検を中心にした活躍の様子とその後見舞われた息子の殺傷事件の顛末などが講談調で語られており、読み物として実に面白いのです(その分、資料価値という点では相当割り引きしなければならないかもしれません)。その語りの随所になかなか辛辣な人間観察がちりばめられており、今読んでも思わずウーンとうならされてしまいます。それでちょっとそのいくつかをご紹介したくなったのです(ほぼ現代仮名遣いにしてあります)。
[重蔵の性格について]
頼朝の募りに応じて真っ先に馳せつけたのが近藤國平というもので、これが重蔵の祖先であった。されば、瀧之川(滝野川)という土地は、重蔵の身にとって深い因縁があり、近藤家のためには忘れ難き記念の地である。
弓奉行を罷められ、江戸へ帰って来ても、小普請入では生き甲斐のない日を送るのだから、重蔵の気性としてはそれに堪えられるはずがない。いかに焦っても、どれほどもがいても、相手が幕府の役人ではどうすることもできなかった。幕府の方でも、こうした人物はあまり好いておらないのだ。充分に実力を持っている人でも、それを深く隠して、表面には何も知らぬといった風を粧い、いっさい他に対してはその覇気を包んで、何事も唯々諾々、御無理御尤もでいる人が多く喜ばれているのだから、重蔵のごときはっきりした人物は、どうしても容れられないのが、当時としてはあるいは当然であったかもしれない。
[人心の腐敗堕落について]
世間というものは、多く粉飾によって保たれ、人間というものには皆表裏がある。清浄無垢、生れたままの純真は、育ってゆくに従い、何時かしら虚偽に落ちるものだ。
昨今の世態人情は殊にそれの甚だしきものがあり、油断も隙もならぬ恐ろしい世になってしまった。多くの人の代表者たる議員に正しい者が稀有で、大概はその場限りの塗り合せで、胡麻化している者ばかりだから驚く。人民の代表となって良い事をするというのではなく、その肩書を利用して自分のためを謀るのであって、その他には何も考えておらぬ。そうした人を推し上げる者の方でも、その人を利用して何かやってみたいと思って、選挙に駆け歩くのであるから、その結果は想像しうるのである。叩頭(こうとう)、買収、馳走、因縁──これだけのことを除いて、本当の信認投票で選ばれて来る議員が、果して幾らあるだろう。また、投票する方の人が、よく人物を見立てて、誤りなき公正の一票を行使する者が幾らあるだろう。考えてみると、莫迦(ばか)らしくなる。
教育家に、教育家らしい心を持つ人がどれほど在るか、赤裸々にして見て、真の教育家といわれる者が今の教育家中に、果して幾人あるであろうか。その内面に入って見ると、驚くべき腐敗で、とても本当の教育家らしい者は、暁天(あかつき)の星と一般、まことに心細いほどである。我らは、こうした教育家によって、子供を託して
置くのである。
末世(まっせ)の坊主は、葬式の事務員たるにすぎぬが、それにしても、霊界の人として、多少は敬意を払われているのだ。その坊主なるものの多くは、みな破戒堕落の輩(やから)であって、口には道理(もっとも)らしいことを吐(ぬ)かしても、その行うところは俗人も及ばざるほどに汚いものである。
貰うことは知っているが、与えることは知らない、人を苦しめることはよく行(や)るが、人に恵むことはさらに(滅多に)しない、というのが末世の坊主の常例(つね)であって、物欲と色欲の他に何物も無い、という状態である。大震災の当時、寺地を利用して悪銭を貪り、災後の借地人を虐待して法外の利得を謀ったのは、坊主の地主に多かった。佛(ほとけ)に仕える身で高利貸を行ったり、貸家業を営む者は、今でも少なからず在る。檀家を虐めて金品の寄(喜)捨を仰ぎ、それによって一身の栄耀(えいよう)を謀り、あるいは、寺に伝わる重代の者を売って、女狂いをする者は、ほとんど軒並といってよいくらいだ。
寺院によって衣食している坊主が、代議士になるのだといってさかんに蠢動(しゅんどう)したのは、昨年のことであった。霊界に在ってその人らしい行いのできぬ者 が、政界へ乗出して何事をするつもりであるか。実に苦々しいことである。
徳川の末世に及んで、坊主の堕落は実に甚だしきものがあった。阿部伊勢守(あべいせのかみ)や大塩平八郎の手によって一通りは叩きつけられたけれども、これとても普遍的に行われたのではなく、江戸と大阪の一部に留まり、ほんの申分的(もうしわけてき)に一掃除されたにすぎなかった。
[政治の醜態について]
人に物を送ってその歓心を求むるとか、あるいは金の力で役人の心を動かすとか、こうした汚いやり方を平気でする者は昔から多く在って、それがために世間の問題になることも幾たびか繰返されているが、まことに嘆かわしい次第である。
議会政治が行われるようになってからは、一層それがはげしくなったように思われる。そうした汚いことによって政治が行われてはならぬということが、議会政治の起った原因の一つであるのに、かえってこれがひどくなったなぞは、何という皮肉であろう。
昨今では、賄賂を取る人が働きのある者として迎えられ、それを不義の行為として斥(しりぞ)ける者は、反対(あべこべ)に、融通の利かぬ者として、その迂闊(うかつ)を嘲笑されるようになってきた。道義の頽廃、人心の堕落、実に驚くべきものがある。
旧幕の末になって、賄賂の横行したことは、正しい歴史にもこれを諷(風刺)してあるくらいで、故老の書残したものを視ると、上は老中の職に在る者から、下は獄卒の末輩(まつはい)に至るまで、ほとんどこれに触れぬ者はないほどで、時に清廉謹直(せいれんきんちょく)の人もあるが、それは暁天(あかつき)の星に等しく、極めて少ないものであった。
[アイヌ人の人情風俗について(蝦夷通の最上徳内という人物が上司の質問に答えたもの)]
「蝦夷人の食物は、多くどういうものであろうか」
「米の無いために、大概は魚や獣の肉を食しているもののようでござる」
「米に代るものは何か」
「芋の類でしょう」
「醤油や砂糖はどうする」
「醤油の代りには塩を用いているが、砂糖は無い」
「野菜物の汁から甘味を搾ることは、心得ている。いずれにしても、塩辛いものをかえって喜んでいる。彼らの健康は、それがために強い」
「酒はどうじゃ」
「有ります」
「みな飲んでいるか」
「酒は、女子に至るまで、みな好んで飲むが、酋長(おてな)の家族以外は容易に飲むことを得ないので、極くわずかの量に満足するより他はない」
「つまり、酒を多く造らぬという訳じゃな」
「左様う」
「米が取れぬとすれば、芋のごときものから搾られるのであろう」
「それであるから、酒を珍重することは想像も及ばぬほどで、蝦夷人を引付けるには酒が第一でござる」
「男女の風儀はどうであろうか」
「これは、よほど厳格なもので、内地の人も遠く及ばぬほどでござる」
「ふふーむ、それは感心じゃ」
「すべて、冠婚葬祭は礼儀正しく行われているのが蝦夷人でござる」
「義が堅いのじゃな」
「義を重んじ、約(約束)を守ることは、内地の武士も及ばぬほどでござる」
「学問は……」
「有りませぬ……」
「学問が無くて、義を重んじ、約を守ることの堅い、というのは、どういう訳であろうか」
「生れたままの人間は、みな義を重んじ、約を堅く守るが、仲間が多く殖えるに従って、その心が乱れてゆく。そこで、学問の力を借りることにもなるのでござろう。彼らには学問の力を借りるほど、その心は乱れておらぬ」
「人間はそういうものかな」
「仲間が少ないから、力づくで物を争うこともなく、その日の計はその日に立てる。
翌日のことは翌日にすればよい、という風で、まことに簡単な生活(くらし)に安んじているから、義に反(そむ)き、約を違(たが)える、というようなこともせず、悠々としてその日を送っているのでござる」
「それは面白いことじゃ」
「その代り、怠け者が多く、勤勉なる者は少ない」
それまでは黙って聞いていた重蔵が、膝を進めて、
「食うて生きている、というだけじゃ、ハッハ……」
と哄笑一番したので、他の者も思わず笑い出した。
「近藤氏の言われる通り、彼らは食うて生きているだけで満足しているのじゃが、目まぐるしい争闘のうちに日を送る人も、やはり食うて生きているだけのことではある まいか」
徳内はこう言って重蔵の顔を見た。
[役人根性について]
昔も今もさらに変らないのが、役人根性である。二た言目には役人風を吹かして、威張り散らすのを、まるで役得のごとく心得、規則を楯に尊大振って、人民を塵芥(ちりあくた)のように取扱う奴があったものだ。
昨今の時世になっても、なおかつ少なからずそうした役人のある所から考えてみると、武家政治の時代にはどれほど威張ったものか、判らない。
有體(ありてい)に言えば、日本くらい役人の威張る国は世界のどこにもあるまい、と思うほど役人の国である。
官庁の役人ばかりでなく、会社銀行にいる者までが、何となく反っ繰り返って、鼻持ちのならぬ輩(はい)が、なかなかに多い。
若い人たちが、学校にいる時から役人を心がけるのも、実は威張りたいが勢一ぱい(精一杯)の望みで、それが外れたら会社銀行へ落込んでゆこう、というような者が多くいるのだから、実に驚き入る。
役人になって威張りたいという間違った考えと、役人は偉いものだから、無理なことでもその命令には服従すべきものだという奴隷根性と、この二つを日本人の頭から取除いてしまわねば、将来の日本国は大きくなりえぬであろう。
旧幕時代の役人が無性に威張ったのは、支那の真似をしたのと、もう一つは武家に無上の権力を与えておいたためであった。これが長く続いていたので、習い性となって今日に至ったものと見るべきである。
ちょっと用事があって人民を呼出すにしても、罪人扱いにしなければ何となく虫の収まらぬ、といったやり方であるから、肝玉(きもったま)の太いものは、どうかするとそれに反抗したくなるのは、尤も千万である。
上司は下僚に対しては一視同仁でなければならぬ。いかなる場合にも依怙偏頗(えこへんぱ)の沙汰など決して為すべきでものではない。けれども実際においては、何時の世にもそれが行われているのだから、実に嘆かわしい次第である。
武家という階級が町人百姓に対して非常な権力を持っていた上に、役人という役人はすべて、武家の占有するところになっていたから、その威張り方は非常なものであった。
武家であり、かつ役人であるということが彼らの間にどれほど幅の利いたものか、それは想像も及ばぬ。
今でいうところの官尊民卑、その風習はまだ容易に除かれず、国民の代表者たる議院の席にある者でさえ役人になりたがることは、ますますひどくなってきた。
大臣は格別として、その以下の役人になった議員が閣下と言われて喜んでいるといった情けない状態は、何時の世になったら無くなるのであろうか。
莫迦(ばか)な国民は閣下と言って、そうした人に近付くのを無上の喜びと心得て いるのも、少なからず在るほどだ。
この風習は武家政治の名残であって、まことに見苦しいことであり、ひどい弊害がこれに伴っていることに、早く気付いてほしい、と常に思っているが、ナカナカその夢は覚めそうに思えぬ。
幕末の太平に武家の人々が役人になることを楽しんだのも一つの時代相と観てよかろう。役人になれば、その肩書によって、無役の武家に対して非常に威張れるといったことが、今の官尊民卑の風を助長させた本源である。
[世界と日本(林子平の生きた時代に関連して)]
世界の地図や地球儀を見て珍しく思った時代もあるが、それに比べて、昨今の日本は実に進んだものである。
外国の書物を拾い読みするくらいの者は、どこの村落へ行っても一人や二人は在る。また、外国人を相手に、たとえ片言にもせよ話のできぬ者は、恥ずかしくて交際場裏へ出ることができぬと言われるほどの時代になって、銀座へ行けばモダンガールとか称する変な女にぶっつかって、気が遠くなる。ラジオを聞けば、豚の臨終によく聞く声で歌を歌う人が多く、解っても解らないないでも、真面目な顔してそれを聞いていなければ、時代に遅れる人として、ろくに付合ってもくれないというほどに、物騒な世の中なってしまった。
進歩といえば進歩に違いない、とも思うが、馬鹿らしいといえば馬鹿らしくもある。何ということなく外国の真似をするのが、今の謂わゆる文化というものであって、本当に外国の文化を心に味わってこれを日本化する、といったような気の利いたことは、薬にしたくもない。ただフワフワとして、外国かぶれに日を送っているのが、現在の国状である。
筆者(わたし)はいたずらに外国の文化を呪うものではないが、さりとて、自国の滅亡を賭してまでも、皮相の文化を取り入れなければならぬ、というだけの熱心は持っていないのである。
今時になって、70年前の攘夷論をふりかざすほどの愚人でもないが、世界を通じてどこの国にも持ち合せのない、美しい国情と、各人の道徳観念だけは、何とかして取り留めておきたい、と思う一人だ。
外国の文化をいかに取り入れても、堅い覚悟さえ持っていたら、国家の前途は何の憂患もなくてすむのだが、今の日本人にこうした心が有るか無いか、それさえすこぶる疑問である。
幕末の人にはこの心があったから、たとえ議論の上では攘夷開国と別れていても、国家の基礎には何の狂いもなかった。そこで、今の若い人たちは、幕末の歴史を調べて、その時代の人物を知るのが最も必要なことである。