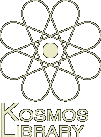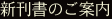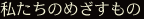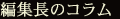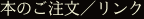第13回 カフカ語録--補遺
ドクトル・カフカは寛容と善意の化身のような人だ。彼のために保険局でいざこざがあったなどということは、およそ思い出せない。しかもあの人の人付き合いのよさは、弱さとか妥協とかを表わすものではない。それどころかドクトル・カフカの人付き合いのいいのは、周囲のどんな人間に対しても、彼の極度の正確で公正でしかも理解に満ちた仕方で接するために、いつの間にかこちらも同じ態度をとらざるを得ない、そういうところにあるのだ。皆は彼のことばに相槌をうつ。彼の意見とどうしても合わない場合には、異を唱えなくともいいようにむしろ黙ってしまう。じつはそういうこともよくあるのだ。カフカは全く独特で、あらゆる通俗と権威に逆らうような考え方を表明することが多いからだ。傷害保険局の連中は必ずしも彼を理解しているとはいえないだろうが、それでも彼を好いている。彼は彼らにとっては格別の聖者だ。しかし彼は、他の多くの人間にとってもそうなのだ。
人間愛はしばしば危機を孕むものだ。だからそれは、偉大な道徳財の一つでもあるのだ。ドクトル・カフカはユダヤ人だが、それでいて彼は、うちの役所の善良で愛すべきカソリックやプロテスタント諸君よりも、はるかにキリスト教の隣人愛を行うことが出来る。彼らはそのことを遅かれ早かれ恥じねばならぬだろう。そうするとなにか卑劣なことが始まりかねない。人間は一つの欠点をもっと大きな欠点でもって包み隠しがちなものだ。なにかで挙げられた役人が、カフカの法の操作のことを喋ってしまうことも充分考えられる。ドクトル・カフカはだから、彼の人間愛ををもう少し用心して扱わねばならいのだよ。そう彼に言っておきなさい。
お父さんの見ていらっしゃる通りだというわけではありません。キリスト教の人間愛とユダヤ精神の間に対立はありません。それどころか、人間愛はユダヤ人の倫理的努力の結晶です。キリストは、その救世の福音を全世界に齎した一ユダヤ人だったのです。さらに、物質的にも精神的にも--すべての価値は一つの冒険に結びついている。すべての価値は身をもって碓証せねばならぬからです。それから周囲の人たちの羞恥心について言えば、お父さんのおっしゃることは正しい。人間はお互い無用の刺激を避けねばいけません。私たちはデーモンに憑かれた時代に生きているのだから、善と正義を行うにも丁度犯罪のように、じつにひっそりと人知れず行って始めて、それはどうにか実現できるものかも知れません。戦争と革命は消えてしまうことはないでしょう。それどころではない。私たちの感情が冷えるにつれて、戦争と革命は灼熱するのです。
心は、二つの寝室のある家です。一方の部屋には苦しみが、一方には喜びが住んでいます。だから人は、あまり大声で笑ってはいけない。さもないと隣室の苦悩の目をさましてしまう。
◇
いや、そのときこそ、あなたは落着きによって、思いやりと忍耐によって、つまりは--あなたの愛情によって--両親のなかに、すでにお二人の内部に死滅しつつあるものを、もう一度目覚めさせねばなりません。あなたはどれほど殴られても不公正な目にあっても、お二人を愛し、公正と自尊心にまで導かねばなりません。何故なら、不公正とは何ものでしょうか。それは人間のまともなあり方ではない。それは道にさ迷い、行き倒れ、塵のなかを這いずり廻ることであり、人間の品位にふさわしくない姿勢のことなのです。あなたは両親を二人の行き倒れのように、愛情の手でもって助け起こさねばなりません。それがあなたの務めです。それは私たちすべての務めです。でなくて、私たちは何が人間でしょうか。あなたは、苦痛のあまりお二人を断罪してはならないのです。
忍耐は、すべての状況に対する特効薬です。われわれは、すべてのものと共振し、すべてに身を捧げ、しかも落着いて忍耐強くなければなりません。……自己克服に始まる、克服という行為があるのみです。これは避けるわけにはいかない。この道を逃れるならば、必ず破滅が待っています。忍耐強くすべてを受入れ、成長しなければなりません。不安な自我の限界は、愛によってのみ打ち破られる。私たちの足もとにかさこそと音を立てる枯葉の向うに、すでに若い新鮮な春の緑を見、そして忍耐し、待たねばなりません。忍耐こそ、すべての夢を実現させる真の、唯一の基盤です。
著者グスタフ・ヤノーホは、去る三月一日六十五歳の誕生日を迎え、三月五日「生涯にこれほど憧れたことのなかった春と新生」を待たずして、帰らぬ人となった。