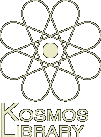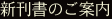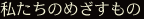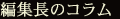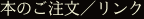第14回 セリーヌ『夜の果ての旅』--早く目覚めすぎた人間の悲劇
いよいよ新しいミレニアムの夜明けを目前に控えた今、サングラハの会員の皆様はどのような思いでお過ごしでしょうか? 私たちの心の中の二つの部屋の一方には「希望」が、そしてもう一方には「絶望」が住んでいて、私たちの多くはおそらくその間のどこかに佇んだまま、不安げなまなざしで漠然と未来を見遣っているのではないでしょうか?
かつて支那の小説家魯迅が「絶望の虚妄なるは希望の虚妄なるに相同じい」、言い換えれば、絶望も希望も虚妄である点で変わらないというふうなことを言ったと竹内好著『魯迅』の中で見たことを覚えています。このように肝を据えて、過去に絶望することも、あるいは未来に漠然と希望を抱くこともなく、朝目が覚めたら、今日もまた生きているのだと思ってその日一日を精一杯生きていくこともまた、一つの生き方なのかもしれません。
今年の初めにアナン国連事務総長が、新年の挨拶の中で「人類は今や運命共同体になった。道は相当険しいが、みんなで力を合わせればなんとかなるかもしれない」というようなことを述べたというニュースを聞いた時、ああここにもまた「世界中心的」スタンスに立って世界を見渡している人がいるようだなという印象を受けました。
新しいミレニアムには、いよいよますます自己中心的、自集団(家族、市町村、会社など)、自文化、自国家中心的スタンスを含みつつ超えて世界中心的スタンスに立って物事を考えることが求められることでしょう。しかし現実には、新しいミレニアムが始まっても、このスタンスに立った人は当分の間は相当な危険と孤立を覚悟しなけれならないでしょう。なぜならこれは、ミゲル・ルイスの言う「みんなが酔っぱらっているパーティーで一人だけしらふでいる」ような「覚醒」を伴うからです。
ウイルバーの本などで悟りに至までの壮大な人間進化・発達論が気軽に読めるようになった現在も、真に世界中心的と言えるスタンスに立っている人はまだそう多くはいないでしょう。ですから、仮に第一次世界大戦あたりまで遡ったらそんな人の数はもっと少なく、したがってそのスタンスで目覚めてしまったら、いかほど孤独であったか想像しうるというものです。
今回ご紹介させていただくセリーヌもそんな人の一人です(あるいは、少なくとも筆者はそう思っています)。そのセリーヌの『夜の果ての旅』(中央公論社、一九六四)には訳者の生田耕作さんの「解説」が付されているのですが、それは解説の域を超えた深く感動的な名文です。それによると、一八九四年(明治二十七年)(クリシュナムルティが生まれる一年前)にフランスのセーヌ県で生まれたセリーヌは、二十歳の時、第一次世界大戦においてフランドルの戦場に騎兵軍曹として従軍。大戦終了後、医学の勉強を始め、二十五歳で結婚。三十歳の時パリ医科大学から医学博士号を授けられるが、翌年離婚。約束されていた社会的地位と平穏な家庭生活を放擲、アフリカ植民地に渡って黄熱病および眠り病予防のための研究に従事。三十四歳の時、フランスに戻って医者を開業。一九三一年(三十四歳の時)に『夜の果ての旅』を出版。その後苦難の人生を経て、一九六一年、六十七歳の時、最後の長篇『リゴドン踊り』を執筆中に脳溢血で倒れる。「解説」の冒頭で生田氏は次のように述べています。
セリーヌは「七月一日、パリ郊外ムードンの隠栖所において、不遇の生涯をとじた。地区司祭から葬儀の執行を拒否され、《戦犯文学者》《国賊作家》セリーヌの遺体は、おりからの小雨空の下を、なかば秘密裡に、少数の友人と家族の者だけに見送られ、ムードン墓地の鉄道線路わきの土地に、さびしく葬り去られた。故人の生前の意志に従って、墓石には、ただ一語《否》の文字だけが刻みつけられた。
ほとんど時を同じくして世を去った(セリーヌの死亡の翌日)世界的な流行作家ヘミングウェイの名声につつまれた華々しい死にくらべて、迫害と汚名に傷ついた《敗残の巨人》……セリーヌのあまりにも痛ましい最期であった。
だが、一切の権力を、組織を、いな全世界、全歴史、全人類の欺瞞を呪詛し、その糾弾に生涯を賭け、ついに絶望的な闘いに傷つき倒れた《呪われた作家》にとって、この不名誉な末路こそ、むしろふさわしい最後の栄冠であったともいえるだろう。
ある評者は「これこそはまさしく類のない葬儀、セリーヌにふさわしいものであった。腐敗した時代と国家においては、芸術家は、ましては彼ほどの桁はずれの予言者は、これ以外の生涯は持ちえようはずはなかったのだ」と述べています。晩年には、戦犯宣告、一年余りにわたる牢獄生活、文壇からの抹殺、生活の困窮と、文学者としてまた人間として、悲惨のどん底に置かれていたのです。
セリーヌの生涯を見ていると、「魂がその幸福なる神との一体感を捨て去る決心をするのは、この闘争に満ちた、戦争によって傷ついた惑星上に人間の肉体を持って現れるためである。このような決心は、素晴らしいが故の危険性もはらんでいる。危険にさらされることこそ、何が魂を満足させるのかを立証する唯一の方法だ」という、フレデリック・ヴィーダマン著『魂のプロセス』の中の言葉を思い出します。しかもセリーヌの魂はまさに「荒魂」とも言うべき激烈なものであり、それからほとばしり出る言葉は読む者を激しく揺さぶらずにはいません。
このあまり類を見ない過激な魂を誕生させるきっかけになったのは、やはり第一次世界大戦での従軍体験でした。彼は「見てしまった」のです--戦争の実態、戦争を陰で支えているシステム、市民の心理構造等々を。つまり、「戦争とは、われわれの日常生活の壮大で血なまぐさい投影である」(クリシュナムルティ)ということを。『夜の果ての旅』の冒頭には「ひとの世は冬の旅、夜の旅。一筋の光も射さぬ空のもと、われらは道を求めゆく」という「スイス衛兵の歌」(一九七三年)が載っていますが、まさにその衛兵たちのように主人公もセリーヌも一気に暗黒の世界、血なまぐさい屠殺場に飛び込んだのです。実際、二十歳のセリーヌは危険な伝令任務を率先志願し、激しい砲火を潜り、生命を賭して任務を遂行しています。そのさい腕および頭部に重傷を負いますが、その任務遂行に対して武勲章を授けられ、『国民画報』誌は彼の献身的愛国行為を讃えています。
しかし表向きの華々しさとは裏腹に、青年セリーヌは戦争の正体を一気に見抜いてしまいます。負傷のおかげでパリに戻り、療養していた物語の主人公フェルディナンは、アメリカからフランスを救うのを手伝うために来ていた愛国心に燃えたローラという名の美少女と次のような対話を交わしています。
「……僕が死んでも火葬だけはご勘弁ねがいたいほどさ! ……骸骨のほうが、なんといっても、まだしも人間に近いからね、灰よりはまだ生き返りやすい……灰になればおしまいだよ! ……だからさ、戦争が……
「まあ、そいじゃ、あなたは本当に腰抜けなのね、フェルディナン! いやらしい人、どぶ鼠みたい……」
「そうだよ、ほんとの腰抜けさ、ローラ、僕は戦争を否定するんだ、それに戦争のお添え物も、何から何まで……僕は戦争に弱音をはいたりはせんよ……僕はあきらめんつもりだ、僕は……めそめそ泣いたりはせん……そいつに荷担する連中も、なにもかも、その連中とも、戦争とも、僕はなんのかかり合いも持ちたくない。たとえ奴らが七億九千五百万人で、僕のほうはひとりぼっちでも、まちがってるのは奴らのほうさ、ローラ、そして正しいのは僕のほうさ、なぜなら僕の望みは僕にしかわからんのだから。僕はもう死ぬのはごめんさ」
「でも戦争を否定したりはできないわ、フェルディナン! 祖国が危機に瀕しているときに、戦争を否定するなんて、気違いか臆病者ぐらいよ……」
「そんなら、気違いと臆病者万歳さ! いや気違いと臆病者生き残れだ」
続いて、「百年戦争」に言及し、その間に殺された兵隊の一人でも名前を思い出せるだろうかとローラに問いただし、「奴らは犬死したんだ……まったくの犬死さ、ばかな奴らさ!」と吐き捨てるように言っています(ついでながら、私たちの父親の多くは、第二次世界大戦で遅ればせながら「消耗品」としての役割をいやというほど味わわされたわけです)。第一次世界大戦中にこう言った時、主人公もセリーヌも共に自国家中心主義を飛び越えてしまったと言いうるでしょう。もちろん、そんなことを公言したらたちまち軍法会議にかけられて処刑されるか、気違い病院に送られてしまうでしょう。ですから、犬死しないためには、表向きは愛国青年のふりをしながら、なんとか集団的狂気に感染しないように気をつけつつ、うまく立ち回って生き延びるしかないわけです。「たとえ奴らが七億九千五百万人で、僕のほうはひとりぼっちでも、まちがってるのは奴らのほうさ」とフェルディナンが言っていますが、実際にセリーヌは脳溢血で倒れるまで一貫して、むしろ激しさの度合いを高めつつこの態度を保ち続けています。
『夜の果ての旅』は一九三二年に出版され(当時としては異例の、わずか数日で五万部が売れた)たのですが、その内容に西欧ブルジョワジーの腐敗ぶりへの激しい批判を見て取った共産主義者たちは、セリーヌに好意的な態度を示し、それが機縁で彼は一九三七年にソヴィエト文壇の招きでソヴィエトを旅しています。が、帰国後彼が発表した『懺悔』という文書で彼は激烈なソヴィエト批判を展開し、ソヴィエト・コミュニズムの偽善性、機械主義、プロレタリアの幸福の神話に激しい攻撃を加えています。それまでは左翼的アナーキストとして左翼陣営におおむね好意的に評価されていた彼は、一転してこの反共文書によって共産党と完全に袂を分かちます。フランス共産党の機関紙『ユマニテ』はセリーヌを《人間の敵》ときめつけ、ソヴィエトの御用作家ゴーリキイは作家集会においてセリーヌをファシストとして糾弾するといったありさまでした。
問題の反共文書の中でセリーヌは次のように述べています。「われわれの社会は物質的豊かさのもとで傾きかかっている、がそれは精神的貧しさのもとでくたばりつつある……合理的コミュニズムも同じこと、詩人のいない文明のもとでくたばってしまうだろう。コミュニズムは、なによりもまず《狂気》でなければならぬ、なにものにもまして《詩》でなければならぬ。詩人のいないコミュニズム、科学的で、理屈ずくめで合理的で、物質中心的で、官僚的な、鼻もちならぬ連中どもの、ごますりどもの、たいそうな言葉のコミュニズムは、徹底的に熱意を欠いた、散文的な、卑劣きわまる強制奴隷制度、地獄の挑戦、悪よりもさらに悪い改革手段にすぎない」
ヨーロッパが破滅--第ニ次世界大戦--に向かいつつある中、セリーヌの攻撃はヨーロッパ人、白人種全体に、とりわけ白人の頽廃、不正の象徴としてのユダヤ人資本家の戦争挑発陰謀に向けられます。彼の使う《ユダヤ人》という言葉は《ブルジョワ》の代名詞程度だったのですが、しかしそうした反ユダヤ主義的著作や言動によって、戦後戦犯の罪に問われ、「国賊作家」の汚名をこうむる不幸を招いてしまいます。
「戦後セリーヌの前に待ち受けていたものはまさしく茨の道であった。暴徒による家宅襲撃、愛妻リュセットと飼猫ベベールをともなって決死のフランス脱出、戦禍のドイツを横切り命からがらのデンマーク亡命、厳寒の北国での二年近い牢獄生活、戦犯宣告、文壇からの黙殺、生活苦。現代史の犠牲者、二十世紀のオデュッセウス、セリーヌの苦難の記録は、晩年の諸作品……に独創的な灰色の文体でもって、くりかえし物語られている」と「解説」で生田氏は述べています。
「セリーヌが描くのは現実ではない、現実が浮き出す幻覚である」というアンドレ・ジードの言葉に対して、生田氏は次のように述べています。
だがこの幻覚がかりに精神錯乱者のたんなる白日夢にすぎぬとすれば、セリーヌの作品はこれほどまでに激しい衝撃を与えるわけはなく、ましてや作者と作品の距離が常識化された現代において、作者がこれほどまでに深刻な憎悪を読者のなかによびさますこともありえないであろう。セリーヌの攻撃的姿勢は、善良な《市民》の怨恨をかき立てるものを含んでいるのだ----それはいわば……貞節を信じつづけてきた妻の不貞現場を見せつけられた男の恨みにもたとえられる。確固不動のものと信じつづけてきた既成理念に裏切られた人間の怒りである。国家も、戦争も、正義も、愛も、イデオロギーも、政治も、ヒューマニズムも、すべてはセリーヌの作品のなかでこっぱ微塵に粉砕される。教え込まれ、信じ込み、その上にあぐらをかいてきた理想、すべてが突如得体の知れぬ酸のもとに光沢を失い、もろくも潰え去り、われわれは情け容赦なく一挙に野蛮状態にひきもどされ、白紙からの再出発をしいられるのだ。
注意すべきことは、こうした虚偽・欺瞞への激しい攻撃の裏には、権力意志への恐怖と、《愛》《名誉》《富》《立身》など、空疎な美辞麗句への気恥ずかしさが潜んでいるということです。事実、開業医セリーヌは、権力者や金持ちたちを激しく攻撃する著述に専念する一方で、パリの場末のクリシイで貧民相手の町医者として、いわばフランス版「赤鬚」としての活動を終生続けています。もっとも、一九五一年、五十七歳の時、特赦を得て国外から妻と共にフランスに戻り、パリ郊外の離れ家で開業したものの、それまでの彼に対する悪評を知っていた患者たちは、しばらくは寄りつかなかったようです。それで妻がバレー教師を内職に、生活を助け、以後終生彼はこの住居を離れず、動物を友とし、執筆に専念しつつ、隠遁生活を送っています。
セリーヌの生涯をたどっていると、筆者は自分の心が大いに鍛えられ、生きることへのバネを与えられるのを感じます。近々そのセリーヌへの畏敬の念をこめて、『クリシュナムルティの教育・人生論--心理的アウトサイダーとしての新しい人間の可能性』を出したいと思っています。あまりにも早い時点で世界中心的スタンスに立った人間としていろいろな点で共通点のあるこの二人の巨人に、今後も導きの糸であり続けてもらおうと思っています。