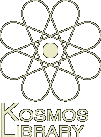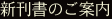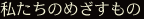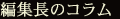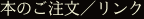第15回 『日本奇僧伝』--仏教アウトサイダーの世界
筆者は現在
『カミング・ホーム』という、いわば「文化横断的〈悟り〉論」のようなものを出すべく、高瀬さんにお願いした翻訳を見直させていただき、ようやく終了しかかっているところです。ハイデッガーとクリシュナムルティから始まって、ラーマクリシュナ、ラマナ・マハリシ、禅の十牛図、プロティノス、ユダヤ教ハシディズム、聖パウロ、バワ・ムヘイヤッディーン(現代のスーフィー)、さらには求道に関して『易経』に立てた伺いに対する易断の記録まで、大変バラエティーに富んでいて面白い内容なのですが、こちらの不勉強を思い知らされて四苦八苦しています。
なかでも『易経』はこの機会にさっと目を通してみて、なかなか面白いと思ったというよりは、今から三千年も前に書かれたとはとても思えない内容なのに今さらのように驚きました。例えば卦十六「蠱(こ)」。蠱とは、皿を虫が食い荒らす、または皿に盛った食べ物に虫が湧いていること。泰平が続くと内部に腐敗と混乱が進行し、下僚はひたすらへつらい、上司はなすことなく日を送る。また、年増が若い男を誘惑するさまをも表している。天変地異、風気紊乱、まことに多事多難である。しかし絶望することはない。窮すれば通ず、矛盾が深ければ深いほど逆に根本的解決が可能となる。これを機会に、内部に巣食う病根を徹底的に摘出することだ。腐敗と混乱の時は、同時に革新、新生の時代でもある。そう『中国の思想[IV]易経』(丸山松幸訳、徳間書店)に書かれています。
易経を読めば読むほど、人間は進化などしていないのではないかという疑いが深まります。さらに「陰極まれば陽に転ず」というのも、なんだか疑わしい。それどころか、易経が書かれてから三千年の間に人類が蓄積してきた悪いカルマがヘドロのように溜まりに溜まって、人類の未来を厚い黒雲のように覆っているのではないのか? 易経の解説書『繋辞下伝』には、「善行も数多く積まなければ名誉を得るに至らないし、悪事も数多く重ねなければ身を滅ぼすに至らない。ところが小人は、わずかの善行など利益にならぬと考えて行おうとせず、わずかの悪事ならたいしたことはないと考えて中止しない。しかし、こうして悪事を重ねるうちに、ついには身の破滅は逃れようもなくなる」と書いてあります。実に意味深い言葉だと思います。
◇
先日、
『カミング・ホーム』の参考書を買いに近所の書店に出かけて探していたところ、ふと『日本奇僧伝』を見つけました。著者は宮本啓一さん、いや先生で、筑摩書房から「ちくま学芸文庫」の一册として一九九八年発行となっていました。実は、宮本先生とは旧知の間柄で、昔、春秋社編集長だった岡野主幹から小生にクリシュナムルティの『生と覚醒のコメンタリー』の翻訳依頼があった時、宮本先生が編集部員として担当してくださったのです。原稿の受け渡しの時、本郷の小生の事務所の付近の寿司やで何度も歓談する機会があり、その時小生が深草の元政上人の書いた『扶桑隠逸伝』というのを阿佐ヶ谷の古書店で見つけ、面白そうだと思っていたところ、宮本先生が関心がおありのようなのでお見せしたのです。案の定気に入られ、とても面白いとあちこち吹聴していたところ、やがて東京書籍の編集の方が興味を持たれ、奇僧の逸話を手ごろな一冊の本にまとめてくれということになり、『扶桑隠逸伝』をヒントにできあがったのが『日本奇僧伝』というわけです。出版されたのが一九八五年のことですから、ずいぶん以前のことですが、版を改めて筑摩書房から文庫で出ていることを知って、本当に我が事のように嬉しく思ったしだいです。
「文庫版へのあとがき」を読むと、宮本先生のスタンスがよくわかります。旧版が出てから十二年間、「根本的な疑念をもとに取り組んできたテーマが、少なくともひとつはある。それは、大乗仏教批判、ひいては救済主義批判である。そして、日本仏教はすべて大乗仏教を(奇妙に変形させながら)引き継いできたものであるから、私のそのテーマのかなり重要な部分は、当然の成り行きで日本仏教批判ということになる。」
そして、最初期の仏教やゴータマ・ブッダの思想を調べれば調べるほど、「大乗仏教、ひいては日本仏教が、仏教の出発点からいかに遠ざかっているか、いかにそれをないがしろにしているかが、ほとんど耐えがたいほどの思いをともなって浮き彫りになってくる。大乗仏教は、ゴータマ・ブッダの透徹した生のニヒリズムと経験論、それに裏打ちされたプラグマティズム、そしてかれの中道精神、これらからまったく逸脱してしまっているのである。ところが、わが国の仏教学者のほとんどは、僧籍にある人か、熱心な(大乗)仏教信者かであるため、こうした問題点を指摘することがない。たとえ薄々感じてはいても、おそらく見て見ぬふりをしているのである。嘆かわしい話であり、アカデミズムのかけらもない。
思えば、本書は、こうした私の取り組みの出発点をなすものであった。本書で取り上げた人物の圧倒的多数は、日本仏教のいわば表舞台というところで活躍した人たちではなく、表舞台を徹底的に忌避し、批判した人たちであり、したがって、ほとんどが、無名に近い人たちである。そのため、本書は日本仏教史を、ただ漠然と「正面」から知ろうとする向きからは無視されたきらいがある。空海も、法然も、親鸞も、道元もまったく取り上げてはいないのであるから、無理もないのかもしれない。
しかし、読者諸氏もしっかり目覚めてほしい。地下鉄サリン事件など、オウム真理教の恐るべき悪事が露わになってからもう三年も経つ。しかし、驚くべきことに、日本仏教側、とくに仏教学者から、きちんとした視点よりするオウム真理教批判はひとつも世に出されていない。いや、真相は、驚くべきというよりも当然のことなのである。というのも、オウム真理教は、大乗仏教およびその突出形態である密教(金剛乗)の鬼子とはいってもれっきとした子供であり、したがって、大乗仏教に身を寄せる人たちは、それらを批判することができないからである。それを批判するという作業は、そういう人たちにとって、みずからの依って立つ基盤を切り崩すことにほかならないのである。
オウム真理教を根本的に批判することのできない仏教など、あるいは仏教学者など、少なくとも「オウム以後」にあって、どれほどの存在意義があろうか。
そういう思いを抱きながら、本書を改めて読み直してみたが、軽微な問題を除いて、その基本構想が、古びるどころか、いやまさに「オウム以後」の今日、新鮮な光を放っているのが確認でき、著者としては安堵している。」
-----
宮本先生は現在、国学院大学文学部教授に任じておられます。やや長くなりましたが「あとがき」をご紹介したのは、あたかたもブッダの気迫が直接伝わって来るかのような烈々たる批判精神をぜひ知っていただきたかったからです。
◇
さて、『日本奇僧伝』では、奇僧が「異能の人」「反骨の人」「隠逸の人」の三部に分けて紹介されています。「異能の人」の部には目覚ましい神通(力)を発揮したとされる人(仙人を含む)を、「反骨の人」の部には世俗の権力に対して強烈な反骨の行動をとった人を、「隠逸の人」の部には徹底的に粗末な衣食住を楽しんだ、いわゆる頭陀行の人が収められています。ここでは、そのうちのほんの一人だけをご紹介しておくにとどめます。
隠逸の人の一人で、平等という僧がいます。この人は、世俗の生活を捨てて山、すなわち寺院に入り、そこで長年修行しながらも、またその山を捨てるという、いわば二重の出家を遂げた人の一人です。二重の出家が必要だったのは、宮本先生によれば、「比叡山を筆頭とする山が、世俗の権力と癒着して腐敗していたということにもよるし、また、それだけ末法意識が強かったということをも示している」ということです。
この平等は、比叡山におり、弟子もいたのですが、ある日、厠(かわや=便所)で遁世の決意を突然固め、そのまま出奔して乞食になったという奇抜な逸話の持ち主で、その決意を固めた場面は次のようなものです。
少し前の時代、比叡山に、平等供奉という貴い人がいた。
あるときのことである。厠に籠っていたとき、世の中が、朝日に消える露のように無常であることをさとるこころがにわかに起こった。このようにはかない世の中に、名利にのみほだされて、本来なら厭うべき不浄の身を惜しみつつ、どうして空しく明かし暮らしてきたのであろうかと思い始めると、今までのことも悔やまれ、長年住み慣れた所もうとましく感ぜられた。もはや二度と再びここに帰ってくることはあるまいと思い定め、下着の白衣に足駄というそのときの出で立ちのまま、衣などを着ることもなしに、これといったあてどもなく飛び出して、とりあえず西の坂(雲母坂)を下り、京に、向かった。
こうして成り行きに任せて淀のあたりの渡し場から、船頭の好意で下りの船に乗せてもらい、伊予の国にたどり着き、時をかまわずさまよい歩き、家々の門口で乞食をしながら日を送っていました。比叡山では突然平等がいなくなったので、弟子たちが大騒ぎし、あちこち捜しまわったのですが見つからないので、とうとう泣く泣く平等を弔う仏事を執り行った。
ある日、物乞いのため伊予の国司の館に入っていくと、たまたまそこに逗留していた平等の弟子の浄真阿闍梨が乞食を見かけます。まるで人間とは思えない姿で、いたいたしいほど痩せ衰え、ぼろがあちこちから垂れ下がっているような綴り合わせの衣を一枚引き被っただけである。まことにみすぼらしいのだが、どこか見覚えがあるように思われたのでよくよく見つめて考えてみると、何とわが師ではないか。胸があふれる思いで、飛び出し、師の手を取って縁の上に上がらせた。伊予守などが驚き怪しむ中、阿闍梨は事の次第を泣く泣く語ったが、平等の方は終始ことば少なく、そしていきなり無理やり暇乞いをして足早に去っていってしまった。
その後あちこち探したもののついに見つからなかったのだが、はるかに時を経て、ある山人が、人も通わぬ深山の奥の清水のある所に死人がいると知らせにきた。これを聞いた阿闍梨は、もしやという思いに駆られ、山人から聞いた場所を尋ねてみると、そこには平等が西に向かって端座し、合掌したまま入滅していた。まことに貴いことだと心を打たれながら、阿闍梨は泣く泣く弔いを行った。
平等のような僧が出てきた背景について、宮本先生は別の箇所で次のように述べています。
僧というのは、そもそも出家した人、つまり、世俗の生活と価値体系をきれいすっぱりと断ち切った人のはずである。であるから、生産に従事したり、蓄財に浮き身をやつすなどということは、少なくとも釈尊の時代には完全に御法度であった。日々の食い扶持は、日々の乞食、托鉢によって確保すべきで明日、明後日の食い扶持を思いわずらってはならないのである。
そしてまた、出家者の集団は、本来全員が平等なのであるが、やはり組織である以上、おのずから上下関係というものが必要になる。そこで古くは、受戒して正式に出家してからの年数の長短を、上下関係の基準とした、中国仏教では、この年数を法臘と呼び、それに基づく席次を臘次といったが、ともかく、出家の世界に、世俗の秩序原理が入りこむことはきつく戒められていた。
ところが御存じにように、わが国では長い間、出家の世界は、僧綱制度(明治になって廃止)によって世俗の権力の管理の下に置かれてきた。僧正、僧都などの序列が世俗法によって制定され、重要なポストは朝廷や幕府に任免権があるというのだからたまらない。
とはいえ、出家の方も出家の方で、世俗の権力から頂戴するポストをこの上ない名誉に思い、後生大事にありがたがたがるというありさまで、やがては、在俗時の家柄によって昇進のスピードが違うとか、人脈的にいってこちらよりもあちらの系列に入った方が有利だといったように、門閥、派閥が幅を利かせ、人事異動(?)が発表されるたびに山は一喜一憂し、貪瞋 が猛威を振るうこと、あたかも俗界におけるがごとしということも珍しくなくなった。というわけで、心ある僧たちは、名聞利養の道に迷い入ることをさけるため、重要なポストへの就任を固辞したり、山から出奔したりした。
冒頭にご紹介した易経の卦十八「蠱」には、隠退した君主または無位の尊者の心がけとして、「王侯に仕えず、野にいて一身を高潔に保つ。その志は模範とするに足る」とあります。