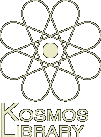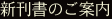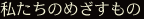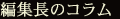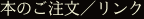第18回 「カルマ」再考
◇
◇
多くの東洋諸国がいま西洋に紹介しつつある、偉大なる知恵の中核となる言葉があります。それはサンスクリット語の「カルマ」で、西洋がたったいま理解し始めている概念です。もし私たちが衰退し、滅亡せずに、成長し、健康であり続けたいなら、私たちはそれを理解し、実行してみなければならないのです……。
カルマの法則は因果の法則です。私たちが世界に投入するあらゆる行為に対して、私たちはそれに等しく、ふさわしい反応を受けるのです。カルマの法則は、なぜ盗人は盗みに会うか、なぜ怒りっぽい人は怒気の世界に住むか、なぜ愛情深い人は愛情深い世界に住むかを説明しています……私たちは自分がまいた種を刈り取るのです。
カルマは私たちの人生に個的に作用し、さらにはこの惑星上の全人類に作用します。西洋はカルマの法則に対して完全に無意識であることによって、……全世界にとって実に多くの困難を引き起こしてきたのです。
白人種はとりわけ、地球上のほかのあらゆる人種を扱う上で、いくつかのゆゆしいカルマ的誤りを犯してきました。私たちが世界中に欲求不満と怒りを生み出してきたとしても驚くにあたりません。私たちは全員、いくつかの基本的態度を変えなければなりません。
マーカス・アレンは主にヴェトナム戦争(一九五四-七三)への反省を込めて語っており、今こそアメリカ人は西洋の最も偉大な師(キリスト)の教えを思い出し、それを実践に生かさなければならないというのです。
カルマの法則は因果の法則です。私たちが世界に投入するあらゆる行為に対して、私たちはそれに等しく、ふさわしい反応を受けるのです。カルマの法則は、なぜ盗人は盗みに会うか、なぜ怒りっぽい人は怒気の世界に住むか、なぜ愛情深い人は愛情深い世界に住むかを説明しています……私たちは自分がまいた種を刈り取るのです。
カルマは私たちの人生に個的に作用し、さらにはこの惑星上の全人類に作用します。西洋はカルマの法則に対して完全に無意識であることによって、……全世界にとって実に多くの困難を引き起こしてきたのです。
白人種はとりわけ、地球上のほかのあらゆる人種を扱う上で、いくつかのゆゆしいカルマ的誤りを犯してきました。私たちが世界中に欲求不満と怒りを生み出してきたとしても驚くにあたりません。私たちは全員、いくつかの基本的態度を変えなければなりません。
「汝の隣人を愛せよ」……「汝の隣人が汝にしてほしいと望むとおりに、汝の隣人に対せよ」……「汝がまく種のとおりに汝は刈り取る」
私たちは皆、他人を許し、認めることを学ばねばなりません。私たちは皆、他人と争うことをやめねばなりません。私たちは、ほかの人々を犠牲にして生きることをやめねばなりません。
◇
肉と血との神秘と奥義。キリストがこの神秘をその弟子たちに啓示した時に、それは彼らを戦慄せしめかつ魅惑した。「わが肉を食いわが血を飲む者は永生を受ける。われは最後の日にこれを蘇らすであろう。けだしわが肉は誠に食物であって、わが血は誠に飲物である。われを食する者はわれのごとく生きるであろう。」││「何という不思議な言葉であろう。誰かよくこれを聞きうるものがあろうか。彼はヨセフの子イエスではないか。彼の父母はわれわれの知るところではないか。どうして彼がその肉をわれわれに与えて食ましむることがでできよう。」
秘教的なカルマの解釈は次のことを認めている。完全に孤立した個人というのは単にわれわれの想像の作り事にすぎない。各人の生活は、地方的、国家的、大陸的、そしてついには地球的規模へと常に広がっていく円によって、全人類の生活とからみ合っている。各々の思考は、世界に広く行き渡っている精神的雰囲気によって影響される。また、各々の行為は、無意識のうちに、人類の一般的活動によって与えられる支配的かつ強力な示唆の協力で成し遂げられる。
今回のテロ事件も、こうしたより大きな「集団的カルマ」という観点からとらえ直す必要があるのではないかと感じています。なお、最近プロセス指向心理学の創始者アーノルド・ミンデルの書いた『紛争の心理学』(講談社現代新書、長沢哲監修・青木聡訳)が出版されました。とりわけ「テロリストと向き合う」というチャプターは、今回の事件について考える上で必読だと思われますので、お知らせしておきます。
◇
◇
◇
◇