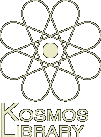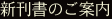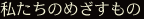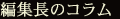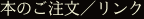第32回
■シルバーバーチ自身は何者だったのだろうか。
■なぜ今世紀になって出現したのだろうか。
■キリスト教を諸悪の根源のように批判しているが、その根拠は何なのだろうか。
■イエスは本当に磔刑にされたのだろうか。 等々……
■なぜ今世紀になって出現したのだろうか。
■キリスト教を諸悪の根源のように批判しているが、その根拠は何なのだろうか。
■イエスは本当に磔刑にされたのだろうか。 等々……
第1部 交霊会にまつわる「謎」と「なぜ?」
「謎」その2◇ なぜこの時代(二十世紀)に出現したのか?
「謎」その3◇ 霊言集が出版されるに至った経緯にも不可解な「?」が
「謎」その4◇ 霊言を活字化して公表する問題でなぜシルバーバーチは一言も口を挟まなかったのか?
「謎」その5◇ なぜ地上時代の身分も姓名も明かさなかったのか?
「謎」その6◇ バーバネルの死についても「なぜ?」が
●学者としての本分を貫いた人たち
●「事実」と「信仰」のはざ間で悩んだ人たち
●イエスの実像は? そして今、霊界でどうしているのか?
資料(2) フレデリック・マイヤース著「死の真相」--『永遠の大道』より
資料(3) ジョン・レナード著「「死」の現象とその過程」--『スピリチュアリズムの真髄』より
資料(4) モーリス・バーバネル著「宗教界による弾圧」--『これがスピリチュアリズムだ』より
資料(5) 「イエス自ら語った生い立ち」--『イエス・キリスト--忘れられた物語』より
資料(6) 「青年牧師との論争」--A・W・オースティ編『シルバーバーチの霊訓』より
文献(1) ハネン・スワッファー著『「あの世」から帰ってきた英国の新聞王・ノースクリフ』
文献(2) D・ダドレー著『西暦三二五年のキリスト教総会『第一回ニケーア公会議』の真相』
「謎」その2◇ なぜこの時代(二十世紀)に出現したのか?
「謎」その3◇ 霊言集が出版されるに至った経緯にも不可解な「?」が
「謎」その4◇ 霊言を活字化して公表する問題でなぜシルバーバーチは一言も口を挟まなかったのか?
「謎」その5◇ なぜ地上時代の身分も姓名も明かさなかったのか?
「謎」その6◇ バーバネルの死についても「なぜ?」が
●学者としての本分を貫いた人たち
●「事実」と「信仰」のはざ間で悩んだ人たち
●イエスの実像は? そして今、霊界でどうしているのか?
資料(2) フレデリック・マイヤース著「死の真相」--『永遠の大道』より
資料(3) ジョン・レナード著「「死」の現象とその過程」--『スピリチュアリズムの真髄』より
資料(4) モーリス・バーバネル著「宗教界による弾圧」--『これがスピリチュアリズムだ』より
資料(5) 「イエス自ら語った生い立ち」--『イエス・キリスト--忘れられた物語』より
資料(6) 「青年牧師との論争」--A・W・オースティ編『シルバーバーチの霊訓』より
文献(1) ハネン・スワッファー著『「あの世」から帰ってきた英国の新聞王・ノースクリフ』
文献(2) D・ダドレー著『西暦三二五年のキリスト教総会『第一回ニケーア公会議』の真相』
◇ ◇ ◇
エーテル体と肉体とが完全に融合している時は肉体は若々しく溌溂としているが、やがて高級な生体エネルギーは死後の生活で使用する身体、つまり幽体の充実のために抽き取られ、一方、低級なエネルギーも徐々に使い果たして老化していく。
岡尾正恵は庄六と称した。生国はどこだったか分からない。十四、五歳の時に両親に離れてから、京都の商家に縁があって養われていたが、その頃から人がらがしめやかで、よろづにわたってさとかった。それで主人も頼もしく思って、後には家をも譲りたい下心でいた。
……私の言う自由な時間とは、普通人が言う意味においての閑暇のことではない。外見的な閑暇はなお存在し、それは種々の法律や、時間を労働によって克服する必要を省略するのが目的である機械的な諸手段の完成によって、自己を擁護し、自己を一般化さえしてゆくのである。一例として、労働時間は法律によって割当てられ、計算せられている。
◇ ◇ ◇
読者の中には、本章のアプローチ全体--教師は人として生徒に関わりうるという信念--が、見込みのない非現実的なもので、かつ理想的であると感じている人がいるかもしれない。本質的に、教師にも生徒にもお互いの関係の中でかつ主題との関係の中で、創造的であることが、励みになるとはわかるものの、このような目標は全く不可能であると感じるかもしれない。不可能であると感じるのは一部の読者だけではない。一流大学理学部の科学者たちが、また一流大学の学者たちが、あらゆる生徒が創造的になるよう励まそうとすることは馬鹿げている、私たちには並の技術者や労働者が多数必要であり、少数の創造的な科学者や芸術家やリーダーが現れれば、それで十分であろうと、論じるのを聞いたことがある。