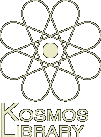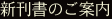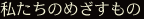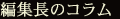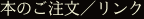第36回
久しぶりですが読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか? 異常な事件が続発していますが、「心の砂漠化」が急速に進行し、人間の心あるいは脳が異変をきたしつつあるのではないかと大いに危惧されます。蟹の中には、片方の爪が異常に大きく、もう片方の爪が異常に小さいのがいますが、知性だけが異常に発達し、感情が萎縮していて、ごく当たり前な感受性も育っていない、そんな人間が若者を中心に急増しているような気がします。というか、知性もまともに発達しておらず、暴力性だけが鬱積していて、条件が整うと外部へ向かって犯罪行為として爆発するか、あるいは内部に向かって自傷行為や自殺に行きつくのかもしれません。筆者の借家の隣家にも中学生頃から引き蘢り続けている男の子(現在は高校生の年齢)がおり、働きに出ている姉といざこざがあるらしく、しばしばかなりのわめき声が聞こえてくることがあります。どこの家でも多かれ少なかれ負のエネルギーが鬱積しているのではないでしょうか。
さて、前回はキャロライン・ブレイジャー[著]/藤田一照[訳]
『自己牢獄を超えて--仏教心理学入門』と
『〈あの世〉からの現地報告[三部作]:その(1) 死後の世界も自然界である』に続き、緊急出版として拙訳で
『クリシュナムルティの教育原論--心の砂漠化を防ぐために』(以下、『原論』)の刊行を予告いたしましたが、予定通り4月9日に全国配本いたしました。
これはインド独立後間もない時期にインドに行き、そこで教育者たちのグループを前にして行なった講話や質疑応答などを踏まえてクリシュナムルティ自身が書き下ろしたもので、原書は1955年にロンドンのビクター・ゴランツ社という、彼の本をかなり手がけた出版社から出されており、今も読み継がれています。
クリシュナムルティは早い時期から教育に関心があり、インドのリシヴァレーに最初の学校を建てたのは1925年、すなわち彼が30歳の時です。こうした彼の歩みについては、『原論』の「解説」やや詳しく述べておきました。また、解説では1946年頃からの彼のインドでの足跡を辿り、ついでに
『しなやかに生きるために--若い女性への手紙』の背景を詳しく紹介しておきました。この頃の彼は、第二次大戦中カリフォルニアのオーハイでたっぷり英気を養った後だけにきわめて元気溌溂としており、彼の長い人生の中でも特筆すべき時期だったと言えるでしょう。
内容は以下のとおりです。
■教育と人生の意義 ■正しい教育のあり方 ■知性、権威、英知
■教育と世界平和■学校■親と教師■性と結婚■芸術、美、創造
これらの章題はとりたてて目新しいものではなく、むしろまっとうすぎるくらいです。しかし書かれてあることは根源的という意味でなかなか「ラディカル」です。例えば次のような言葉。
何が人生の意義なのだろう? 何のために人生はあるのだろう? 何のためにわれわれは生き、奮闘努力しているのだろう?
もしわれわれが単に学位を得、より良い職に就き、より有能になり、他の人々に対するより大きな支配力を持つだけのために教育されているのなら、われわれの人生は浅薄で虚しいものになるだろう。
もしわれわれが単に科学者になり、書物に縛られた学者、あるいは知識に溺れている専門家になるだけのために教育されているのなら、われわれは世界の破壊と不幸に手を貸してしまうであろう。
ナショナリズムの分離主義的精神が火のように世界中に広まっている。さらなる拡張、より広範囲にわたる権力、より多くの豊かさを追求している人々によって愛国心が養成され、巧妙に利用されている。そしてわれわれの各々がこの過程に加わり、寄与している。なぜなら、われわれもまたこれらのものを望んでいるからである。他国の土地と国民を征服することは、商品ならびに政治的・宗教的イデオロギーのための新しい市場を与えてくれるのだ。
人は、こういった暴力と敵意のあらゆる表現を偏見のない精神で、つまり、それ自身をいかなる国、民族またはイデオロギーとも同一化させることなく、何が真実かを見出そうとする、そういう精神で見つめてみなければならない。
あるいは次のような言葉。
思うに、われわれは本当は武器を望んでいるのだ。われわれは、軍事力の誇示、制服、儀式、飲酒、騒音、暴力が好きなのである。われわれの日常生活はそれと同じ冷酷な浅薄さの小規模な反映なのであり、そしてわれわれは羨望や浅慮によって互いに滅ぼし合っているのだ。
われわれは裕福になることを欲している。そして豊かになればなるほど、それだけわれわれは酷薄になる。たとえわれわれが大金を慈善と教育に寄付しようと。犠牲者から略奪し尽くしてから、われわれは彼に略奪品のごく一部を返し、そしてそれをわれわれは博愛行為と称する。思うに、われわれは自分たちがどんな破局を準備しつつあるのか気づいていないのだ。われわれのほとんどはその日その日をできるだけ速やに、できるだけ考えずに過ごすようにしており、そして政府や抜け目ない政治家たちに自分の人生の指揮を委ねている。
正しい教育は明らかに主権政府にとって危険である--従ってそれは、粗雑または微妙な手段によって妨げられるのだ。少数者の掌中にある教育と食料は間をコントロールする手段になってきた。そして政府は、左のそれであれ右のそれであれ、われわれが商品と弾丸を生産するための効率的な機械であるかぎり、無頓着である。
さて、こうしたことが世界中で起こっているという事実は、市民であり教育者であり、既存の政府に責任があるわれわれが、自由かさもなければ隷属か、平和かさもなければ戦争か、人間にとっての幸福かさもなければ不幸かを根本のところで気にかけてはいないことを意味している。われわれはあちらこちらでちっぽけな改革をすることは望んでいるが、われわれのほとんどは現在の社会を解体して、まったく新しい構造を築き上げることを恐れている。なぜならこれは、われわれ自身の根源的変容を必要とするからである。
◇ ◇ ◇
編者は現在『クリシュナムルティの生と死』という、メアリー・ルティエンスによる伝記を翻訳中です。その中にクリシュナムルティが戦時中オーハイにいた時のことが出てきます。
一九四〇年にヒットラーがオランダとベルギーを潰滅させた後、Kは彼の多くのオランダ人の友人についての知らせをまったく受けなくなり、インドからの知らせもほとんどなくなった。フランスは六月二十二日に降伏した。……Kは、オーハイとハリウッドの両方で週に二回ずつグループ討論を開き始めた。彼はまたハクスレー夫妻と頻繁に会った。(Kの平和主義が、戦争中ずっとカリフォルニアに留まることへのハクスレーの罪悪感を和らげた。)一九四〇年の春に、オーク・グローブでKは八回の講話をしたが、彼が平和主義を説き、「あなた方の内なる戦争にあなた方は関心を持つべきです。外なる戦争にではなく。」と言った時、聴衆の多くは愛想をつかして立ち去っていった。
世界中が戦争の最中にある時に、この人はなんという呑気なことを言っているのだとアメリカ人の聴衆は思ったのでしょう。しかしたとえ一億人が戦争の必要を訴えようと、一貫して彼は反戦平和を唱え続けたのです。ここで思い出されるのは内村鑑三です。これについては拙著編訳
『片隅からの自由』の中の「戦争について」という論考で紹介しておきましたが、ここで改めて言及させていただきます。
◇ ◇ ◇
白鳥によると、第二次大戦後、鑑三が日露戦争・第二次大戦の頃、熱烈に徹底的に戦争反対を唱導していたことが思い出され、反戦論者として再評価され、改めて敬意を寄せられるようになったというのです。そもそも、「日清日露戦役の時には、戦争反対説などは何処にも現われていなかった」と白鳥は回想しています。鑑三でさえ、日清戦争の時には、それを「正義の戦」であるとして、英文で書いて、世界に向かって宣伝したりしていたのです。キリスト信者が戦争反対を唱えるのは当然なはずなのに、その当然のことを敢行する者が滅多になかったというわけです。第二次大戦中の宗教者たちの戦争協力についてはいろいろ議論され批判されてきたようですが、実はそれ以前から問題があったのです。日露戦争に反対して非戦論を唱えたのは、幸徳秋水などの社会主義者の他には、キリスト教徒の内村鑑三ぐらいだったようです。
日露戦争の頃、白鳥は読売新聞の記者として社会の各方面に取材しに出かけ、「戦争景気をよく見聞していたのだが、戦争を呪詛していた日本人は何処にもなかったと云ってよかった。大抵は讃美者であった」のです。さらに「文学者美術家教育家などに、戦争行為に対して懐疑の念を抱いていた者は絶無のようであった。そして戦争反対を唱える者がたまにあるとすると、それは変人奇人と思われるに過ぎなかった」というのです。鑑三もまた変人奇人の類いと見なされていたのでしょう。
「日露戦争中のある夏、私は、新聞の文学関係記事の担任者として、当時小川町に住んでいた佐々木信綱氏に招かれて晩餐を饗せられたことがあったが、その時の相客は老文学者依田学海と上田敏とであった。雑話のうちにトルストイの徹底的の非戦説が出ると、翁は『口先で話が極らなければ、腕ずくで勝負をつけるより外為方がないじゃないか』と、口角泡を飛ばして論じた。『トルストイは先生より年下ですよ』と上田が云うと、『そうか、年下のくせに生意気だ。学海先生のお説を聞きに来い』とふざけた口を利いて一座を笑わせた。トルストイの無抵抗主義なんかは、真面目に人に取合われない時代であった。内村のように馬鹿正直に、真剣に無抵抗主義を唱え、戦争廃止を唱えるのは、むしろ奇異の振舞なのであった」と回想しています。
日露戦争に勝利し、第一次大戦では対岸の火事で儲けた後、第二次大戦で領土を拡大し、大儲けをしようと思ったのが、あにはからんや徹底的に苦汁をなめてから、ようやく反戦論者が多数出現することになったのです。これに対して鑑三はどうだったのでしょう? 白鳥は彼の次の言葉を引用しています。
余は日露非開戦論者であるばかりではない。戦争絶対的廃止論者である。戦争は人を殺すことである。そうして人を殺すことは大罪悪である。そうして大罪悪を犯して個人も国家も永久に利益を収め得よう筈はない。
世には戦争の利益を説く者がある。然り、余も一時はかかる愚を唱えた者である。しかしながら今に至ってその愚の極みなりしを表白する。戦争の利益はその害毒を償うに足りない。戦争の利益は強盗の利益である。これは盗みし者の一時の利益であって、彼と盗まれし者との永久の不利益である。盗みし者の道徳はこれがために堕落し、その結果として、彼は終に彼が剣を抜いて盗みし物よりも、数層倍の物をもって、彼の罪悪を償わざるを得ざるに至る。もし世に大愚の極みと称するものがあれば、それは剣をもって国運の進歩を計らんとすることである。
が、こうした鑑三の非戦・軍備撤廃論にもかかわらず、「それは実際的に何の効果も」なく、「それに刺戟されて、小さな反戦運動が一つ起こされるものでもなかった」のです。それどころか、「政府をつついて、露国と開戦させようとする運動は、学者の間にさえ起こったのであったが、仏教徒の間には元よりのこと、キリスト教徒の間にも反戦運動の破片も現われなかった」と白鳥は回想しています。いかに当時の日本が好戦的な雰囲気に包まれていたかがわかります。
編者は最近阿佐ヶ谷の古書店で『内村鑑三思想選書・第1巻:世界の平和は如何にして来るか』という、1949年に出版された本を入手しました。ちょうどクリシュナムルティがインドで教育者たちに講話を行なっていた頃です。通読して、やはり偉い人だと改めて実感しました。終始一貫して大上段に構えて反戦を訴え続けていたのはひょっとしたらクリシュナムルティと鑑三ぐらいだったかもしれないと思いたくなりました。その気概あふれる言葉(『聖書之研究』明治36年11月19日)を少しだけ紹介しておきます。
戦争は始まるかも知れない、始まらないかも知れない。然り、戦争はすでに始まっている。今始まったのではない、カインがアベルを殺した時に始まったのである。人類は同胞相互を妬んでいる。憎んでいる、そうして兄弟を憎む者は兄弟を殺す者であると聖書に書いてある。神を畏れざる人類は、剣を以て戦わざる前に、その心においてはすでにすでに相互を屠りつつある。彼等が剣を抜いて同類を殺し、砲を放って隣人を屠るのは、この内心百鬼夜行の状態を外に顕すまでのことである。(これは「戦争はわれわれの日常生活の壮大で血なまぐさい投影である」というクリシュナムルティの言葉を思い出させます。)
剣を以て獲しものは、獲しものにあらずして盗みしものなり。而して盗みしものはついにまた他の奪うところとなる。戦争は罪悪なるのみならず愚策なり。もし物を得んと欲せば、正直なる労働を以てすべし。剣と銃とを以てして強盗の所業にならうべからず。過去六千年間の人類の歴史は、最も明白にこの一事を示すにあらずや。然るに二十世紀の今日、なおこの歴史の教訓を悟る能わずして、地を流してまでもわが意を張らんと欲す。ああ愚かなるかな人類、彼等は未だ地を嗣ぐの術を知らざるなり。
世にキリスト教国なるものありと信ずるなかれ。地上未だかかる国あるなし。兵を蓄える国はキリスト教国にあらず、海に兵艦を浮かべ、陸に砲車を引きながら、我はキリスト教国なりというものは偽善国なり。而してかかる国は英国なり、露国なり、米国なり、ドイツ国なり。彼等何の面目ありて、異教徒を教化せんとて宣教師を外国へ送るや。「医者よ、みずからを医せ。」
「蝮(まむし)の裔(すえ)」とは学者とバリサイ人とのみにあらず。今の世に在って開戦論をとなえて恥とせざるキリスト教の教師、牧師もまたこの類なり。キリストはかかる教法師に必ず告げて言い給わん、「かかる者は磨石(ひきうす)をその頸にかけられて海の深みに沈められん方、なお益なるべし」(マタイ伝18章6節)。
そして内村鑑三は、世界平和は「先ずわが心に充溢する大満足、大平康あって、然る後にすべての人との間に平和は来る……」と述べています。「国際連盟によって世界の恒久平和が来ると思うは、それこそ大いなる迷信である。……虎や狼のごとき自己中心の人類が如何に方法を講じたればとて、愛の結果たる平和を実現しようはずがない」と述べています。結局、クリシュナムルティが言うように「内に豊かな人間」だけが平和な生き方を実現できるということでしょう。なぜなら、内に貧しい人は、それを覆い隠すために貪欲に物を蓄えようとし、その過程で互いにぶつかり合うからです。
◇ ◇ ◇
最後に、現在クリシュナムルティの『既知からの自由』の刊行を準備中であることをお知らせしておきます。これは40年前に『自己変革の方法』として霞ヶ関書房から刊行されたもので、今も読み継がれている名著です。このたび大野龍一氏が翻訳を引き受けてくれ、よりわかりやすい訳文にしてくれました。6月刊行をめざしています。